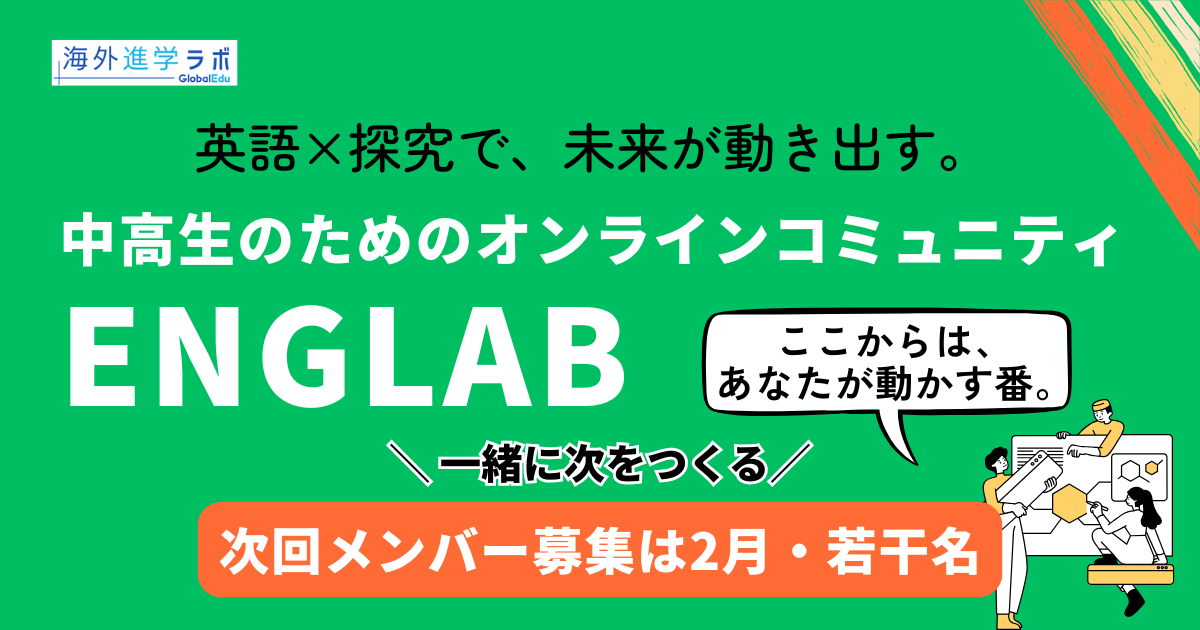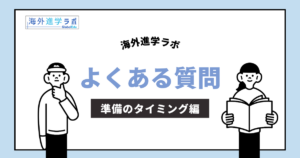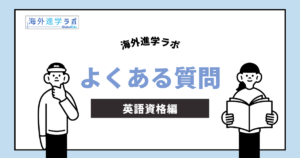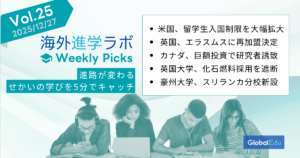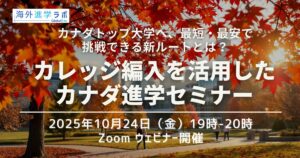海外進学Q&A|国内併願との比較編
国内と海外、学びの違いって何が大きい?
最大の違いは「学びの主体が誰か」という点です。
国内の大学ではカリキュラムが固定されており、講義形式で知識を得るスタイルが多いですが、海外では学生が自ら課題を見つけ、討論・レポート・プレゼンを通じて学ぶ形式が中心です。
 海外進学ラボ
海外進学ラボ学び方が異なることで、自律性・表現力・批判的思考が養われる点が、海外進学の魅力としてよく挙げられます
👇 関連情報をチェック
国内にしかない分野と、海外が強い分野は?
国内では法学部・教育学部・文学部など、日本の制度や歴史に深く関わる分野が強く、海外では開発学・国際関係・アントレプレナーシップ・AI/データサイエンスなど、グローバルで実践的な分野が盛んです。
志望分野によって適した進路が変わるため、希望する学びがどちらに強いかを比較するのは非常に重要です。
👇 関連情報をチェック
海外進学と国内総合選抜・推薦入試の大きな違いは何?
最大の違いは、「評価される視点」と「書類の自由度」にあります。
国内総合選抜・選抜型入試では、調査書・内申点・課題の達成度など学校内の実績が大きく関わりますが、海外進学では、本人の“ストーリー性”や“課外活動・探究の背景”が重視され、自由記述での表現力が問われます。
また、面接も日本では短時間で形式的な傾向がありますが、海外では対話型で、志望動機や思考力が深く掘り下げられるのが一般的です。
海外出願と国内総合型選抜は同時並行できる?
はい、十分可能です。むしろ、活動実績や自己PR文、志望理由の整理などは共通点が多く、効率的に準備できます。
ただし、国内外で出願時期や必要書類の形式が異なるため、スケジュール管理がとても重要になります。たとえば国内は夏〜秋、海外は秋〜冬がピークなので、計画的に逆算して動く必要があります。
ラボではこの両立を前提とした戦略的な個別相談も可能です。
👇 関連情報をチェック
併願時、出願のスケジュールがかぶることは?
あります。とくに国内の総合型選抜(9月〜11月)と、海外大学の出願時期(10月〜3月)は一部重なります。
そのため、どちらかに集中しすぎると、もう一方の準備に支障が出ることも。
早い段階で志望校ごとの締切を確認し、書類作成や資格取得を前倒しで進めておくと、精神的にも余裕が持てます。



進路設計は“逆算力”がカギになります
👇 関連情報をチェック
📖 いつから始めるべきか確認 準備のタイミング編|海外進学Q&A
出願費用や準備コストの違いは?
国内の総合選抜入試は1万7000円〜3.5万円程度の出願費用に対し、海外では1校あたり50〜100ドル程度(約7000〜1万5000円)、さらに英文証明書・スコア提出料・翻訳なども含めると準備コストは高めです。
ただし、出願校を絞って準備したり、早めの準備で費用を抑える工夫もできます。事前に予算を組んでおくと安心です。
国内出願書類と海外出願書類は兼用できる?
一部は兼用可能ですが、内容や視点にアレンジが必要です。
たとえば、国内推薦で使う「志望理由書」は日本語で文字数制限もあり、端的な結論が求められるのに対して、海外のパーソナルステートメントは“ストーリー性”“内省の深さ”が重視されます。
推薦状についても、国内では教員が学校指定用紙で作成することが多く、海外出願ではより個人に焦点を当てた内容が求められます。
👇 関連情報をチェック
📖 書類作成のポイント書類&実績編|海外進学Q&A
英検やTOEFLは国内でも活きる?
A: はい、活きます。特に英検準1級やTOEFL iBT80点以上は、多くの私立大学の総合型選抜や英語外部試験利用型入試で評価されます。また、出願時の加点や英語試験免除にもつながることがあります。
さらに、これらの資格取得は「努力の証明」として、志望理由や面接でも好印象を与える材料になります。



英語資格の取得は、国内外問わず進路の選択肢を広げる強力なツールです
👇 関連情報をチェック
📖 英語資格の選び方【進路とエイゴ #04】英検・IELTS・TOEFL、どれを選ぶ?
📖 英語資格が未来を変える【進路とエイゴ #05】英語資格が未来を変える──国内・海外進学で活きる本当の理由
🎓 スコアアップを目指す IELTS対策講座|オンライン完結・マンツーマン指導で5.5〜7.0突破
国内と海外のエッセイの違いって?
国内のエッセイ(志望理由書)は「結論 → 根拠」という論理構成が基本ですが、海外のパーソナルエッセイは「経験 → 気づき →成長 →今後につなげる」といった“物語形式”が主流です。
さらに、英語で書くことに加えて、文化的なコンテクストや価値観の表現も求められます。
形式が違う分、国内向けと海外向けで同じテーマを別の視点で書くことが必要です。
👇 関連情報をチェック
📖 書類の書き方を詳しく 書類&実績編|海外進学Q&A
探究活動や課外活動は両方で評価される?
はい、評価されます。
探究やボランティア、コンテストなどの課外活動は、国内では推薦・総合型選抜、海外では出願書類やエッセイの重要な要素になります。評価の視点は異なりますが、共通して求められるのは「活動の背景にある動機」や「学びの深さ」。



活動そのものよりも、“どう考え、どう行動し、何を得たか”の整理が大切です
👇 関連情報をチェック
🔗 活動を選ぶヒント 進路をひらく課外活動ナビ
📖 先輩の体験談を読む 中高生チャレンジレポート|日本・海外の中高生による挑戦・体験レポート
🎓 実践コミュニティで挑戦 ENGLAB|中高生が”未来をひらく力”を育てる学びの実践コミュニティ
自己PRの書き方は国内と海外でどう違う?
国内の自己PR文では、定型的な形式(結論→実績→意欲)が好まれますが、海外ではストーリー重視で、自分の経験から得た気づきを語る形式が多いです。
また、海外では過剰な謙遜よりも、自信をもって自分の強みを伝える姿勢が評価されます。
どちらの場合も“事実+内省”をバランスよく表現することがポイントです。
👇 関連情報をチェック
📖 書類作成のヒント 書類&実績編|海外進学Q&A
面接の形式や重視される点はどう違う?
国内の推薦入試では、形式的な質問や志望理由確認が中心で、短時間でのやりとりが多いです。
一方、海外の面接(インタビュー)は、応募書類に基づいた深掘りが行われ、考え方や将来の展望、価値観まで問われる“対話型”が主流です。



正解のある受け答えよりも、自分の言葉で語る姿勢や「なぜそう思ったのか」の説明力が評価されます
両方準備するのって負担が大きくない?
確かに負担はありますが、効率よく重なる部分を整理すれば対応可能です。たとえば、課外活動の棚卸しや自己分析、エッセイの構成要素は国内外で共通しています。
重要なのは、早めにカレンダーを作って締切を把握し、優先順位をつけて準備すること。



時間的にも精神的にも余裕を持つために、ラボのような外部サポートを活用するのも効果的です
👇 関連情報をチェック
💡 個別相談で効率化 海外進学ラボTOP|個別相談・セミナー情報
併願している人はどのくらいいる?
海外進学希望者のなかでも、約6〜7割程度は国内との併願をしている印象です。
とくに総合型選抜(旧AO入試)や帰国生入試など、柔軟な選抜方式のある大学と併願するケースが多いです。
「国内にも滑り止めがあると安心」という気持ちは自然ですし、実際、活動の整理や英語力の証明など共通する準備項目も多いため、戦略的な併願は進路の選択肢を広げる有効な手段となります。
保護者としてどちらを優先させるべき?
“子どもがもっとも納得して前に進める方”を軸に選ぶのが理想です。
保護者は、経済的な視点や社会的な安心感から国内を勧めたくなる場面も多いですが、本人が自信と希望を持って進める選択こそ、長い目で見て力になります。



国内外の情報を偏らずに集め、一緒に比較・対話をしながら“うちの進路”を組み立てていくプロセスがとても大切です
国内の“指定校推薦”と海外進学、どちらがリスクが少ない?
指定校推薦は合格率が非常に高く、日本国内では安定した進学ルートとして認識されています。
一方で、海外進学は語学力や書類の完成度、奨学金の有無などに左右されるため、リスクはやや高めです。
ただし、キャリアの幅や学びの自由度は海外が上回る場合も多く、どちらを“リスク”と考えるかは価値観によります。保護者・本人での話し合いが大切です。
国内大学に落ちたとき、海外出願しておくと安心?
安心感はあります。国内推薦入試や総合型選抜で不合格になった場合でも、海外出願が進んでいれば、進学の選択肢が残ります。
とくに海外大学は出願締切が1月〜3月のところもあり、国内の結果を見てから出願できるケースもあります。
ただし、急な出願には書類や英語スコアの準備が必要なため、余裕をもって事前に準備しておくことが重要です。
国内志望のまま海外出願だけ追加するのはアリ?
十分アリです。国内の志望が固まっていても、「選択肢として海外も見ておきたい」「奨学金があれば挑戦したい」という理由で海外出願を追加するケースは増えています。
とくに英語力や課外活動がある程度整っているなら、無理のない範囲で準備が可能です。



視野を広げることで、進路に対する納得感が増し、国内出願へのモチベーション向上にもつながります
国内併願の候補はどう選ぶべき?
併願先を選ぶ際は、「自分の興味関心に合っていること」「出願時期が海外と重なりすぎないこと」「英語力や活動実績が活かせること」を基準にしましょう。
たとえば国際教養系・SDGs系の学部は、海外出願準備と親和性が高く、エッセイや英語資格も活かしやすいです。
また、出願条件が柔軟な大学を複数確保しておくと、心の余裕にもつながります。
学校の進路指導の先生にどう伝えればいい?
最初に「国内進学と並行して、海外大学も検討しています」と率直に伝えるのがベストです。
そのうえで、「どのタイミングで相談に乗ってもらえるか」「どの先生が詳しいか」も聞いておくと安心です。
学校によっては海外進学に詳しい教員が限られていたり、書類サポートの方針が異なるため、早めの共有と連携が重要です。
海外進学の検討は、国内進学にマイナスになる?
いいえ、基本的にはなりません。むしろ、海外進学の検討を通じて「学びたいこと」や「将来の方向性」が明確になれば、国内進学にも好影響があります。
ただし、学校側がサポートしづらくなることがないよう、早めに方針を共有し、推薦書や書類準備のスケジュールを丁寧に管理することが大切です。
海外留学の経験は日本の大学に有利になる?
A: 短期留学や海外プログラムへの参加経験は、国内の推薦入試や自己推薦で“多様な経験”として評価されることがあります。
とくに英語での発表経験や、国際的な視点を持った探究活動は強みになります。
ただし「海外に行った」という事実よりも、「何を学び、どう考えたか」をしっかり言語化できるかが評価の分かれ目です。単なる経歴でなく、内面の成長と結びつけて伝えることが大切です。
👇 関連情報をチェック
🔗 課外活動の選び方 進路をひらく課外活動ナビ
📖 体験レポートを読む 中高生チャレンジレポート|日本・海外の中高生による挑戦・体験レポート
🎓 留学プログラムを探す 小学生から大学生まで、世界中の留学プログラムを安心サポート
併願を続けたままどこかで切り替える判断軸は?
よくある判断軸は「奨学金の有無」「進学後のキャリアとの相性」「本人の意志の強さ」です。
たとえば、第一志望の海外校に合格しても、奨学金が取れず断念するケースもあります。逆に、国内校より明確な学びの魅力を感じて海外に進む人もいます。
切り替えのタイミングは高3秋〜冬が多く、“どちらになっても納得できる材料”を集めておくと迷いにくくなります。
最終的に併願をやめて1本に絞るとしたら、いつ?
多くの家庭では、高3の秋〜冬、つまり海外出願や国内推薦の直前が決断のタイミングになります。
この時期に志望度・準備状況・経済面などを総合的に判断し、一本に絞るかどうかを考えるケースが多いです。
最初から完璧に決めきる必要はありませんが、「どの時点で決断するか」を家族で共有しておくと、迷いなく進めます。
👇 関連情報をチェック
💡 決断をサポート 海外進学ラボTOP|個別相談・セミナー情報
海外進学に関するイベント・資料・Q&A更新情報をLINEでお届けします。



受験準備のヒントや、保護者向けの特典情報もいち早くお届けします