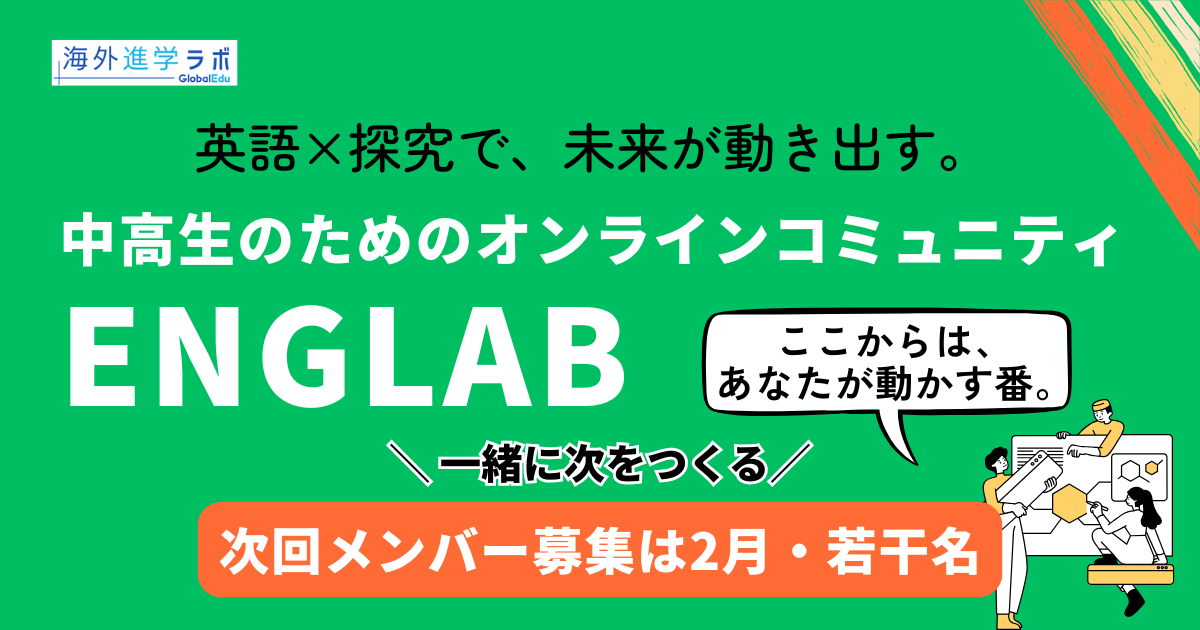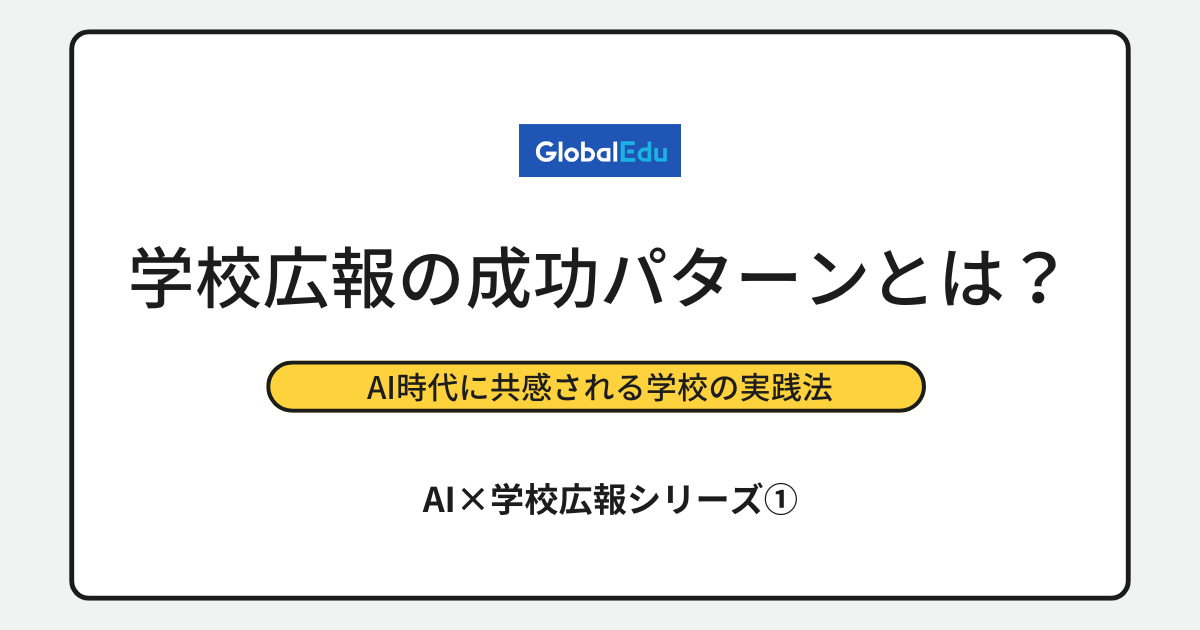教育現場の発信は、いま転換期を迎えています。
AIが記事を作れる時代に、「どんな学校が共感されるのか?」。
その答えは、「何を伝えるか」ではなく、「どう関係を築くか」にあります。
ここでは、AI時代に成果を出している学校広報の共通点を、国内外の事例や取材をもとに整理しました。
広報は「採用」でも「募集」でもない、“関係構築”の場
これまでの学校広報は「情報提供」中心。
でも、AIが情報を整理できる今、学校の価値は“関係のつくり方”で決まります。
- 数字ではなく、理念を語っている
- 一方的ではなく、対話を生んでいる
- 発信が“共育”の延長になっている
共感される学校は、広報を“教育の一部”として設計しています。
成功する学校広報の3つの型
| パターン | 特徴 | 成果の出やすい場面 |
|---|---|---|
| ① ストーリー共感型 | 学校の理念や生徒の成長を物語として発信 | 入学希望者・保護者層への信頼構築 |
| ② 学び共創型 | 教職員・生徒・保護者が発信を共に作る | 校内文化形成・職員間の一体感 |
| ③ 社会接続型 | 地域・企業・大学と連携し、社会に開く | 地域との共創・広報の拡散力向上 |
多くの学校は①で止まっていますが、②③の段階に進むと“自走する広報文化”が育っていきます。
事例から見る「AI時代の成功パターン」
事例①:理念を「翻訳」したブランディング(東京都内 私立校)
校内研修でChatGPTを使い、教育理念を“生徒が語れる言葉”に翻訳。
その言葉をSNS・パンフレットで発信したところ、保護者の口コミが急増し、体験会参加数が前年比1.8倍に。
💬 「理念が、誰にでも伝わる言葉になった」という職員の声が象徴的。
事例②:生徒×教職員の共創広報(関西エリア 公立高校)
探究活動をAIで要約 → 生徒が広報文を修正 → 教員が理念に沿って監修。
この流れを定着させたことで、学校全体に「発信=学びを共有するもの」という意識が根づいた。
📈 学校公式Instagramのフォロワー数は半年で3倍に。
事例③:地域と連携する発信(北海道の私立中高一貫校)
地域企業との共同イベントをAIが要約し、地域メディアと共同編集して発信。
AIの活用が「地域の学びのハブ」として注目され、教育委員会主催のフォーラム登壇へ発展。
成功する学校に共通する「3つの原則」
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| ① 発信を“目的”にしない | 広報は教育・理念・学びの延長線上に置く |
| ② AIに“任せる”より“共に考える” | AIは効率化ではなく、対話を深めるために使う |
| ③ 小さく始めて文化にする | SNS一投稿・校内ミーティングから始める |
広報を“行事報告”から“文化の共有”へ。
この転換が、AI時代の成功の分岐点です。
これからの広報は「運用」ではなく「編集」
AIがテキストを生成できるようになった今、本当に問われるのは「編集する力」。
- AIが出した文案を、学校の理念に沿って整える
- 取材の中から“物語の核”を見つける
- 発信後の反応をもとに、次の問いを立てる
広報担当者は、もはや“発信係”ではなく、学校の哲学を社会とつなぐ編集者なのです。
Globaleduの提案 — 広報を「共育デザイン」へ
Globaleduでは、AI時代の学校広報を支援するための「共育ブランディング」プログラムを提供しています。
提供メニュー
- 学校理念・ミッションの再言語化セッション
- 広報・ブランディング戦略設計
- ChatGPT活用支援(研修・テンプレート提供)
- 教職員×生徒の共創発信プロジェクト
- 取材・記事制作・外部広報の代行
AIが文章を作り、人が“意味”を作る
AIが進化するほど、人間の“意図”と“物語”の価値が高まります。
学校広報のゴールは、数字でも流行でもなく、「理念が生きて伝わること」。
そして、その理念を社会と共に育てていく力こそ、AI時代の“共感される学校”の条件です。
🔗 関連リンク
- ChatGPTで変わる学校広報|AIを“効率化”ではなく“共育化”する使い方
- 学校ブランディングの新常識|理念を「物語」で伝える方法
- 教職員に必要なAIリテラシーとは?学びと発信を支える新しいスキルセット
教育機関の方へ|AI×教育の次のステップへ
グローバルエデュでは、AI時代の学校広報・教育ブランディング・リテラシー研修など、教育現場を支援する「共創プログラム」を展開しています。