「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今週は、ビザや入試制度といった「制度系の揺らぎ」と、それにどう向き合うかを考えさせられる5本をピックアップ。
米国のF-1ビザ発給数が大きく落ち込み、中国とインドにおける動向に注目です。加えて、オーストラリアの高騰ビザ費や、不正受験が発覚したTOEIC事件など、「試される制度」と「選ぶ側の視点」が交差する内容が多め。
学校現場ではスマホが学習に与える影響に対する教師と生徒の意識差、移民政策が教育現場に与える影響も浮き彫りに。
米国の学生ビザ発行数の落ち込み、中国とインドが減少数の60%を占める
PIEニュースが入手したデータによると、2025年5月時点で米国のF-1(学生)ビザ発行数は前年比で22%近く減少し、中国とインドがその減少分の60%を占めることがわかりました。
とくにインドは、米国への留学生最大供給国としてのシェアは維持したものの、前年比44%減という大幅なビザ発行数の落ち込みを記録しています。そうしたなか、インドの米国大使館は今夏の新規面接枠を保証できない見通しを発表。申請者の身元調査やソーシャルメディア活動の審査が強化された状況もあり、米国留学に慎重なインド人学生も増えつつあるようです。
一方、インドに次ぐ留学生供給国の中国も、米国に対してこれまで以上に様子見の姿勢を強めており、ここ数年は英国留学を優先して選ぶ傾向が生じています。
 副編集長 城
副編集長 城アジアも含めて最近は海外留学の選択肢が充実しています。一ヵ国にこだわらず、複数の国や地域に出願するスタンスが定着していくのではないでしょうか
出典リンク
- THE PIE | China, India account for 60% of all year-on-year F-1 visa declines
- ApplyBoard(ApplyInsights)| US Student Visa Issuances Grew More Diverse in the First Half of the 2025 Fiscal Year
値上げ続く豪学生ビザ申請料、減額に向けた動きが水面下で進行中
International Education Association of Australia(IEAA)のCEOであるPhil Honeywood氏は、直近で2000豪ドルまで値上がりしたオーストラリアの学生ビザ申請料は、精力的なロビー活動のおかげで減額を実現できるだろうと期待感を表明しています。
豪の学生ビザ申請料は、約1年前の710豪ドルから1600豪ドルという大幅な値上がりに続き、2025年7月にはさらに2000豪ドルまで引き上げられ、留学生には厳しい改定が相次いでいました。
そうしたなか、世界的にも高額なビザ申請料が減額される可能性が浮上していますが、減額が確定しても正式適用されるのは最短で2026年1月1日以降になる見通し。
実際、豪州では2024年のビザ申請料値上げを主要因として、名のある語学学校が次々に閉校に追い込まれており、留学生はもちろんのこと、学生を受け入れる側にとっても深刻な影響が広がっています。



ビザ申請料の減額は、豪留学に関わる全方面の個人や団体にとって待望の動きといえそうですね
出典リンク
- THE PIE | Australia’s education leaders push for lower student visa fees for short-term students
- THE PIE | IRU and RUN set out new vision for Australia’s international education system
- THE PIE | Perth International College of English closes due to visa fee hikes
米国政府の移民捜査に連動して生徒の出席率が低下している実態が明らかに
欠席問題の専門家でもあるスタンフォード大学教授Thomas Dee氏の調査報告によると、移民強制捜査を公約に掲げた第二次トランプ政権が発足した時期(2025年1月)に合わせて、カリフォルニア州学校における生徒の欠席日数が22%も急増していたことが明らかになりました。
とくに欠席日数の増加が目立ったのは、幼稚園年代~小学5年生の比較的低年齢の生徒たちです。これは、年齢の若い子どもをもつ親の方が、トランプ政権下の移民政策方針に不安感を抱き、子どもを学校に通わせることを躊躇していた状況が読み取れます。
さらに、Dee氏が調査対象としたエリアには農業従事者が多いことから、不法移民取り締まり強化に対してリスク回避=欠席を選択する家庭が高比率を占めた可能性もあります。



米国では農業労働者の61%を移民が担っており、4割以上が法的な滞在資格を有していないと見られています
出典リンク
- Economic Research Service(ERS、米国農務省(USDA)傘下の調査機関)| Legal status of hired crop farmworkers, fiscal 1991–2022
- EdSurge | Immigration Raids Are Preventing Students From Attending School
- EdWorkingPapers | Recent Immigration Raids Increased Student Absences(PDF)
米国STEM教師はスマホこそ学習の障害と問題視、生徒側の認識と大きなギャップ
Edweek Research Centerが中学校と高校の教師および10代生徒を対象に実施した調査によると、約80%の教師が、ゲームやSNS等のスマホによるオンラインアクティビティを「STEM学習の大きな阻害要因」と認識していることがわかりました。
また、「スマホに費やす時間がSTEM授業にどう影響するか?」という問いに対しては、94%の教師が「ある程度は悪影響」もしくは「非常に悪影響」という回答を選択しました。
一方、生徒にも同様の質問が用意されましたが、約半数がスマホ使用はSTEM授業には「影響なし」と認識しており、「影響なし」回答がわずか4%の教師側の認識とは明確なギャップが浮き彫りに。
また、一部の生徒がスマホ依存は学習の妨げと自覚するものの、ほぼ同率で「学習内容に無関心」、「成績低下への不安」、「教師のフォロー不足」などの回答が寄せられ、生徒の考える学習阻害要因は人それぞれ一様ではない実態が示されました。



今から30~40年前に日本で同じ調査を行えば、スマホの位置がそのままテレビゲームに置き換わっていたかもしれません
出典リンク
- Education Week | Students Don’t Think Cellphones Distract Them From Learning STEM. Teachers Disagree
- EdWeek Research Center | Student Motivation and Learning(最終報告版)
日本でのTOEIC組織的不正受験発覚、他の紙ベース試験セキュリティに対する疑念も
2025年5月、不審な受験者の特定をきっかけに、過去2年間で803名もの関与者が発覚した日本国内のTOEIC不正受験事件。これは、いまだに紙ベースの対面試験を継続しているグローバルな英語試験業界にも大きな波紋を呼んでいます。
同事件では、捜査が進む過程で、ペンダント型中継器や耳の奥まで入る小粒イヤホン、さらに使用法を指南する動画までも押収され、非常に巧妙な仕掛けによって組織的不正が行われていた実態が見えてきました。
もっとも、自宅受験のオンラインテストなど新方式のセキュリティには、これまでも厳しい視線が向けられる傾向にあったようです。ただ、今回はむしろ「慣れ親しんだ」紙ベース試験で深刻な不正が発覚し、大きなニュースにはなっていないものの、2025年に入りベトナムやウズベキスタンなど紙ベースIETLS試験が廃止されるケースも出てきています。



不正行為の質が変化しているため、従来は安全だった試験方式が今後も通用するとは限らないかもしれません
編集メモ
出典リンク
- THE PIE | Mass TOEIC cheating uncovered in Japan
- 時事通信 | 米粒大のイヤホン使用か 指南動画も、TOEIC不正―警視庁
- TOEFL® Resources by Michael Goodine | IELTS to go Computer‑Only in Vietnam
- TOEFL® Resources by Michael Goodine | Paper IELTS Shuts Down in Uzbekistan
次回予告:
「人の悩みをAIに打ち明ける。」一見、現実味の薄い表現に思えるかもしれませんが、海外では生徒の相談先としてAIチャットが成果を示しつつあるようです。
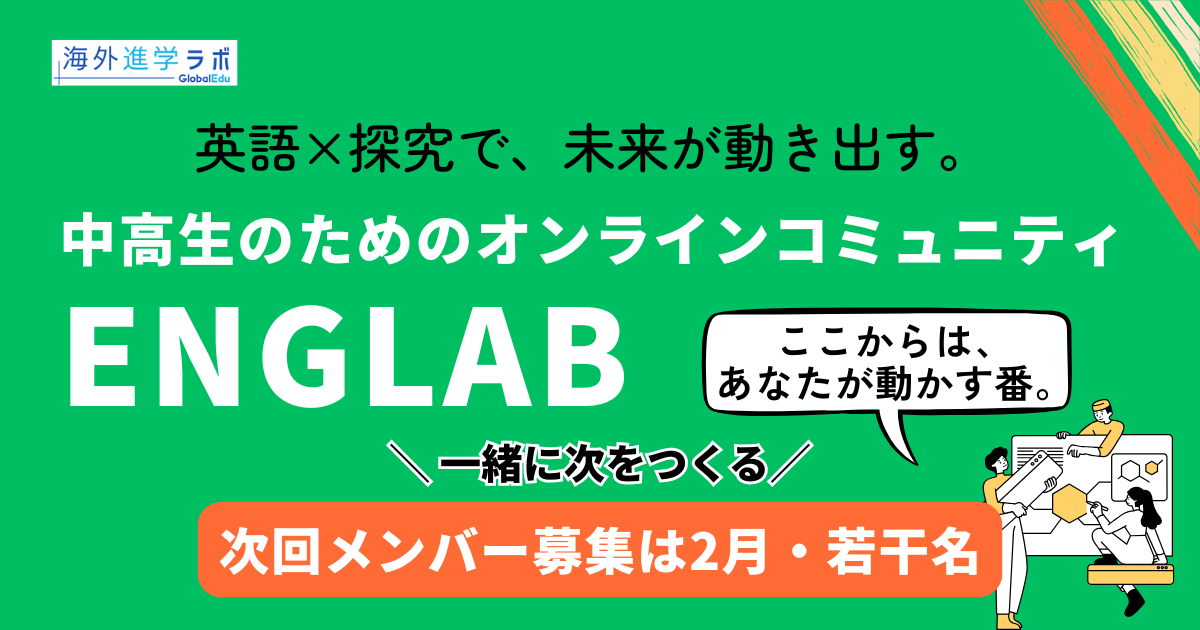


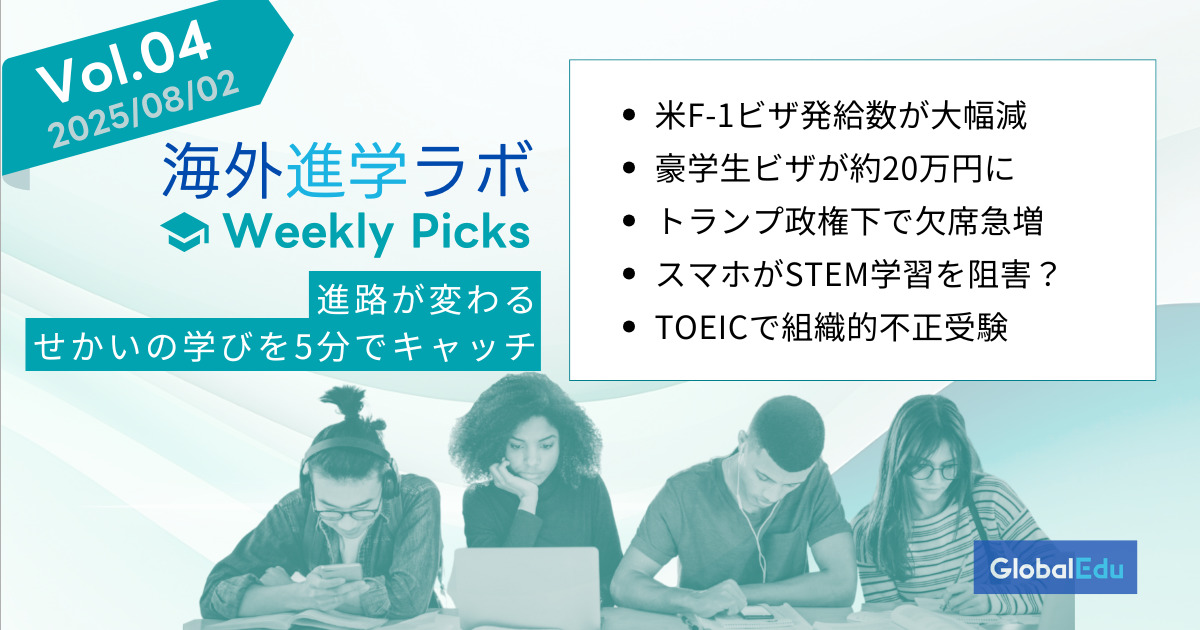






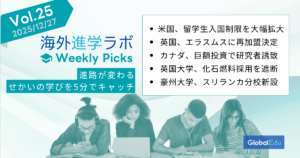
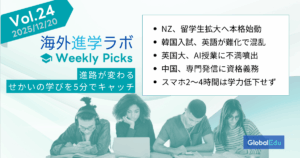
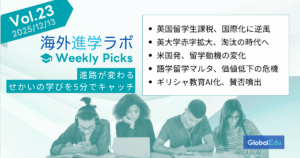
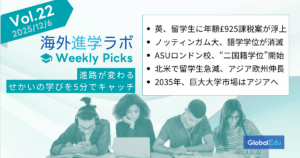



進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります