「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今号では、「留学先の選び方」に関わる外的要因が複数浮かび上がった一週間でした。経済成長の鈍化によって中国人学生の進学先に変化が見られる一方、カナダでは留学生の財政要件が引き上げに。コスト・制度・地域性といった複数の要素が、進路選択にますます影響を与える状況となっています。
また、AIツールをめぐる教育現場の対応も注目の的に。IBや英国大学の動きからは、禁止か容認かの二元論ではなく、活用の“設計”が問われる時代へと進んでいることが見えてきます。DuolingoによるAI対話型スピーキング試験の導入も、まさにその象徴と言えそうです。
留学先の「選び方」と「学び方」が大きく変わる節目かもしれません。
経済成長鈍化を背景に、中国人学生の留学先選択傾向に変化?
これまで世界中の大学へ多数の留学生を送り出していた中国ですが、留学主要国ビッグ4(米・英・豪・カナダ)に限れば中国人留学生の増加にかげりが見えつつあるようです。
とくに留学生離れが目立つのが米国で、国際教育分野の調査会社BONARDによると、中国人留学生は5年前と比べて約8万人もの減少を記録。ただし、英国のみ2020年以降、中国人留学生数は緩やかに増加し続けており、ビッグ4内では優先度が高まりつつある傾向が読み取れます。
こうした事象について、BONARDのシニアコンサルタントSu氏は、「中国では中流階級の経済成長鈍化により、留学国選びにおいてもコスト優先の意識が高まっている」と分析。代わりに、シンガポールや香港など、ビッグ4より近場・低コストながら国際的に高評価な学位を得られる進学先にシフトする傾向にあるようです。
 副編集長 城
副編集長 城留学生受け入れに積極的なアジア圏と異なり、ビッグ4が総じて在留資格チェックを強化している点も留学先選びに少なからず影響はあるでしょう
出典リンク
- THE PIE | Are Chinese students losing interest in the ‘big four’?
- THE PIE | “Asian tigers” ramp up internationalisation amid big four woes
カナダ、留学生の就学許可証に対する財政要件を2025年9月より引き上げ
カナダ政府は、留学生の就学許可申請に伴う財政要件を現状の20,635カナダドルから、2025年9月1日以降は22,895カナダドルに引き上げることを決定しています。
この変更は、カナダ国内の中長期的なインフレに対応するための段階的施策の一部で、独自制度を運用するケベック州を除いた、カナダの全ての州および準州を対象に適用されるものです。また、留学に際して、1名以上の家族が同伴してカナダ国内に滞在する場合は、留学生家族の人数に応じて証明すべき生活資金額は引き上げられます。
カナダ以外の主要留学国(ビッグ4)の近況に目を移すと、英国とオーストラリアは学生ビザ申請手数料の値上げ、米国では新たなビザ関連費用が追加されるなど、留学生にとって経済的負担の上乗せとなる変更が目立っています。



学費、生活費、事務手数料等の連鎖的な上昇を背景に、今後もビッグ4以外への留学ニーズが高まることが予想されます
出典リンク
- THE PIE | Canada increases financial requirement for students
- Government of Canada | Study permit: Get the right documents
- NAFSA | Budget Law Imposes New Immigration Fees
進歩が著しいAI生成ツールに対するIB評価ディレクターの見解は?
IB(国際バカロレア)評価ディレクターMatt Glanville氏は、AI技術が私たち生活の一部になる未来を想定したうえで、AIツールを全面禁止することなく、IB学習のルール内で生徒が倫理的且つ効果的に使用できるよう推進する方針を示しています。
例えば、IB教育を象徴するエッセイ作成においては、全てまたはその一部がAIツールによって生成された場合は生徒自身の執筆作品とは認められません。ただし、エッセイ内の資料や引用としてAI生成物を使用する際は、必ず本文中にクレジットを表記し、出版物等のケースと同じように参考文献として適切に明示することを求めています。
Glanville氏は、AIツールから派生する問題は、エッセイ代筆による不正行為のように「昔からの問題」と本質は変わらないと認識しており、生徒自身の作品か確認するための着眼点を学校教師と共有したうえで継続的に対処していく旨を明らかにしています。



ルールを守って効果的にAIツールを活用すれば、エッセイ作品の質を高めることにつながりそうですね
- IBO | Artificial intelligence in IB assessment and education: a crisis or an opportunity?
- IBO | Artificial intelligence (AI) in learning, teaching, and assessment
Duolingo、2025年7月よりAI技術を活かした相互型スピーキングテスト導入
Duolingo English Testは、2025年7月1日以降の試験を対象に、AI技術を活用したインタラクティブスピーキングテストを新たに導入しています。
これまでのスピーキングテストは、人間同士の対面タイプか台本に縛られた自動音声タイプかの二択に限られ、それは同時に一貫性もしくは柔軟性のいずれかが犠牲になるトレードオフ問題を浮き彫りにしてきました。
しかし、Duolingoが新開発したスピーキングテストでは、生成AI機能を備えた仮想キャラクターとの間で、現実に即した相互コミュニケーションを実現可能にしています。試験中は、6~8回の質疑応答があり、受験者の回答内容に応じてAIは最適なフォローアップ質問を選択するほか、回答の正確性や流暢さを安定して評価できる性能を保持しているようです。なお、試験時間との兼ね合いで、従来のRead Aloud(声出して読む)形式の問題は削除されました。



面接官より、対AIの方がリラックスして試験に臨める受験生も多いのではないでしょうか
英大学生のAI使用による不正行為1年で7000件発覚、逆に盗作は減少傾向
ガーディアン紙の調査によると、英国大学生のAIツールを使用した不正行為は年間約7000件に達しており、専門家はそうした調査結果を依然として氷山の一角と捉えています。
実際、調査対象の大学の中には、AI関連の不正を独立して記録していないケースもあり、不正検知への取り組み姿勢には大学ごとにバラつきが見られる状況です。
また、興味深いのは、AIが絡む不正行為が確認された2022~2023年度の調査以降、盗作による不正行為はAIの普及と相反して減少し続けていること。同調査に携わったPeter Scarfe心理学准教授は、例えAI使用禁止を要求しても、学生は検知をすり抜けてAIツールを使用しうる一面を教育業界は認識しておく必要があると述べています。



現役学生からは、AIツールは学習や研究のアドバイザーとして大いに役立つという声も上がっています。そのメリットを活かし、リスクを軽減するための活発な議論が期待されますね
- The Guardian | Revealed: Thousands of UK university students caught cheating using AI
- The Guardian | Researchers fool university markers with AI-generated exam papers
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
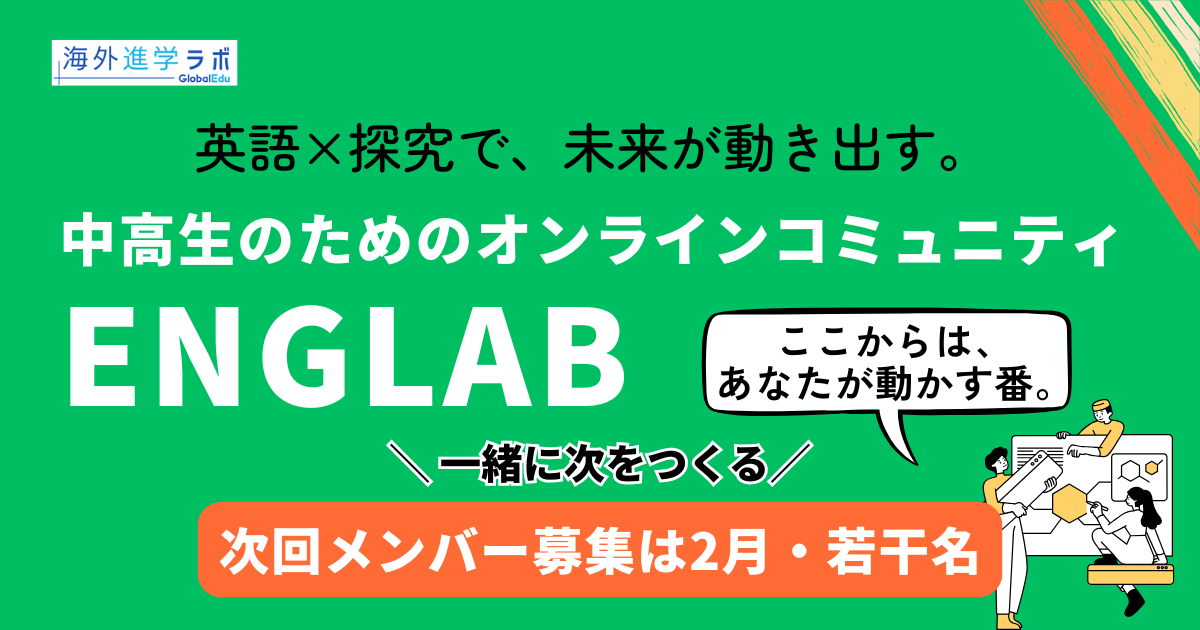


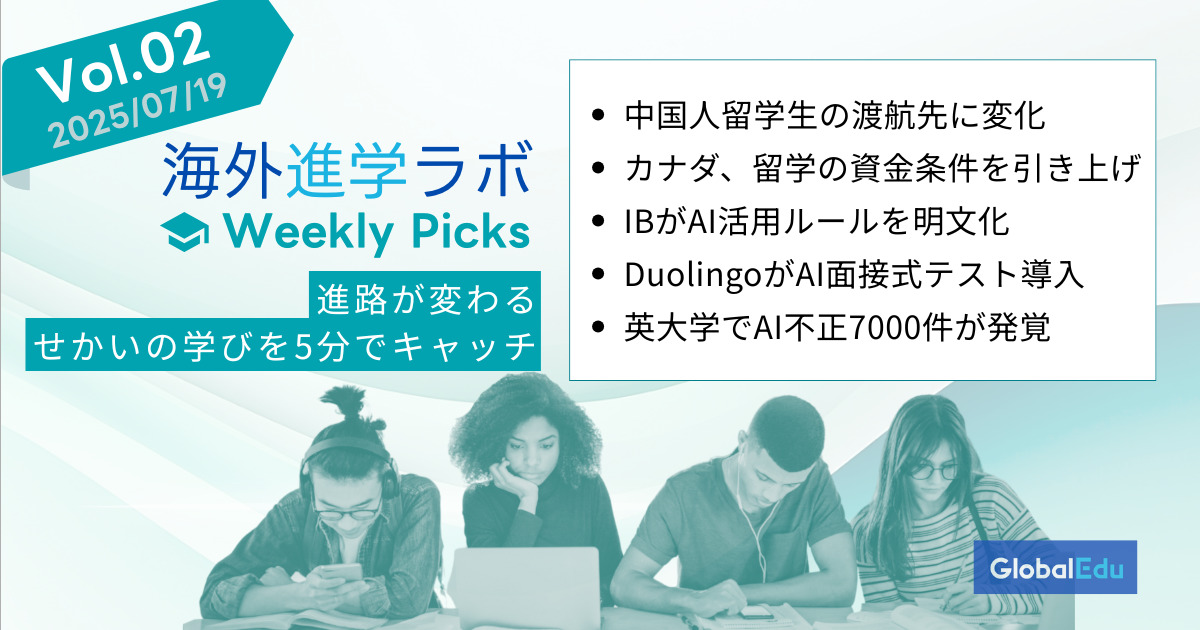







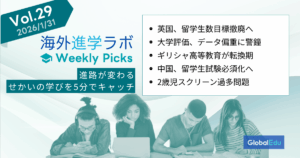
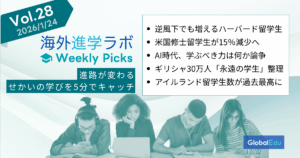
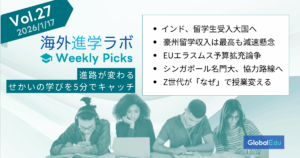
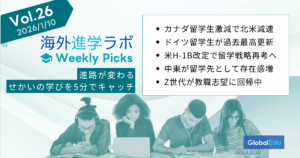

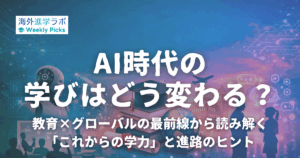
進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります