「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今号では、進路や学びの選択に影響を与える“見えにくい力”に注目。
親の期待や性別バイアスが子どもの進路選択に影響を及ぼすという日本の研究、短期ジュニア留学が注目されるアイルランド、ビザ政策が語学留学に影を落とすカナダ、大学の「不要学位」削減を進めるアメリカの動き、そしてポッドキャストを通じた家庭内学びの可能性まで──。
進路選びは本人の意志だけでなく、制度・環境・文化的価値観によっても形づくられるという視点から、今週の5本をお届けします。
早稲田大研究:「親の期待」が女子の進路選択に影響
早稲田大学政治経済学術院の尾野嘉邦教授ら研究グループの調査によると、親の期待や無意識バイアスにより、子どもの進路選択が左右される可能性が実証的に示されました。
架空の高校生プロフィールを提示し、親として「受験を勧めるか否か」を3000人の成人男女に評価してもらった調査実験では、難関大学受験については子どもの性別による評価差は少ないものの、男子向けのイメージが強い理工系学部には女子の受験を勧めない傾向が確認されたようです。
さらに、「男子の大学進学に高い便益を期待する」または「古き性的役割意識が強い」回答者ほど、女子に難関大学受験を勧めない傾向も明らかに。
このように、女子が難関大学や理工学部への進学を避ける要因は、親の性に関わるバイアスを背景とした大学へのイメージや期待利益にある可能性が示唆されました。
 副編集長 城
副編集長 城もちろん子どもには自由意志があり、親の意識がストレートに進路選択に反映されることはありませんが、中長期的に子どもの価値観形成に影響する可能性は高そうです
出典リンク
- 早稲田大学 | 女子の進学選択に影響する「親の期待」― ジェンダー観が高等教育への進路を左右 ―
- 国際学術誌「Research in Higher Education」Gendered Expectations for College Applications: Experimental Evidence from a Gender Inegalitarian Education Context
アイルランドの留学生受け入れ数が2024年に過去最高を記録、ジュニア世代のミニステイも留学人気を支える
アイルランドの英語教育部門(English Education Ireland)は、2024年に125ヵ国から128,000人以上の留学生がアイルランドを訪れ、その人数は過去最高水準に達したと発表しました。
本調査によると、2024年のアイルランドの留学生受け入れ数はコロナ禍前の109%の水準を記録し、授業料、宿泊費、その他の直接的支出のみを合算しても国内に7億9200万ユーロの経済効果をもたらしたそうです。
もともとアイルランドは成人留学生の中長期留学先として堅調な需要を維持してきましたが、最新調査ではミニステイと呼ばれるジュニア向け短期プログラムの人気上昇が浮き彫りになりました。
海外留学にネガティブな要因が山積するなか、短期滞在の英語没入体験に対する強いニーズが示されたことで、関係者はこうしたジュニア留学市場の継続的な成長に期待を寄せています。



アイルランドは世界的に人気の留学先ですが、日本人内の知名度はあまり高くありません。欧州で語学留学先を探している場合は注目に値する選択肢でしょう
出典リンク
- THE PIE | Record number of students hosted by English Education Ireland in 2024
- English Education Ireland | Annual Report on English Language Training in Ireland 2024
カナダ政府の就学許可・移民政策厳格化の余波で、2024年語学コース学生数が急落
カナダの言語学校を統括するLanguage Canadaの調べによると、カナダの就学許可件数の制限やビザ処理遅延の影響もあり、2024年度の語学プログラム受講生は15%も減少したことが明らかになりました。
こうした事象に対し、同組織のGonzalo Peralta事務局長は、質の高い学生に対する高等教育へのパイプライン縮小を懸念するとともに、「地域コミュニティに力強さや包括性をもたらすはずの異文化相互学習の機会が失われてしまう」と悲観的な見解を述べています。
ただし、留学生数の国別トップシェアには日本がランクインし、韓国と台湾はそれぞれ10%弱増加を記録するなど、学生数の落ち込みが目立つ南米とは対照的に東アジアが留学生の主要供給地としてシェアを伸ばしたのは印象的です。



留学生には逆風と捉えられる政策変更も少なくありませんが、カナダへの日本人留学生の流れとしてはそこまで大きな変化は表面化していないようです
出典リンク
- THE PIE | Canada’s language sector takes hit as visa policies hinder growth
- Language Canada | New Report Highlights Economic Impact, Challenges, and Growth Opportunities in Canada’s Official Languages Education Sector
米国の一部州、大学に対して需要の低い学位の削減を要求する法案を可決
共和党が優勢な米国の3州は、一定の条件に則り、教育機関に対して卒業生が少ない学位を廃止するよう働きかける法律を可決しました。
インディアナ州のケースでは、同法律の施行とほぼ時期を同じくして、州が提供する学位の5分の1に相当する400の学位プログラムが自発的に廃止または統合される計画が明らかになりました。
こうした大学運営への州議会の積極的な関与には、「需要の有無だけで学術研究の価値が定められるべきではない」と教員や学術団体からは批判的な声が相次いでいるようです。
一方、今回の法律を推進する立場としては、「州の労働力ニーズを満たすために、希少な資源をより需要の高いプログラムに振り向けたい」という狙いがあり、ユタ州では「戦略的再投資」の要件に見合えば、削減された分の教育予算を取り戻せる仕組みも用意されています。



高等教育のあり方にどの程度ビジネス理論が適用されるべきか、これまで以上に包括的な視点が求められそうです
出典リンク
- Inside Higher ED | Legislatures Require Colleges to Cut Degrees in Low Demand
- Inside Higher ED | Indiana Public Universities to ‘Voluntarily’ End 19% of Degrees
ポッドキャストは子どものスクリーンタイム問題の解決に貢献する?良質な教育ツールとしての可能性
グローバル規模で教育環境改善に取り組むEDC(Education Development Center)の調査研究によると、子ども向けPodcastは世代間学習を促し、時間超過になりがちなスクリーンタイム抑制につながる可能性が示されました。
Podcastといえば、従来のラジオにオンデマンド機能が備わったような特性を有する音声メディア。今回の調査では、ポッドキャストが子どもの発想力や思考能力を拡張させるという有益な一面のほか、音声コンテンツを親子で共有し、家族間コミュニケーションが促されることで子どもの総合的な発育にも役立つ点が評価されています。
また、近年子ども向けポッドキャストの人気が急上昇した背景について、「スクリーンタイム超過によるリスクを抑えつつ、子どもに良質なメディアを消費してもらいたいという親のニーズに合致したのではないか」と情報メディアの専門家は分析しています。



どういったコンテンツを視聴中か共有・管理しやすい特性は、親側には大きな安心要素になりそうですね
出典リンク
- EdSurge | Could Podcasts Fix Screen Time Woes for Children?
- Education Development Center | How Can Podcasts Support Family Learning? Findings from a New Report
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
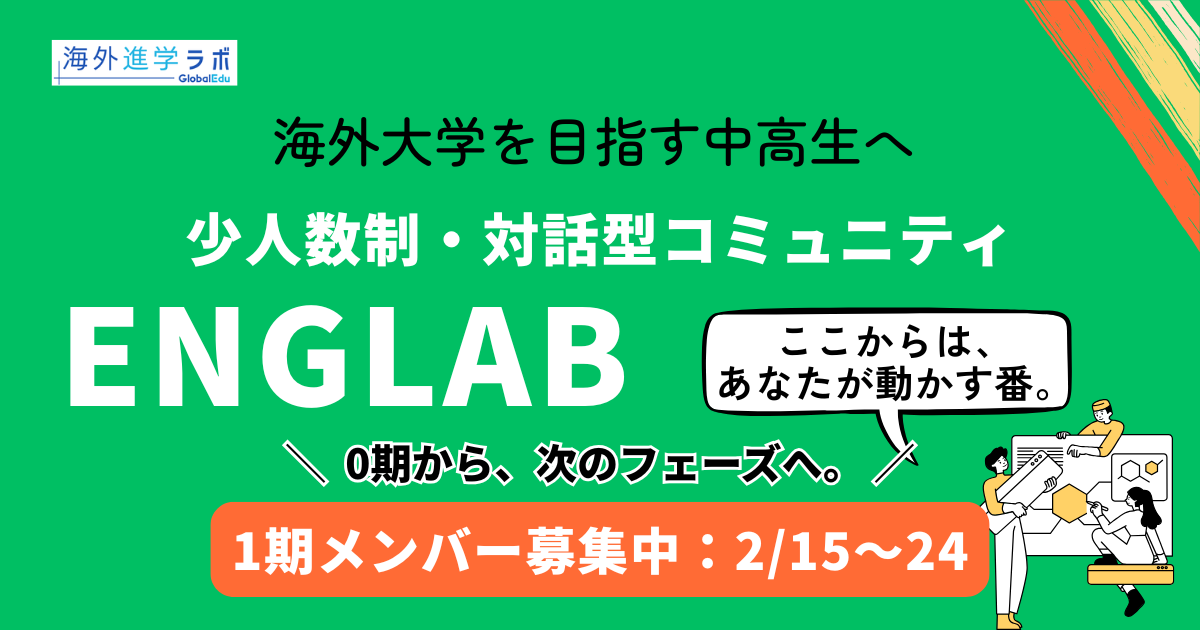






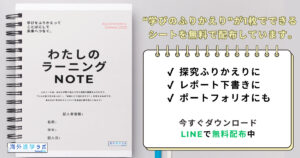

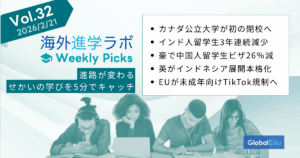
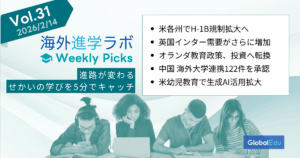


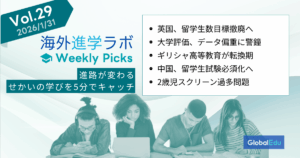
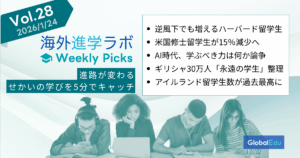
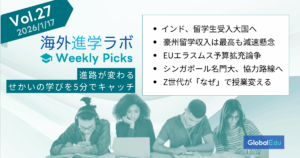
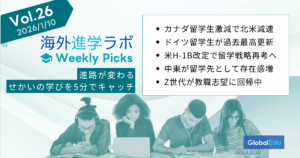
進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります