「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
世界の教育制度は、ビザ規制、予算削減、授業料制度、言語政策、そしてAI革命と、あらゆる側面で大きな転換期を迎えています。
今週は、米国で相次ぐ留学生政策の揺れ動き、北欧の学費制度が生む影響、オランダの国際教育縮小、そして生成AIによる試験制度の再考まで。
グローバル進学を目指す私たちにとって「選べる進路」と「必要な備え」がどう変化していくのか、5分で押さえていきましょう。
米国政府、F-1学生の長期滞在が不可となる新規則案を発表、延長手続き必須化へ
DHS(米国国土安全保障省)はビザ資格の乱用防止を目的として、学生(F-1)ビザ期限を4年間に厳格化する規則案を8月27日付けで発表しました。
これまでF-1学生は、「Duration of Status」として実質的に学生資格を維持する限りは米国滞在が認められてきました。本規則が正式適用されれば、4年を超えて滞在する場合は学生ビザの延長申請が義務化され、まさに、47年続いた制度の根本的変更が行われることになります。
NAFSA(Association of International Educators)CEOのFanta Aw氏は、「こうした変更は、学生を煩雑な行政手続きに釘付けにさせるばかりか、何ら悪意のない学生に懲罰的処置が及ぶリスクも伴う」と批判的見解を表明。また、新ルールにより、入学初年度の大学からの転校や修士生の専攻分野変更についても、従来にない制限が設けられる見通しです。
 副編集長 城
副編集長 城本規則案は30日間のパブリックコメント期間内にあり、正式採用される時期は明確ではありませんが、引き続き動向を注視していきましょう
出典リンク
- DHS(米国国土安全保障省) | Trump Administration Proposes New Rule to End Foreign Student Visa Abuse
- THE PIE | US proposes visa time limit rule to end “abuse” of system
米国務省、1億ドル相当の留学プログラム中止を通達、承認済み予算の撤回に抗議の声
2025年8月13日、米国務省の地方支局に対し、現在の財政状況において優先度が低いことを理由に、少なくとも22の国際交流プログラムを中止する意向がECA(Bureau of Educational and Cultural Affairs)より通知されたようです。
もしこの内部連絡通りに進展すると、総額1億ドル規模の予算が削減され、国際交流を待望する1万人の学生に影響が及ぶと見られています。
しかも、今回削減されるのは、議会で承認済みの補助金である点も大きな波紋を呼んでいます。中止プログラムにも携わるAlliance for International Exchangeの事務局長は、「行政管理予算局(OMB)が介入して予算撤回するのは違法ではないか」と疑問視。2つの国際交流団体が主導し、留学プログラム救済を求める1万通以上の書面が各州の議員宛に送達されています。



OMBはもともと競合予算を調整する役割を担いますが、本件は単なる調整を超えた権限行使のようにも印象付けられます
出典リンク
- THE PIE | US scraps $100m in study abroad programs
- THE PIE | Over 10k urge Congress to save US study abroad
- the White House OMB
フィンランド大学、留学生授業料有料化により入学者層や入学後の行動に変化
教育研究員Charles Mathies氏ら3名は、フィンランド政府の複数資料を用いて、2015年~2019年にかけて授業料有料化が留学生にどのような影響を及ぼしたかを調査。その結果、
2017年の学費導入後も出願数自体は変動しなかったものの、フィンランドの大学に入学する留学生数は減少し、その構成比率も比較的裕福な国からの留学生が増加したことが示されました。
また、有料化をきっかけに、経済的にあまり豊かではない国の留学生は初年度からより多くの単位取得に励むという行動的変化が見られたものの、裕福な国の留学生に限れば同様の行動パターンは確認されなかったそうです。
Mathes氏は、「学費が上がるにつれて、国際教育への参加権が裕福な国の人々に限定されていくだろう」として学費設定と教育機会の公平性の問題を指摘しています。



2023年にはノルウェーも留学生の授業料有料化に踏み切り、2025年現在日本人が北欧圏に留学する場合は学費が発生してしまいます
出典リンク
- The Times Higher Education | Students from lower-income countries ‘priced out’ by non-EU fees
- Research in Higher Education | If You Charge Them, Will They Come? The Effect of Levying Tuition Fees on International Students
オランダの英語学位縮小の動き、国際色豊かな高等教育の将来が不透明化
近年のオランダは、留学生数を抑制し、オランダ語による高等教育機会を拡大する法整備を進めており、全体の約30%を占めていた英語限定の学士課程は今後20%程度に縮小される見通しです。
こうした法整備は、2023年に発足したPVV(自由党)を含む右派連立政権の方針を強く反映しており、オランダの留学生数は2024年度に入って過去10年間で最低の伸び率(3%)にとどまりました。
留学生定員や英語コースの制限により、留学生の住居不足やコスト高の解消、卒業後のオランダ国内定住率の向上など社会・経済面への好影響も期待される一方、UNL(オランダ大学協会)は地域ごとの労働需要も踏まえて大学が国際化を自主管理しやすい枠組みの実現を求めています。さらに、わずか数年内のオランダ高等教育の方向転換を受けて、国際的な人材確保における長期的影響を不安視する声も上がっています。



蘭の少数政党が乱立する政治構造も影響し、大学の将来にも不透明性が高まっています
出典リンク
- QA UPDATES | オランダ:留学生数の抑制と英語による学士課程の削減
- ETIAS | Dutch Unis See Sharp Drop in New International Students
- オランダの国際教育振興機関「Nuffic」 | Inkomende diplomamobiliteit in het hbo en wo 2024-25
生成AI革命的進化への対応策、専門家は試験プロセスや評価方法の見直しを提言
英国の教育資格規制機関「Ofqual」のチーフ監視員であるIan Bauckham氏は、「学習理解度を問うために、学科試験よりもエッセイコースワークを優先するのは、昨今のAIリスクを踏まえると現実的ではない」と警告しました。
また、Surrey 大学 AI研究所のAndrew Regoyski 博士も「監視なしで生徒が執筆作業を行える状況は、根本的に疑問視せざるを得ないと」と同調するとともに、生成AIが日常に浸透するにつれ、「学生がテーマを分析し、執筆し、批評する能力を失う」というAI依存の兆候を懸念しています。
さらに同博士は、「エッセイに何を書くかではなく、執筆内容の理解度を問う試験、すなわち探求トピックについてのディスカッションを実施する」必要性に触れ、生成AIの存在を念頭に置いた評価方法の確立を求めています。



自筆エッセイテーマについての議論は、その理解度と関与度を同時に評価するには最適な方法ではないでしょうか
出典リンク
- The Guardian | A-levels and GCSEs need overhaul to keep pace with generative AI, experts say
- The Guardian | ‘It wasn’t an error’: Ofqual boss defends regulator after withdrawn data row
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
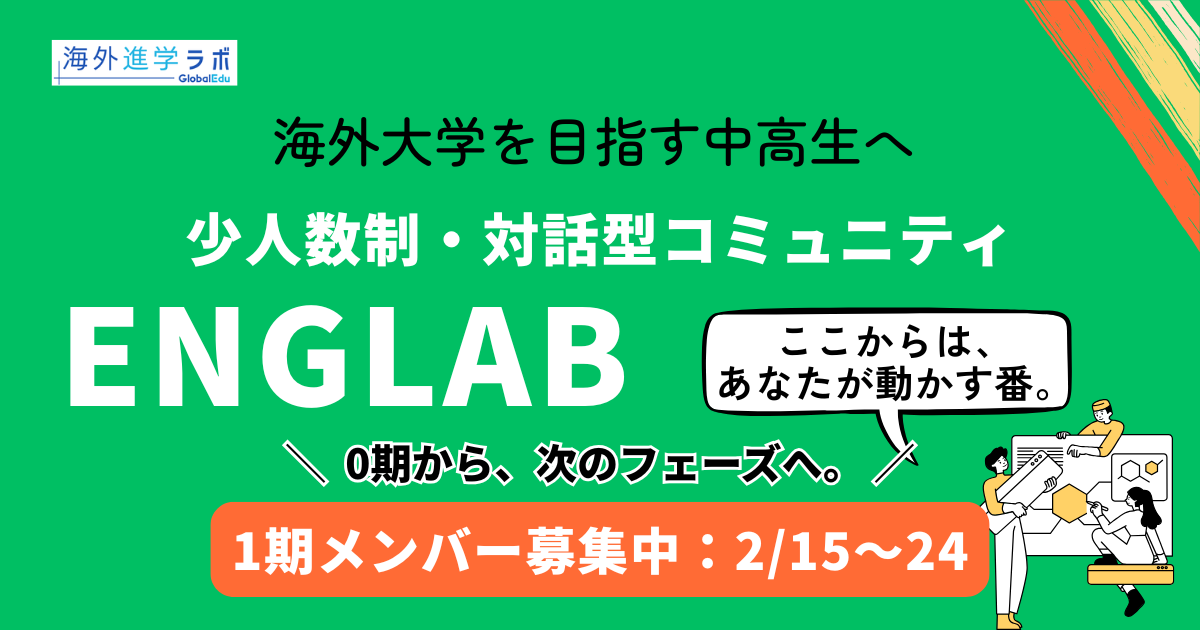


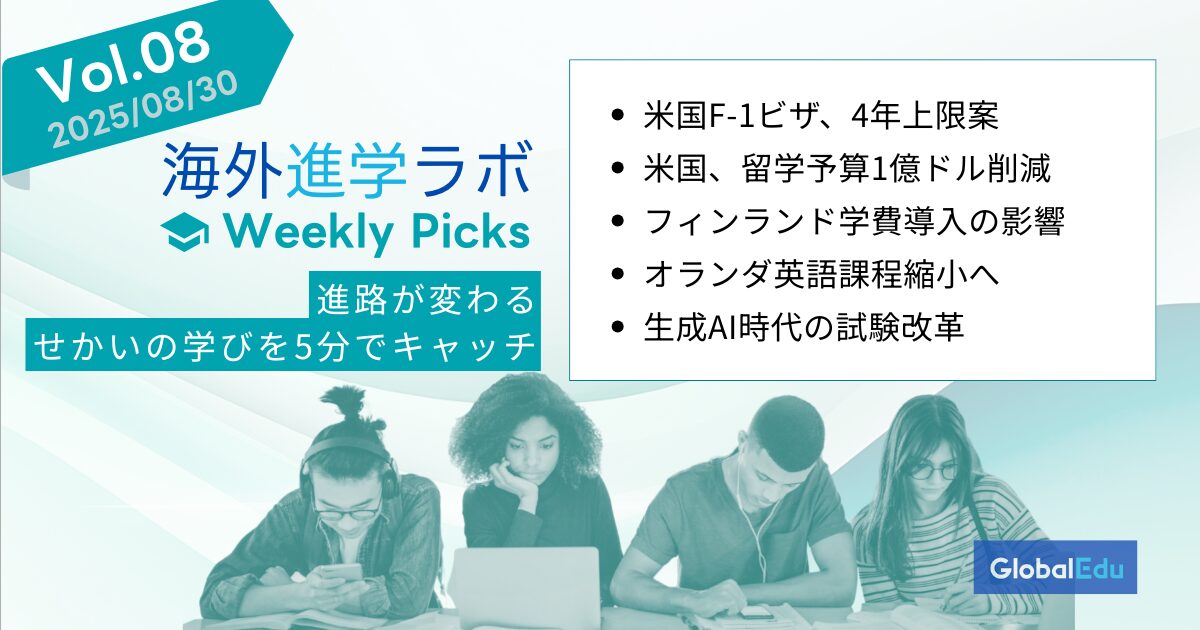


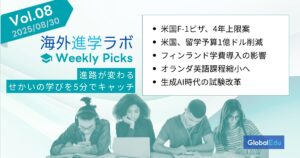


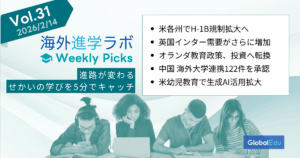


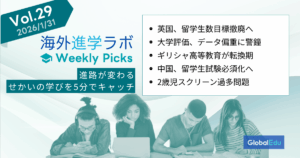
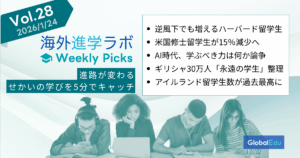
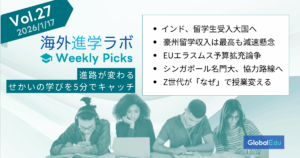
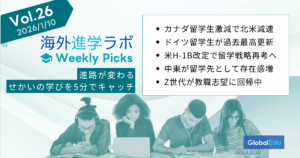

進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります