「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今週のPicksは、教育を取り巻く国際的な視線が色濃く映し出されました。
米国では国民の多くが留学生に肯定的である一方、ビザ制限をめぐり意見が割れる現状が浮き彫りに。オーストラリアでは、留学生の永住率や雇用の実態が従来の想定よりはるかに高いことが報告され、受け入れの制度設計が問われています。
英国では学生の3分の2がAIを学習に利用し、大学の対応力が課題に。さらに米国高校生の基礎学力低下が20年ぶりに深刻化し、学習環境の変化が議論を呼んでいます。そして日本ではDuolingo English Testが本格展開を開始。
各国の動きは、進路を考える上で「教育の国際化」と「変化する学びのリアル」をどう受け止めるか、私たちに問いかけています。
米国最新調査、アメリカ人は自国への留学生に肯定的、制限政策の可否は割れる
Pew Research Center(米国)が約9000人を対象に実施した最新調査によると、米国人の79%が「留学生はアメリカの高等教育に利益をもたらす」と認識しており、支持政党を問わず基本的にポジティブな留学生への見方が明らかになりました。
その一方、米政府が米国の外交政策を批判した学生のビザを取り消す行為については、肯定が42%を記録し、特に支持政党によって賛否が分かれる傾向が判明。また、国別に留学生数を制限すべきかの問いに対しては、対象国によって15%程度の賛否ギャップが確認されました。
こうした結果について、国際教育交流団体AIEAのCEOは「米国人の根本的な認識は一致しており、双方の考えをシェアし、誤解を払拭するため、生産的な議論を始めるべき段階にある」と評価しています。
 副編集長 城
副編集長 城近年は教育が政治論争に巻き込まれるケースも多いですが、留学生受け入れの支持率は4年前の調査とほとんど変わらないそうです
出典リンク
- THE PIE | Majority support for international students in the US
- Pew Research Center | Americans tend to view international students positively, though some support limitations
豪雇用問題の諮問機関、留学生在留率を過小評価と指摘、雇用実態も表面化
豪の雇用問題を扱う諮問機関「Jobs and Skills Australia(JSA)」が2025年8月にまとめた報告書によると、過去10年間に豪留学を始めた学生の最大40%が10年以内に永住権を取得している動向が明らかになりました。
これは過去に豪内務省が発表した、留学生の16%が最終的に永住権に移行する推定値とギャップが大きく、これまで留学生の在留率を低く見積もり、人材や社会に適合した雇用環境を実現できていなかった可能性が浮上。また、JSAの最新調査により、高等教育を経た留学生は英語力不足を主な理由として専門外や低賃金の仕事を担う傾向が強く、むしろ職業教育訓練(VET)を修了した方が待遇面では恵まれやすい実情も示されました。
同報告書は、留学生の雇用可能性を高めるため、大学教育において英語スキル向上や職業キャリアとの統合型学習をより中核的な要素に据える必要性を提言しています。



留学生のスキルや多様性を社会還元する仕組みの重要性を考えさせられる調査結果です
出典リンク
- The TImes Higher Education | Residency rates of overseas graduates ‘grossly underestimated’
- SHAPING A NATION(オーストラリア政府機関) | Population growth and immigration over time
- Jobs and Skills Australia(オーストラリア政府系組織)| International Students Outcomes and Pathways Study
英世論調査、学生の4分の1はAIツール使用の検出は不可能と認識
英国の大学生1027名を対象にYouGov(オンラインベースの市場調査会社)が実施した調査によると、回答者の約3分の2が学習用途で普段から生成AIを活用しており、AIユーザーの23%が成績評価対象となる提出課題に対して(全体または一部を問わず)生成AIの使用経験があることがわかりました。
また、生成AIによる100%創作物を提出した場合、大学に見つかる可能性が「非常に高い」と考える学生は約4分の1にとどまり、それとほぼ同率の23%が大学から検知されないだろうと認識している実態が示されました。
今回の調査結果により、正当な学習サポートツールとしてのAI、不正行為ツールとしてのAI、双方に明確な境界線を設ける難しさや大学側の検知体制の準備不足が浮き彫りにされたといえそうです。



学習時の使用目的では「概念をわかりやすく説明し直してもらう」や「提出課題の改善点を提案してもらう」が回答の上位を占めました
出典リンク
- The Times Higher Education | Quarter of students ‘believe AI-assisted work will go undetected’
- YouGov | Sample Size: 1027 students in the UK Fieldwork: 13th June – 13th July 2025
米国高3生の読解力と数学、過去20年間で最低水準、原因追求への議論に拍車
米国教育省傘下のNational Center for Education Statistics(NCES)が実施する全米教育進歩評価(NAEP)によると、米国高校3年生の読解力と数学の平均点が過去20年間で最低を記録したことが明らかになりました。
とくに読解・数学ともに基礎レベルを下回る生徒層の拡大が目立ち、その影響が高校3年生全体の低調な成績に反映される結果に。NCES責任者は、近年の生徒行動の変化として慢性的な欠席傾向を指摘しており、コロナ禍を機にオンライン学習環境が発達したことが、安易な欠席判断を助長している可能性も浮上しています。
また、コロナ禍以前より成績低下傾向は見られたことから、スマートフォン普及による集中力低下や読書離れ(視覚メディア依存)を主張する専門家も少なくないようです。



よくも悪くも自由に学習できる環境が整備されたため、完全にケアが行き届かない生徒層が広がってしまった印象があります
出典リンク
- The Guardian | ‘These results are sobering’: US high school seniors’ reading and math scores plummet
- The Nation’s Report Card | NAEP(National Assessment of Educational Progress:全米教育進捗評価)
Duolingoテスト、9月より日本で本格展開開始、大学向け10万回分の無償提供も
言語学習アプリの世界トップシェアDuolingo, Inc.(本社米国)は、9月25日に都内で開かれたイベントにて、自社の英語試験「Duolingo English Test (DET)」の日本市場への展開を加速させる取り組みとして英語試験の無償提供を含む先行導入プログラムを発表しました。
今後、Duolingo社は12ヵ月以内にプログラム参加を希望する大学と提携し、高等教育の国際化を支援する目的で5年間にわたり、DET10万回分をパートナー校に無償提供する見通し。また、文科省が設けた「英語資格・検定試験の特別受験制度」への参画も決まり、小・中・高等学校の英語教員であれば75%オフの割引料金(17ドル)で受験することができます。



大学出願に活用する英語能力試験としてIELTSとTOEFLの存在が際立ちますが、DETもここ数年で、米国を中心に第3の選択肢としてのシェアを広げつつあり、日本での本格展開にも注目が集まります
出典リンク
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
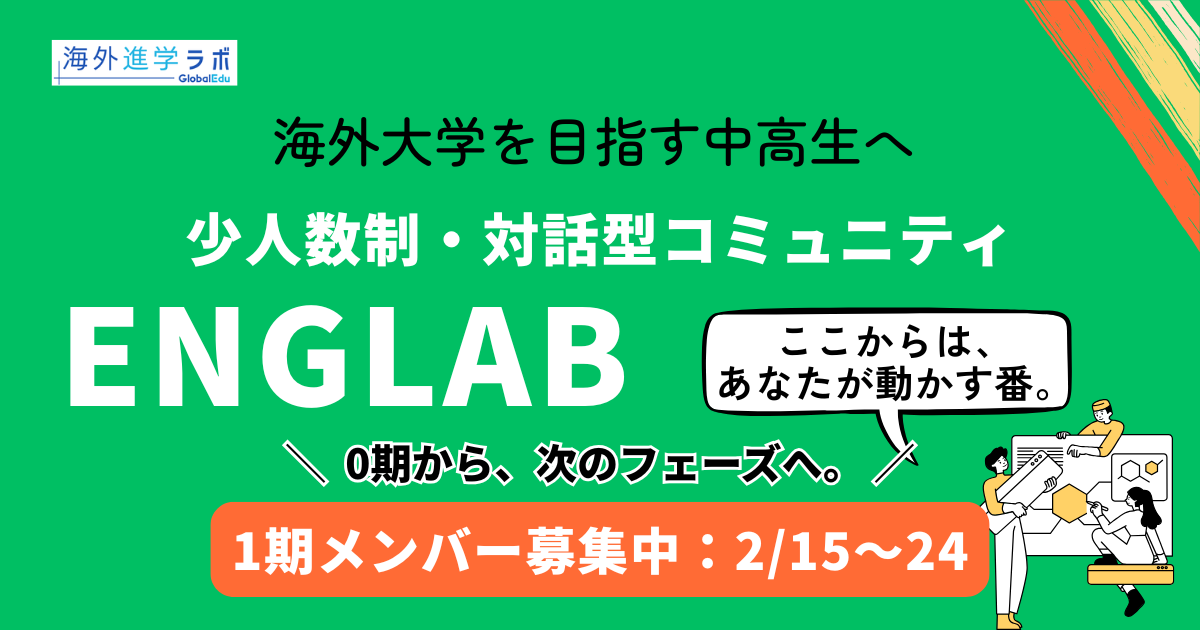


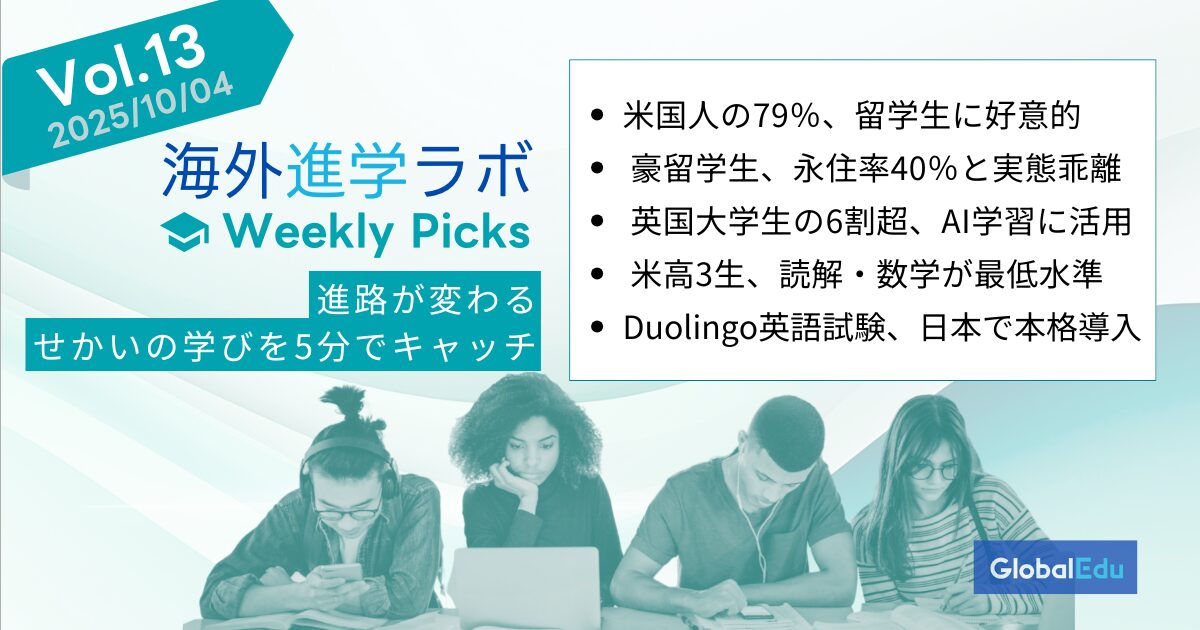




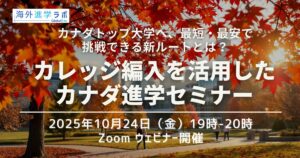
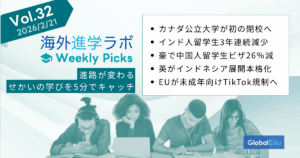
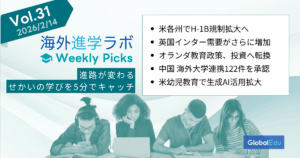


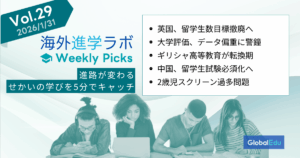
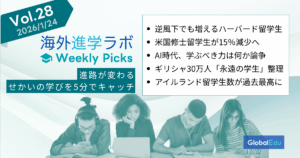
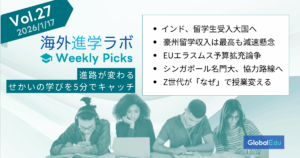
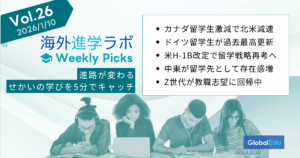
進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります