「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今週の海外進学Picksは、「高等教育の構造転換」と「学びの本質」を問い直す5本。
日本では文科省が学士・修士の一貫課程を正式に打ち出し、アカデミックキャリアの再設計が進行中。一方アメリカでは、留学生の就労制度や資金協定をめぐり、大学と政府の緊張が高まっています。
オランダでは留学生制限の経済影響が議論となり、イギリスではAIネイティブ世代の学び方に新たな示唆が。
世界の教育現場が“自由と成長”のバランスを模索する週でした。
文科省、学士·修士5年一貫制を推進する意向。院進学率上昇狙うもインセンティブ等に疑問符
日本の文科省は10月8日、学士と修士の5年一貫教育(4年+1年)を推進する制度改正ビジョンを公開しました。
現行制度下でも、成績優秀者に限り早期修了可能な仕組みは一部で採用されているものの、先進国平均を下回る大学院進学率の上昇と国際競争力のある専門的人材の輩出を促すため、より体系的な一貫教育課程の編成を目指しています。
例えば、文科省の方針に沿う取り組みとして、東京大学は最短2027年秋より学士・修士5年一貫の英語学位プログラム「カレッジ・オブ・デザイン」を開設する予定。
ただし、こうした改正を疑問視する見方もあり、同志社大学・山田玲子社会学部教授は「特に人文・社会科学系の修士号取得者を高評価する企業ニーズが伴わなければ、結果的に大学院進学率は上がらないだろう」と言及。さらに、教育機関間の移動性が損なわれる問題も指摘されています。
 副編集長 城
副編集長 城現状では国内就職というより、海外キャリアを志望する学生にとってメリットが生じるかもしれません
出典リンク
- The Times Higher Education | Accelerated graduate study in Japan raises quality concerns
- 時事通信ニュース | 学部・修士5年一貫制導入へ=大学院進学者の増加狙い―文科省
- 文部科学省 | 学士・修士5年一貫教育の促進に向けた検討について
米国上院議員、実質的なOPT廃止を政府に要請、米国留学の価値を高める制度に動揺
米国の有力上院議員は、9月23日付けで学生ビザ保持者への就労許可発行を停止するよう求める書簡を米国政府宛に提出。
「OPT(Optional Practical Training;卒業後最大1年間まで米国に滞在し、専攻と同じ分野の仕事に就くことができる制度)」という直接的表現は見当たらないものの、外国人留学生の就労が、大学を卒業した米国人の失業率上昇を引き起こしている等の見解が記されています。
政府系調査機関 opendoorsによると、OPT参加者は2024年時点で留学生全体の22%に相当する過去最高水準(約25万人)に到達。また、国際教育交流団体NAFSAの調査では、米大学院の留学生の半数以上がOPT が米国留学の決定的な選択理由と回答しています。
もっとも現状では議員レベルの案に過ぎませんが、何らかの変更があれば学生の進路選択に多大な影響が及ぶだけに今後の展開を注意深く見守る必要があります。



NAFSAの2023~2024年度調査では、留学生3人に付き1雇用が創出されるなど米国経済への多面的な貢献が示されており、書簡の主張はこうしたデータとは全面的に矛盾する内容となっています
出典リンク
- THE PIE | US Senator calls for end of OPT
- NAFSA | International Students Contribute Record-breaking Level of Spending and 378,000 Jobs to the U.S. Economy
- 政府系調査機関 opendoors | International Students Enrollment Trends
オランダ、大学留学生制限が50億ユーロの経済損失につながる可能性、画一的政策を防ぐ代替案の存在も
ランスタッド(オランダの主要都市エリア)の5大学がSEO Amsterdam Economicsに委託した調査によると、オランダ政府がランスタッド大学に課した留学生上限により、オランダGDPに40億~50億ユーロの減少が生じる可能性が明らかになりました。
分析では、上限策により短期的な歳出カット(年間約1億ユーロ)こそ実現するものの、税収や保険料収入の減少、景気や労働市場への悪影響が波及することで年間50億ユーロ規模の損失に到達する見通し。
こうした調査結果を受け、研究者らはオランダ大学の代表機関(UNL)が提案している共同自主規制案の有効性を指摘。この代替案によると、地域の特性や労働市場ニーズを考慮しながら、各大学がプログラム単位で入学定員の調整を行う仕組みが実現するようです。



今回の調査により、留学生減少による経済や国際競争力への潜在的なマイナス面の大きさが改めて浮き彫りになりました
出典リンク
- THE PIE | Netherlands faces €5bn loss over international student limits
- オランダ・ライデン大学 | Restricting student numbers will cost society billions
- Vereniging Universiteiten van Nederland | Package of measures for self-regulation: internationalisation
MIT大学方針見直し条件の資金優遇案に同意せず、米国政府への正式回答を先行表明
米政権は10月初旬、連邦政府資金の優遇と引き換えに、15%の留学生入学上限を設けることなどを求める協定書を9つの大学宛に送付しましたが、マサチューセッツ工科大学(MIT)は協定への拒絶を正式回答した最初の大学となったようです。
現政権が示した協定には、留学生上限に加え、1国の留学生は5%以下に抑えること、政府の要請に応じて全面的に留学生情報をシェアすることなどが盛り込まれています。
MITの学長は、回答書にて、表現の自由や教育機関の独立性が制限される取り決めや、資金提供先が科学的価値以外に左右される前提について反対を表明。
こうした動向には、カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事も反応し、「現政権からの協定に署名するカリフォルニアの大学には、州による資金援助を行わない」と大学への強硬的要求との対立姿勢を打ち出しています。



本協定は、留学生比率が現状15%を下回る大学のみに提示されており、さらに国際性の強い大学への牽制という見方もあるようです
出典リンク
- THE PIE | MIT rejects Trump’s preferential funding offer
- The Guardian | MIT rejects White House proposal to overhaul policies for preferential funding
- MIT | Compact for Academic Excellence in Higher Education
英国生徒6割以上がAIによる学習能力向上への悪影響を懸念、問われる教師の役割
オックスフォード大学出版局(OUP)が主導した英国学校におけるAI使用報告書によると、80%の生徒が学習目的で定期的にAIを利用する一方、62%が学習能力向上に対するネガティブな影響を実感しており、4人に1人が「自力に依らず簡単に答えに到達してしまう」と自覚している実態が明らかになりました。
OUPの生成AI及び機械学習製品の専門家は、「学習の本質的な役割やAIツールが学習にどのように役立つべきかを示唆する有益な回答が得られた」と評価。
さらに、「AI技術は世代間格差が大きいと考えがちですが、生徒はAIを効果的に活用するためのアドバイスを潜在的に求めている」として教師側の指導力の重要性を強調しています。



学習タスクを楽にこなす処理能力の恩恵を受けつつも、頼るだけでは本質的な学習スキルが身に付かないと案ずる学生として健全な葛藤が調査結果から読み取れますね
出典リンク
- The Guardian | Pupils fear AI is eroding their ability to study, research finds
- オックスフォード大学出版局(OUP) | Teaching the AI-Native Generation
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
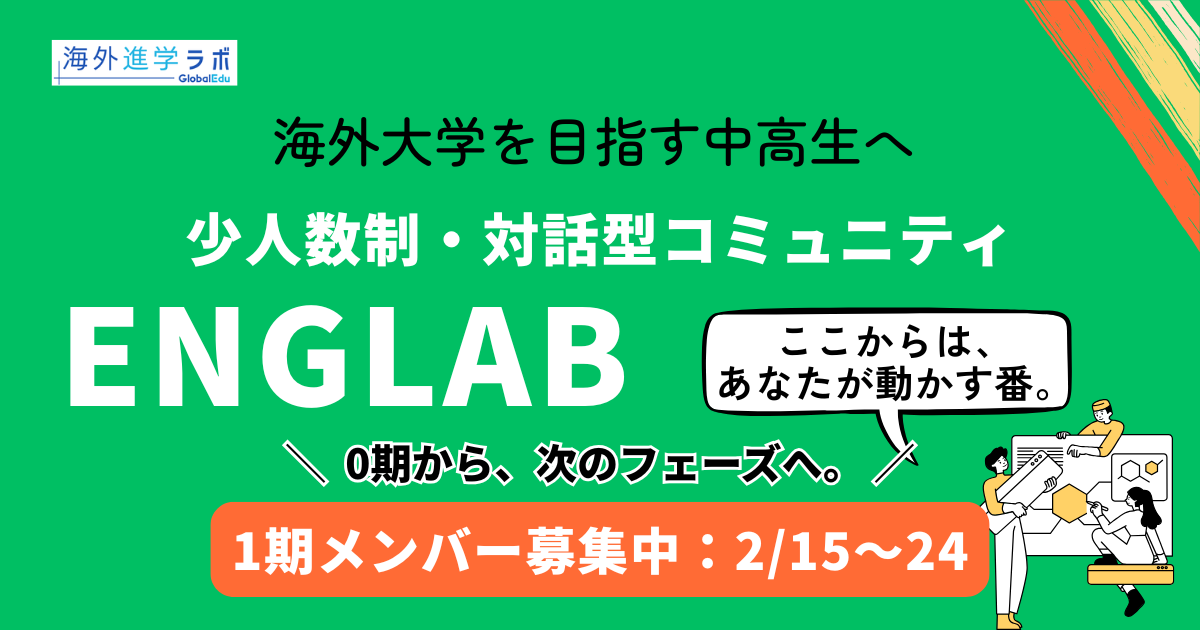


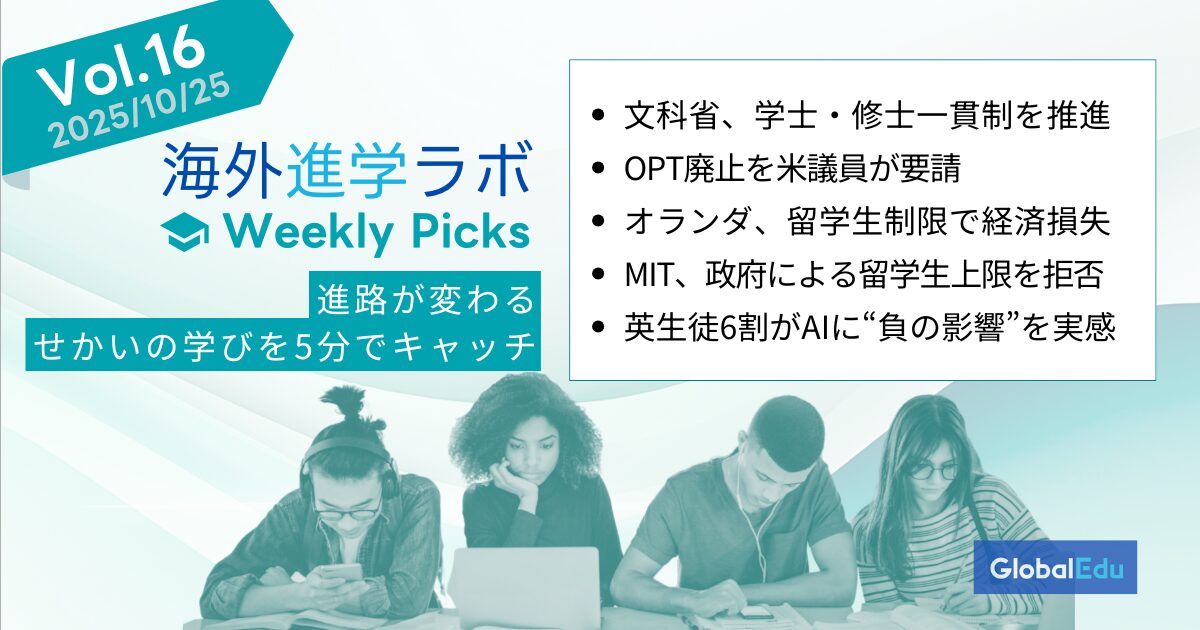





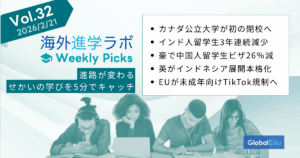
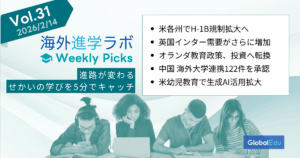


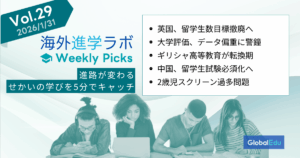
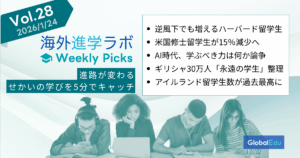
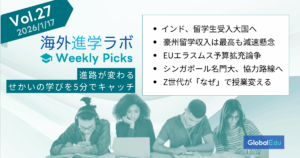
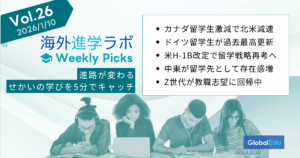
進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります