「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
世界の教育・進学動向を見渡すと、2025年秋も「信頼」と「深さ」がキーワードになりそうです。
米英の大学が依然として世界のリーダー層を輩出し続ける一方、政策の不透明さが留学生の選択を左右する時代に。
米国ではビザ制度改革が続き、AIを核とする新しいスクールモデルも台頭。さらに、学びの質を見直す潮流として「意図的にスローダウンする学習法」にも注目が集まっています。
変化の激しい教育環境の中で、「どんな環境で、どんなスピードで学ぶか」を問い直す時期がきています。
最新のソフトパワー指数、ハーバードやオックスフォードが各国のトップ指導者を多数輩出
英国シンクタンクのHEPIがまとめた2025年度ソフトパワー指数によると、世界各国の指導者(君主·大統領·首相)は特に米英の高等教育機関の出身者に偏る傾向が鮮明になっています。
ソフトパワーとは、各国の高等教育機関が世界に及ぼす影響力や評判のこと。米国は66名、英国は59名の各国トップを輩出し、第3位フランス(23名)以下を大きく引き離す影響力を示しました。大学別では、ハーバード大学(15名)とオックスフォード大学(12名)がそれぞれ10名以上の指導者を卒業生リストに抱えています。
HEPIディレクターのNick Hillman氏は、各国リーダーの4分の1が英国高等教育を巣立っているソフトパワーの恩恵を強調する一方、その波及効果が留学生への高額な課税等により相殺される現象を危惧しています。
 副編集長 城
副編集長 城複数の障壁が顕在化しても米英留学への支持が根本から揺るがないのは、こうしたソフトパワーの存在が大きいのかもしれません
出典リンク
- The Times Higher Education | Harvard and Oxford educate most world leaders, new ranking finds
- HEPI | Kaplan 2025 Soft-Power Index: Harvard and Oxford top the tree
政策の不確実性が留学生の進路選択行動の重大な懸念点に浮上、各国に問われる情報発信の質
IELTS運営母体、IDP Educationが実施した新調査によると、留学生にとって各国の政策の不確実性が進路決定の重大リスクに浮上している状況が明らかになりました。
134の国と地域、留学生7900人の回答を集めた調査結果では、学費負担が最大の懸念事項であることに変わりはないものの、ビザ要件や留学生上限などが事前説明もなく変更されることで進路決定を保留するか、他の地域を選び直す留学生の傾向が示されています。
これは、政府や教育機関が透明性と一貫性を伴う情報発信を行わなければ、仮に条件に恵まれた留学地域であっても留学生からの信頼は損なわれることを意味します。そうした観点では、米英がビザ·入国ガイドラインの明確さについて最低評価にとどまった一方、ニュージーランドが特に優れた情報提供主体としての評価を得たようです。



情報収集チャンネルの多様化により、選択する学生側の敏感かつシビアな意思決定行動が際立っている印象です
出典リンク
- THE PIE | Policy uncertainty emerges as top barrier to student mobility
- IDP | USA MEDIA RELEASE: Emerging Futures 8, Voice of the International Student
米学生ビザ(F-1)からH-1Bへの移行ケース、新手数料10万ドルの免除が明らかに
大統領令によりH-1B(特殊技能職)ビザ申請に新手数料10万ドルが設定された件について、米国で学ぶF-1ビザ留学生には同手数料は適用されないことが米国移民局(USCIS)発表により明らかになりました。
USCISが公開したガイダンスによると、米国外に居住する新規H-1B ビザ申請者に対しては追加手数料10万ドルを適用。一方、F1ビザからH-1B ビザに移行する際に多大な追加費用が発生するケースはなくなりました。これにより、米国内の外国人労働者や留学生に対しては余裕のあるH-1B 採用枠が確保される可能性も浮上。
今回の手数料引き上げにより、海外からの就労が減少し、米国企業の成長力が損なわれる等の懸念も寄せられていますが、ひとまず米国内就職を希望する留学生にとっては1つの安心材料と評価できそうです。



米国政府は、H-1Bビザ制度を積極的に見直す方向で動いており、今後も優遇条件等に変更が加わる可能性も否定できません
出典リンク
- THE PIE | F-1 to H-1B transitions to be exempt from $100K fee
- 米国移民局(USCIS) | H-1B Specialty Occupations
1日2時間授業、学科教員不在のAI学習私立スクールに脚光、専門家からは慎重論も
全米に14校を展開するK-8(幼稚園~中2相当)私立校「Alpha School」は、新拠点サンフランシスコ校にて、AI学習を大胆に全面活用する教育メソッドを導入し、各方面から注目を集めています。
AIツールを授業に取り入れる動きはAlphaに限ったものではないですが、Alphaサンフランシスコ校は科目教員を配置せず、1日わずか2時間のAI活用授業とライフスキルやチームワークを育む放課後アクティビティにより日々のスケジュールを構成。特に、教員不在という点では従来の教育現場の常識を覆す、革新的且つ効率の良い学びのあり方を提唱しています。
こうした取り組みについて、ハーバード大学教育学教授は「AI依存の学習は個人の資質によって成果ギャップが生じやすく、直接的指導を放棄すべきではない」と指摘しています。



仮に全生徒に適合する学び方ではないとしても、従来の対面集団クラスの欠点を解消する貴重な選択肢になりそうです
- 生成AI革命的進化への対応策、専門家は試験プロセスや評価方法の見直しを提言
- 進歩が著しいAI生成ツールに対するIB評価ディレクターの見解は?
- 英大学生のAI使用による不正行為1年で7000件発覚、逆に盗作は減少傾向
出典リンク
- The Guardian | Inside San Francisco’s new AI school: is this the future of US education?
- Alpha School San Francisco
意図したスローペースな学習が根本的な理解を促すという米国人教師の見解
米国の高校英語教師Cathleen Beachboard氏は、「カリキュラムを速いペースで進めて、残り時間を復習に当てる」という学習方針に対して懐疑的な立場を明かしています。
なぜなら、現代の脳科学研究も示すように、生徒が先を急がずじっくり理解できるよう促すことで記憶力や持続的な脳神経接続の向上が期待できるからです。
Beachboard氏はスローペース学習の本質とは、やることを減らすのではなく、正しいことをより良く実践する点にあると主張。例えば、以下のようなアプローチを推奨しています。
- 学習テーマを小さく絞り、より深く掘り下げる
- 生徒自身の考えに敢えてどのように反論できるそうかを問う
- 1つの学習スキルを扱い、生徒が独学可能な段階まで学びを拡張する
- 生徒のミスが目立つ部分を集計し、能動的に克服してもらう



ゆっくり着実な学習習慣こそ、トータル学習時間を短縮する可能性を秘めているかもしれません
出典リンク
- Edutopia | Intentionally Slowing Down to Ensure That Students Learn Material Deeply
- APA PsycNet |Effects of spaced versus massed training in function learning
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
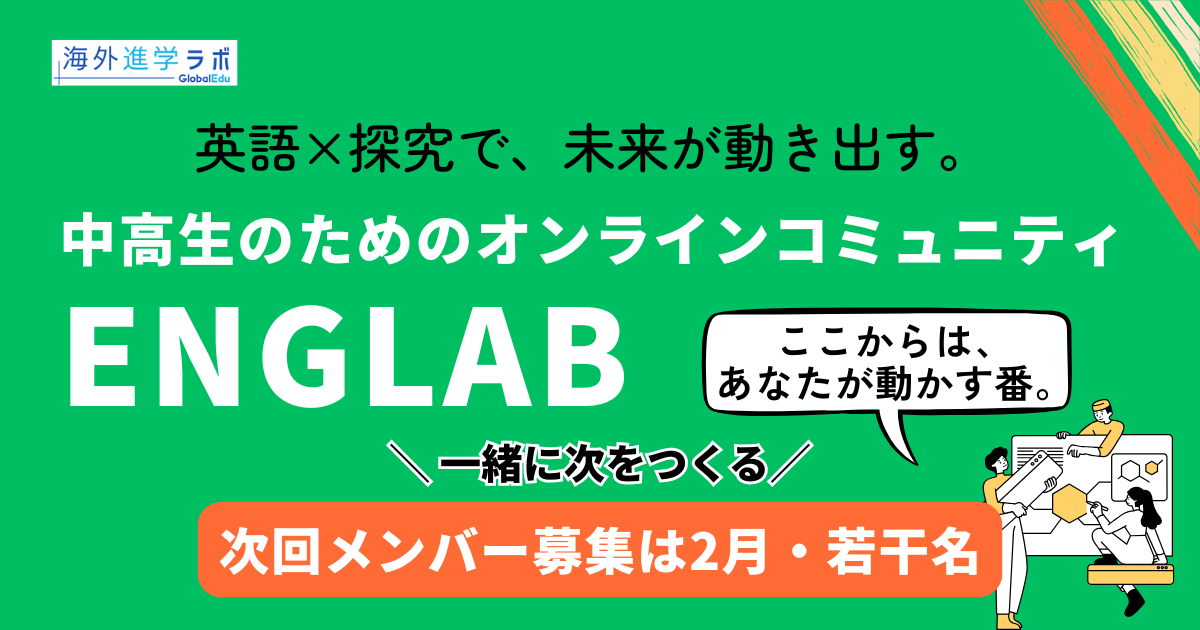


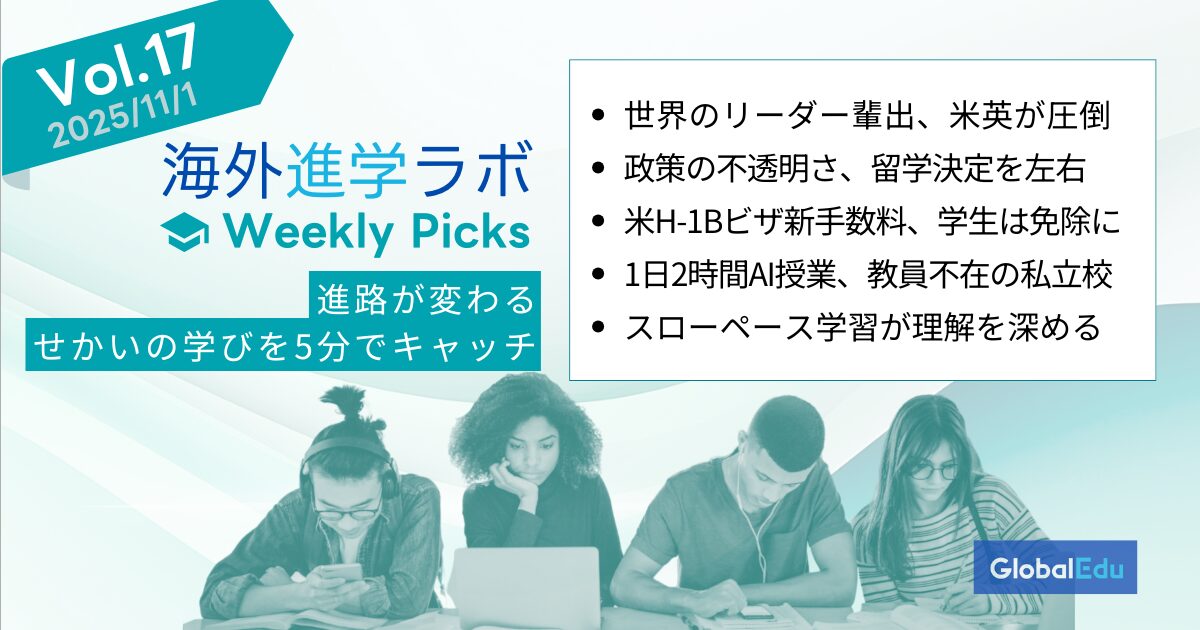






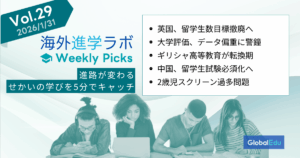
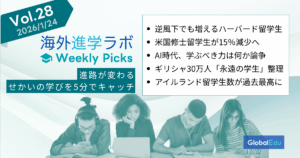
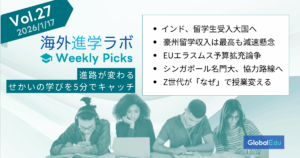
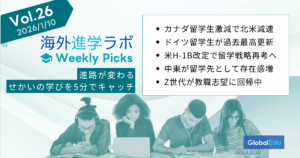

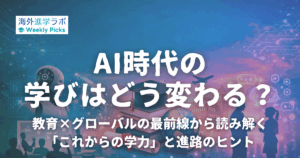

進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります