「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
海外進学を取り巻く環境が大きく動くなか、今週は「進路選択の前提が変わりつつある」ことがはっきり見える話題がそろいました。
MBAでは欧米の人気が落ち着き、アジアの教育機関に出願が集まるなど、将来の働き方を見据えた慎重な選択が進んでいます。一方、シンガポールのように国として留学生受け入れを抑制する動きも見られ、国ごとの姿勢がより明確に。
カナダは2026年から学部留学生の受け入れを大幅に制限し、質の高い大学院教育に重点を置く方針を示しました。さらに、英国では「欠席とメンタルヘルスの関係」、米国では「スマホを遠ざけるほど授業がうまくいく」という研究も。
どのテーマにも共通するのは、“学びの環境づくり”が子どもの未来に直結するということです。
最新MBA出願調査、欧米からアジアへ需要シフトが進行、慎重な進路選択トレンドを反映
世界中のビジネススクールが加盟する非営利団体「GMAC」がまとめた最新調査によると、従来のMBA教育の中心、米国や英国の経営大学院への出願が減少傾向を示す一方、アジア圏のMBAプログラムに対して顕著な出願数増加が確認されたようです。
具体的に、各国の経営大学院への海外からの出願件数は、米国3%マイナス、英国5%マイナス、カナダに至っては49%も減少。一方、アジア圏MBAへの海外からの出願状況は、インドが26%プラス、東南アジア及び東アジアが42%プラスを記録するなど需要シフトと捉えられるほどの増減が生じています。
大手教育コンサルの専門家は、各地域の地政学的な不安要素も影響し「教育投資が幅広い就職機会に結びつくのか、出願者はより慎重に意思決定する傾向にある」と背景を分析しています。
 副編集長 城
副編集長 城専門家によると、アジアの需要増加分が第1志望なのか、バックアップ出願なのかは現状では判別が難しいようです
出典リンク
- THE PIE | Global MBA demand shifts to Asia amid slowdown in the West
- GMAC | Application Trends Survey – 2025 Summary Report
シンガポール高等教育、他のアジア圏と異なり国際化志向が控えめな独自背景
留学先ビッグ4のトレンドと対を成すように、アジア地域は留学生を積極的に誘致する方向に舵を切っています。
しかし、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)副編集長によると、アジア圏グローバル教育の先鋒として知られるシンガポールは、国際化への際立った動きが現状は鳴りをひそめているそうです。
事実、2025年時点のシンガポールの学位需要は、前年比で学士17%減、修士14%減を記録。こうした背景事情に挙げられるのが、もともと地元民の絶対数や構成比率が他国と比べて小規模であること。
それにより、留学生受け入れに対して過敏な世論が形成されやすく、2010年代からは国主導で留学生を積極誘致するプロジェクト自体が実施されていません。
また、他国の主要ケースと異なり、大学経営が留学生の授業料にそう大きく依存しない構造も影響しているようです。



近隣アジアの大学需要の急速な伸びにより、相対的に国際化が停滞して見える一面もあるようです
出典リンク
- THE Times Higher Education | Is Singapore turning against internationalisation?
- Studyportals | Asia, Latin America, and MENA in Global Education — The flow of international students is changing
- 香港の大学、非ローカル学生の上限拡張進むも、多様化と本土化の均衡に悩む特殊事情
- 需要の急増で留学生がマレーシアに集まる、とくに中国人志願者の高シェアが鮮明に
- 日本の国際化推進を見据え学生数の制限を緩和、長期目標の達成に近づくか
- 韓国大学教育の国際化進む反面、留学生に対する就職面の障壁が課題に
カナダ政府、2026年以降の留学生受け入れを約50%削減する計画を発表、大学院生は規制外
カナダ政府は新たに発表された予算案のなかで、2026年の留学生受け入れ目標を2025年度の約50%減に相当する155,000人に定めることを明らかにしました。
この方針は、2026~2028年移民レベル計画に基づいており、2027年と2028年はいずれも新規留学生の目安を年間150,000人に設定。カナダ政府は、2018年比の2倍以上となった一時滞在者数の増加ペースを抑え、住宅・インフラ供給など持続可能な社会環境を整える狙いを説明しています。
その一方、優秀な人材の誘致を促す施策として、国際的な研究者や博士学生の採用を支援する13年間の予算割り当てや、大学院生に対する就学許可上限の免除措置なども同時期に発表されました。



現カナダ政権は一時滞在者数を管理し、質を重視する方向で動いていますが、留学生受け入れ態勢の有り方について困惑の声も広がっているようです
出典リンク
- THE PIE | Canada to slash study permit cap by more than half
- カナダ財務省 | Budget 2025 – Chapter 1: Building a Stronger Canadian Economy
- THE PIE | Canada exempts certain grad students from 2026 study caps
イングランド児童、欠席日数が多いほど精神疾患リスクが高まる調査結果、因果関係はあくまで双方向的
英国公認の統計機関ONSとラフバラー大学が実施した学童児童(5才~16才)100万人を対象とした調査によると、子どもが学校を欠席する日数が多くなるほど精神疾患を患いやすい傾向が明らかになりました。
例えば、出席率100%の生徒は100人中2人以下がメンタルヘルス問題で受診歴があるのに対して、欠席率30%の場合は100人中5人以上に同様の受診歴が確認されています。
欠席の長期化により精神疾患リスクが高まるだけでなく、元よりメンタルヘルスに問題を抱えていると欠席期間が長引くという一面もあり、欠席とメンタルヘルスの双方向的な関係性が示されました。
さらに興味深いのは、特別支援などの学校サービスを享受している場合、メンタルに問題を抱えていても欠席の増加傾向が鈍化すること。



学校側の各種サポートが、健康面で万全ではない生徒にもプラス要素を生み出しているのかもしれません
出典リンク
- The Guardian | School absence a big factor in child mental illness in England, data shows
- 英国統計局 | Child mental ill health and absence from school, England: 2021 to 2022
米国公立校教員向け調査、意志に依存しない携帯電話使用ポリシーこそ効果的と判明
米国の公立校教員2万人以上を対象とした超党派調査によると、校内のデバイスポリシーにおいて、単に携帯電話の使用を制限するだけでなく、どこに保管するか、どのように遠ざけるかを適切に定めることで教師の満足度および生徒の学習意欲が向上することが明らかになりました。
同調査にてわずか1%に相当する、ポリシー運用が「非常に適切」と評価を得た中学校では、授業中は携帯電話のロッカー保管を徹底するよう朝の校内放送を繰り返していました。
ペンシルベニア大学のAngela Duckworth発達心理学教授は、授業中のスマホ持ち込みを許可しながら厳格なルール順守を期待するのは「心理学的に愚かな試み」と指摘。個人の意志に頼らず、「保管や回収によって物理的に遠ざけるのが賢明な選択」と評価しています。



授業時の持ち込み禁止は、生徒にとっても学習しやすい環境が整うため、長い目で見ると大きな不満にはつながらないでしょう
出典リンク
- EdSurge | The Stricter the Cellphone Policy, the Happier the Teacher, Research Finds
- Phones in Focus | 米国の教育現場における 生徒の携帯電話利用ポリシー を科学的に調べる研究プロジェクト
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
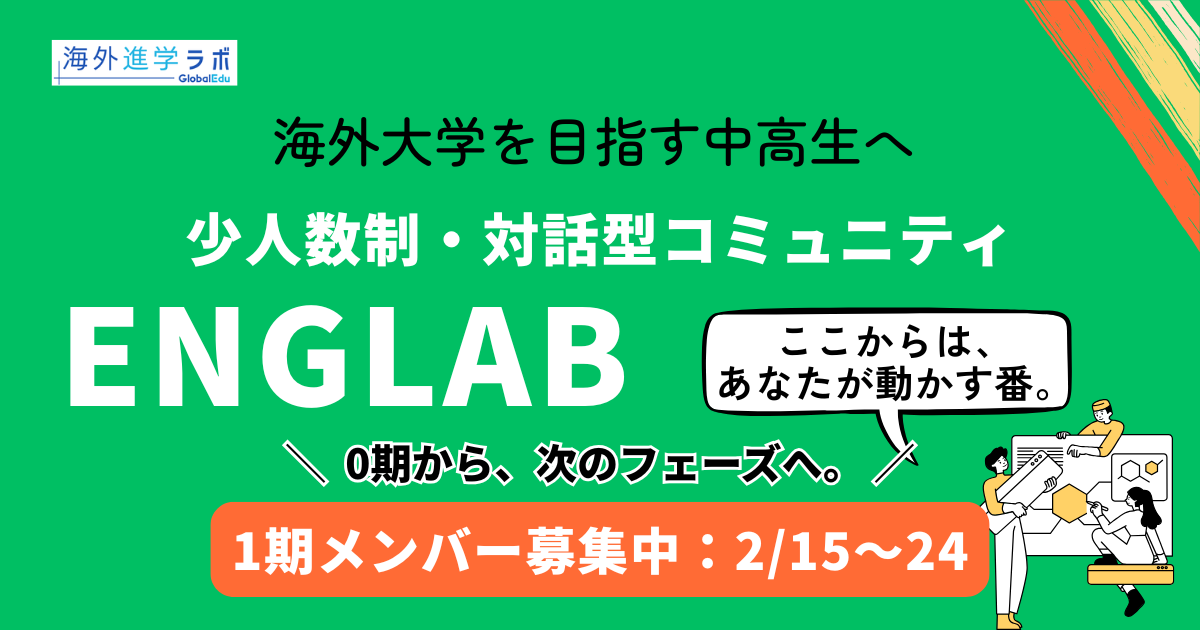


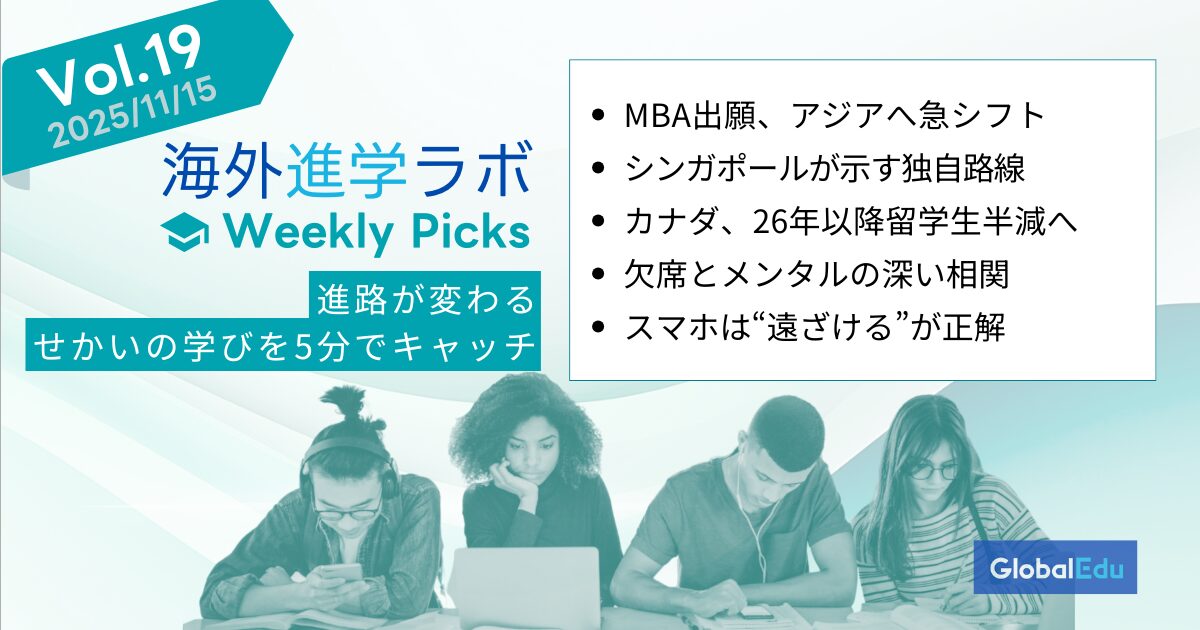






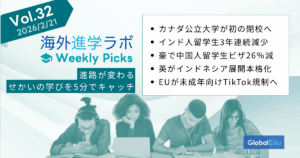
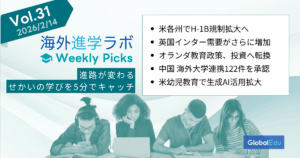

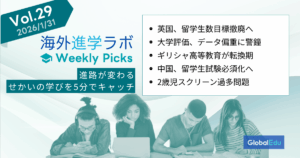
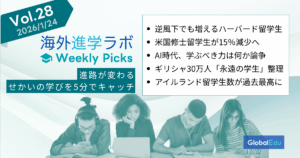
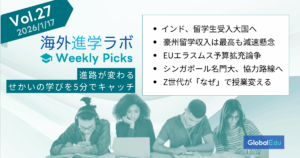
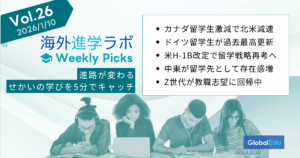

いま、進路をめぐる“前提”そのものが
少しずつ形を変え始めています