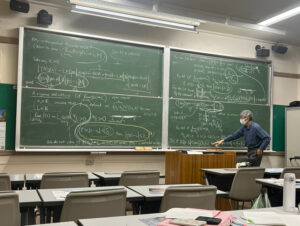ネブラスカ州立大学カーニー校 | TOEFL30点台から1年後に自力で入学→4年後にシカゴで就職するまでのプロセス全公開!

 SENPAI
SENPAI海外大学に進学したSENPAIが、留学生活をレポートします!


ネブラスカ州立大学 | 英語が話せない!と痛感した夏
米国「ネブラスカ州立大学カーニー校 University of Nebraska at Kearney」で、2015年12月まで、「Business Administration」(経営学)を専攻していた竹中萌といいます。
2011年の春に日本の高校を卒業し、その夏にアメリカの大学に進学。2015年12月に卒業しました。


この記事では、まずは①米国に進学するまでの経緯、②1年半でTOEFLの目標スコアを達成するために実践した勉強法、③進学までの手続き、④大学生活から就職までを、順を追って紹介していきます。
私が英語をはじめたのは、中学に入ってから。英語が好きで、大学でも英語を学びたいと漠然と考えていました。
ブルネイへの短期留学が人生を変えた
大学受験を翌年に控えた高2の夏休み、母が「いましかできないことを体験してきたら?」とすすめてくれた、ブルネイへの短期留学が私の人生を大きく変えることになりました。


当時の英語レベルは、英検2級程度。
ブルネイで直面したのは、「話したいことがあるのに何も伝えられない。みんなが何について笑っているのか全然わからない!」という衝撃的な事実。
悔しさと無力さで、とても歯がゆい思いをしました。
日本に帰る飛行機で考えたのは、「日本の大学に進学して、それから英語圏の大学に交換留学したとしても、半年や1年で高い英語力が身に付くのだろうか?」。
そこから、私の気持ちはアメリカの大学に進学する方向へ一気に傾いていきました。
ネブラスカ州立大学カーニー校
| 大学 | ネブラスカ州立大学カーニー校 University of Nebraska at Kearney |
| 所在地 | 905 West 25th Street, Kearney, NE 68849 U.S.A. |
| 留学期間 | 2011年8月〜2015年12月 |
| 留学コスト | 年間230万円(学費、生活費含む) |
| 専攻 | Business Administration(経営学) |
ネブラスカ州立大学 | 自力で米国大学へ進学
アメリカの大学への進学を思い立ちましたが、周囲に米国に進学した知り合いはおらず、当時の私には大学への入学方法や手順などについてまったく情報がありませんでした。
ネットで「アメリカ、留学」と検索をかけてみると、見つかったのは高額な手数料が必要となる留学あっ旋会社に関する情報。
いきなり出鼻をくじかれました。
両親に相談してみると、「入学までの手続きが自力でできないのなら、アメリカに行っても苦労するんじゃない? それでもがんばって自分でやり遂げるつもりなら進学していいよ」。
高2の2学期がスタートしてからは、とにかくアメリカへの進学だけを考え、ネットで進学先の大学を決めるための情報を検索したり、学校の外国人の先生に受験勉強や進学方法について質問したり、自力で海外大学の受験方法を調べ、そのための勉強をはじめました。
そして、約1年半の準備期間を経て、2011年8月に米国の大学へ進学することができたのでした。
ネブラスカ州立大学 | なぜ、カーニー校を選んだのか?
アメリカには4000を超える大学があるため、まず悩むのが大学選びとなります。
そこで、手はじめに検索したのがさまざまな大学の公式サイト。
大学選びは公式サイトのチェックからはじまった
「この大学センスいいなー、キャンパス内の芝生がキレイだなぁ」など思いながら、20くらいの大学のサイトをチェックしました。
サイトを見ていると「この大学いいかもしれない」と思う瞬間があるはず。
私はこのインスピレーションを大切にして、大学を選ぶ際の参考にしました。
そして、外せないのは、大学のある地域の「犯罪率」と「学費の安さ」。
姉妹都市だったネブラスカ州・オハマ市
じつは、私の暮らしていた都市とネブラスカの州都・オマハ市は姉妹都市関係にあり、「ネブラスカ州立大」オマハ校の正規授業料を減免する奨学金制度がありました。
当初はこの制度を利用するつもりで応募してみたものの、不合格。
高3の1月に結果が出て、あわててほかの大学も調べましたが学費は予算をはるかに超えていました。
カーニー校の学費が希望に合致
そんなとき、 SNSでカーニー校の学費が奨学金制度を利用するのとほぼ同額であることを知りました。
学費は年間で約170万円、生活費は家賃と光熱費込みで月5万円弱。
留学にかかる費用は、年230万円ほどで済みました。
キャンパス周辺以外は畑と牧場が広がるだけのカレッジタウンなので、ここでの犯罪も自転車の盗難くらいだと知って心は決まりました。
ちなみに、「ネブラスカ州立大学カーニー校」の当時のサイトは、大学の公式カラーがブルーとゴールドの好きな色の組み合わせで、掲載されていた留学生の写真が本当に楽しそうな表情をしていたのが印象的でした。


ネブラスカ州立大学 | 大学選びのコツ
大学の公式サイトでは、留学生向けのセクションが充実しているかどうかもチェック。
留学生向けの情報の多さでサポートの手厚さもわかる
詳細に入学方法が紹介されている大学ほど、より手厚いサポートが期待できます。
留学あっ旋会社を頼らない人にとって、大学の留学生を担当する部署によるサポートは必須。
入学できるかわからなくても、とにかく早めにメールで質問するなどして、コンタクトを取っておくことをオススメします。
どこの大学に行ったらいいのかわからず、留学あっ旋会社が紹介してくれる指定校に行けば間違いないと考える人もいるかと思います。
もちろんプロのコンサルタントに相談することも大切ですが、その会社から日本人学生がたくさん同じ大学に送られることもあるため、思わぬ人間関係で揉めることも考えられます。
日本の会社の情報は鵜呑みにしない
自力で調べて決めるなら、日本の留学サイトなどに書いてある大学のレビューはあまり信じないほうがいいと思います。
もちろん大学のレベルなどの統計は別ですが、ほとんどの大学情報はその学校を卒業した人が書いたわけではないからです。
とくに、学部や学科などの情報は古いかもしれないので、留学サイトは参考程度にし、大学の地理的条件や1年を通じた気候条件、実際にかかる学費など、さまざまな角度から調べ上げたほうが安全でしょう。
ネブラスカの冬の過酷さは想定外
実際、私もネブラスカに来てはじめて、冬の時期のほとんどが雪に覆われるほど過酷な気候であることを知り、呆然としました。


大学選びで迷うのなら、現地まで大学を見学に行くことをオススメします。
そういった準備も含めると、大学調べは高校3年生がスタートするまでにすませておきたいですね。
大学生活は人生のハイライトのひとつともいえる4年間。現地の学生を間近にみることで、勉強に対するモチベーションがかならず上がると思います。
「思っていたのと違う…」ということもあるので、早い段階で考え直すこともとても大事。航空券などの出費はありますが、不可欠ともいえるコストだと思います。
ネブラスカ州立大学 | 準備から進学までのプロセス
ブルネイからアメリカへの進学までは、下記のようなプロセスでした。
高2
- 夏休み…高2の夏、ブルネイにホームステイし、海外大学をはじめて体験。英語でのコミュニケーション能力の低さを痛感
- 9月…参考書「Longman Preparation Course for the TOEFL iBT Test」を購入し、TOEFL の猛勉強をスタート
- 11月…Speakingのスコアを上げるため、日本の大学進学塾を辞め、英会話スクールに通い始める
高校3年生
- 3月…高3の春休み、アメリカの大学を見学するためにユタ州の友人の家にホームステイ
- 8月…高3の夏休み、1日10時間ぐらいTOEFLの勉強をする。初TOEFL試験に挑む。また、高校時代の成績評価「GPA」(Grade Point Average)を維持するために、高校の授業や試験も真剣に取り組む
- 11月…「ネブラスカ州立大学オハマ校」への奨学金制度へ応募
- 1月…奨学金制度応募の結果は不合格。「ネブラスカ州立大学カーニー校」への進学を決め、出願書類の準備をはじめる(これはかなり遅いと思います)
- 3月…高校を卒業。卒業から2週間ほどして大学から合格通知が届く
高校卒業後
- 4月…学生ビザを取得
- 5月…渡米し、ネブラスカ州立大学附属の語学学校へ通う(授業のスタイルが想像できず心配な人には準備期間としてオススメ)
- 8月…ネブラスカ州立大学カーニー校に入学
ネブラスカ州立大学 | TOEFLのスコアが足りない!
アメリカの大学に進学する際、もっとも重要だったのは「TOEFLで必要な点数を獲得すること」でした。
TOEFLは、非英語圏の出身者が英語圏の学校に入学を希望する際に必要な「外国語としての英語力」をはかるためのテスト。
現在は、試験センターのコンピューター上で受験する「TOEFL iBT」が主流となっており、試験に必要な時間は約4時間半。


ReadingとListening、Writing、Speakingと4技能をはかるテストで、120点満点で採点されます。
受験料も230ドル(試験日の7日まえまでに申し込んだ場合、2016年3月現在)と高く、アカデミックな内容のため難易度も高い。
日本の受験英語ではまったく通用しないので、TOEFLのスコアアップは大きな課題となります。
最初に受けたTOEFLは30点台
高3の春、試しに英検準1級を受けてみたところ、不合格。アメリカの大学の授業についていかれるか、不安しかありませんでした。


最初に受けたTOEFLは、120点満点で30点台。Listeningのスコアの悪さがかなり足を引っ張りました。
「天文学の授業を受けているという設定で教授の次の質問に答えよ」というようなリスニング問題からスタートし、最後まで何もわからないまま固まっていたのが初回のTOEFLでした。
最終スコアは64点
高校を卒業したら、そのまま4年制の州立大学に行きたい。だから、目標スコアは60点以上。60点以上ないと、授業についていけないと考えたからです。
この点数は、米国の難関大に必要とされるスコアとくらべるととても低いのですが、転学などのストレスが溜まるような進路変更は絶対したくなかったので、短大(コミュニティカレッジ)に入ってからTOEFLのスコアを上げ、難易度の高い大学に入り直そうとは考えませんでした。
最終的に、TOEFLのスコアは64点まであげることができました。
ネブラスカ州立大学 | 役に立った7つのTOEFL勉強法
それでは、さっそく「これは役にたった!」と実感したオススメ勉強法を7つ紹介していきたいと思います。
①参考書をやたらと購入するべからず
参考書をたくさん購入する人も少なくないと思いますが、それはNGです。
買っただけでその情報のすべてが手に入ったような気になりますが、活用しきれなければなんの価値もありません。
TOEFLの形式に慣れるには、まずはTOEFLを早い段階で「受けてみる」こと。そして、TOEFL公式参考書を入手し、問題も回答もすべて英語で勉強してみること。
海外の語学学校では、日本語で解説してくれる人などいませんよね。英語を英語で学ぶことによって、海外の生徒と同じ土俵で勉強していという意識が持てるのです。
解説まで英語で書いてあると使いにくいのですが、解説にある知らない単語まで知識として増えるので一石二鳥。
私が活用したのは、参考書「Longman Preparation Course for the TOEFL iBT Test」です。
もし、「時間がかかるし、そんなのハードルが高すぎる」と思うのなら、日本の出版社から出ている参考書を1冊と決めてコンプリートしてください。
TOEFLでもっとも必要になるのは「語彙量」なので、私は英字新聞をとって毎日読んでいました。
そして、毎月購入していたのが月刊誌「CNN ENGLISH EXPRESS」(朝日出版社)です。CNNで報道された最新のニュースを、CD音源と翻訳付きで読めるため速読力が身につきました。
現在では、スマホなどでも読むことができる電子版も販売されているので、より便利に勉強できるようになりました。
②映画や海外ドラマを繰り返し観るべし
洋画を観ることの利点は、想像以上に多いです。日本語字幕を観ながら聞き流しているだけでは、ただの映画鑑賞。どうすれば有益に活用できるのか?
オススメの鑑賞法は、リモコンを持ちながら英語の字幕付きで観ること。知らない単語が目に入った瞬間画面を停止し、その単語を抜き書きします。
当時「プラダを着た悪魔」(米国、2003年)という映画がマイブームだったので、20回ぐらい観ました。
ニューヨークのファッション雑誌編集部を舞台にした映画なので、ニューヨーカーたちの早口なおしゃべりが満載。
英語に聞こえてくるまで時間がかかりましたが、好きなフレーズをまるごと覚えて、実際に使えたときは少し感動しました。
映画を観ながら口を動かしてみると、シャドーイングがいかに難しいかわかります。
つねにリモコンとペン、そして口をパクパクしながら洋画を観たことで、いろいろな感覚が一度に研ぎ澄まされた気がしましたよ。
④SNSを活用するべし
高校時代からじわじわと流行していたのが、さまざまなタイプのSNS。
現在ほど便利なアプリやサイトは充実していませんでしたが、そのなかでも「無料なのに優秀!」と思って利用していたのは、以下の3つのサービス。
Podcast
「Podcast 」は、iPodの「Pod」とbroadcastの「cast」を組み合わせた造語で、iPodを購入したときから利用しています。
さまざまな英語音源のチャンネルがありますが、高校時代は「CNN Student News」と「TED Talks」を観ていました。一度ダウンロードすればどこでも聴けるので、とっても便利ですよ。
YouTube
「Beauty YouTuber」「 Fashion YouTuber」などと呼ばれる同年代のユーチューバーたちが、英語でメイク方法や買ったモノ、自分の部屋や学校生活などを紹介する動画を観ていました。
観ていて純粋に楽しめるため飽きなかったし、アメリカの高校や大学で流行っているモノの知識が増えたので、大学入学後も話題に乗り遅れることはあまりありませんでした。
英語力向上のために、フォローしていたアカウントのほとんどが英語のもの。
短い英語フレーズと日本語訳をたくさんタイムラインに流し、パッと使えるようなカジュアルな英語を習得するのに活用。
好きなアメリカの俳優やセレブのつぶやきのほとんどが知らない単語だったため、楽しみながら語彙を増やすことができました。
④英語で日記を書くべし
高校英語ではつねに英訳や和訳の課題がありましたが、長文を書く課題はあまりありませんでした。
TOEFLのWritingでは、真っ白のページをビッシリと長くてクオリティーの高い英文で埋めて行く力が求められます。
英語で文章を書いてみると、知らない単語や文法のせいでなかなか進まないかもしれません。でもそこから掘り下げて勉強していくことで、弱点が一気に補強されることになります。
毎日一文でも多くの文章を英語で書き、書きっぱなしではなくそれを添削してくれる人を見つけましょう。
私は、高校のALTの教師がいつも職員室で退屈していたので、話しかけたり英作文を添削してもらったりしていました。
また、母の知り合いのスロバキア人にお願いして、SpeakingとWritingの特訓をスタバで不定期でやってもらったこともかなりプラスになりました。
⑤最強の単語カードを作るべし
一般の単語カードよりサイズが大きめのものを選んだり、大学ノートのページを半分にして赤ペンと赤シートで単語ノートを作ったりしました。
書き込むのは、毎回つまずくような本当に覚えられない単語。20個近くは作ったと思います。
単語カードを作る際、単語カードに表も裏もびっしり例文や類義語を付け、単語でなく文章をまるごと覚えていました。そして、その単語カードを歩きながら見ていました。
たとえば「make sense of」という単語帳を作りたかったら、表に「make sense of someone’s command」と書き、裏に「(人)の命令を理解する。interpret, see, construe」と書きます。
「理解する」という意味のmake sense ofを使いたいのに、それが思い出せないとき3つ類義語を書いておけば、記憶の隅にどれか残っているはずです。
英会話の途中、思い出せない単語のせいで固まってしまって会話終了とならないために、make sense ofとその類語をセットで覚え、例文中のcommandという名詞の意味までおまけで覚える。
これぞ、最強の単語カード!
五感を刺激するために、何か噛みながら読んだり、図書館を一周しながらブツブツ読んでみたりもしました。
⑥しるしを付けながら長文読解するべし
難解な文章になるほど、一文が長くなっていきます。長文を読み続けると、知らないうちに文章だけ読んでいて、内容が頭に入っていないことに気づくかもしれません。
それを防ぐために、主語がどこからどこまでで、動詞が何なのか線を引いたり丸をつけたりスラッシュをつけることをオススメします。
TOEFLの問題を何度も解いていると、質問や正答がある程度想像できるようになります。その際、同じ文章を何度も読まなくてすむよう、しるしを付けると時間短縮が実現します。
TOEFL iBTはPCで受験するので本番では同じことができませんが、読みながら手を動かすことが習慣になると、試験中メモを取ることは許されているので、大事な小節や一文を書いて、短時間で答えに辿り着けるようになると思います。
⑦和訳するべからず
日本の大学入試では「以下の文章を和訳しなさい」という問題がありますが、海外大に行くためにはきちんと内容を理解して要約できれば、キレイな日本語に直す作業は必要ありません。
完璧な和訳をしようとこだわると、頭のなかで常に日本語で考えてしまうため反応が遅くなり、むしろ悪影響です。
違う英単語を使い、「同じ文章を書き換えられる力」を意識して勉強することが重要です。
ネブラスカ州立大学 | 出願の流れを押さえよう
今回は、私がアメリカ留学のためにどのような手続きをし、願書送付からビザ取得までに至ったのかをシェアしたいと思います。
最初に、ざっくりと入学手続きまでの流れを説明します。
出願で必要なものを確認
まずは、大学のサイトに行き「Admission」(入学者選考)をクリック。「International」(留学生)と「Requirements」(必要項目)をよく読んだうえで、出願するうえでなにが必要なのか確認します。
この段階でTOEFLやSATのスコアが足りない場合は、大学の語学学校に出願し、その学校で十分な点数を得てから大学に上がることも可能です(記事の下部に語学学校についての情報があります)。


必要事項が揃ったら出願してみよう
必要項目のすべてが当てはまっていたら、オンラインアプリケーションに進み、その大学の出願プロセスで必要なユーザーネームやパスワードなどを作り、まずオンラインで出願。このとき、アプリケーション費が発生すると思うので、クレジットカードが必要となります。
つぎに必要となるのが、銀行の残高証明書、パスポートのコピー、必要なTOEFLなどの試験の点数を証明する書類、そして高校の成績証明書。
もちろんこれらはすべて英語で書かれている必要がありますが、銀行でも高校でも「アメリカの大学に行きたいんですが」と話したら、2日間ほどで英語で作ってもらえました。
そして、大学によって異なるため一概には言えませんが、上記書類を大学のオフィスに送り、合格を待つという流れとなります。
大学決定から出願までの流れ(動画)
以下は「U.S. Embassy Tokyo」(アメリカ大使館) が作成して公開している、「アメリカ留学での大学決定→出願までの流れ」が紹介されていますので、ご参考までに。
大学から送られてくる書類は「合格通知」、「I-20」(学生ビザ取得に必要)、学生寮や学生サービスなどの書類、そして健康保険に関する書類などです。
それらが届いたら、学生ビザ取得の準備に取り掛かることができます。
ネブラスカ州立大学 | 学生ビザの申請&取得法
原則として週18時間以上の授業時間数の授業を受ける人は、滞在期間にかかわらず「学生ビザ」(F-1ビザ)の申請が必要となります。
学生ビザの発行プロセス
大学に必要書類を送り、返事が来て、入学手続き等の書類を受領してからのビザ発行までのプロセスは、以下のとおり。
- 「入学許可証」(I-20)が大学から送られてくるのを待つ
- 「米国国務省」サイトより学生ビザ申請の必要書類を取得する
- SEVIS費の支払いをする
- ビザ申請料を支払う
- アメリカ大使館での面接の予約を取る
- 大使館へ面接に行く
- 学生ビザ付きのパスポートが郵送されるのを待つ
大使館での面接のポイント
大使館での面接でのポイントは、「学業のためにアメリカへ行くのであり、卒業後は出国の意思がある」ということを明確に伝えること。このビザは、大学卒業後3ヵ月で失効となります。
卒業後不正にアメリカに滞在して悪用されないよう、面接官は「勉学のためだけにアメリカへ行くのですよね?」という雰囲気で質問してきます。
かならずYESと答え、間違っても「卒業後はアメリカに残りたい」などと曖昧な表現で返答しないよう注意が必要です。
面接といっても、「なにを勉強しに行くのですか」といった単純な質問が3問ぐらいあっただけ。アメリカ人の片言の日本語での質問だったので、私の場合、ほとんど日本語のみで終わりました。
この学生ビザ申請のプロセスは、順番を間違えると情報不足となり面接の予約まで進むことができません。ひとつずつ確実に行うためには、わからないことがつぎつぎと出てくると思います。
それでも、インターネットで調べたり、くわしそうな周囲の人に聞いたりすることで、代行サービスに頼らずに手続きを行うことは十分可能です。
すべて正確に手続きをし、ビザ付きのパスポートが送られてくれば、きっと渡航前の自信につながると思いますよ。
ネブラスカ州立大学 | 語学学校の活用について
語学学校への語学留学は、TOEFLなどの英語の試験勉強をするための学校なので、入学はとっても簡単。
アメリカでは、1月に「春学期」がはじまり5月に終わるので、語学学校では5月から夏の授業を履修することができます。
高校卒業後は5月に語学学校に入学するのがベスト
3月に高校を卒業した人が、大学附属の語学学校に入学するのは、夏学期がはじまる5月がベスト。
語学学校に入学する際に受けるTOEFLの点数がクリアしていれば、そのまま大学の授業を受けることができ、そのプロセスはとてもシンプル。
ひとりずつアカデミックアドバイザーがついてくれ、語学学校のスタッフが大学への手続きをすませてくれたり、その方法を事細かに教えてくれます。
もし、8月までにTOEFLがパスできなければ、12月までの「秋学期」まで語学学校に行くことになります。その期間に必要点数に達すれば、1月から始まる春学期に学部入学することが可能です。
アメリカの大学への入学のチャンスは年に3回
アメリカでは入学式というものがありません。しかし、卒業式が春・夏・秋の3回あるため、入学する機会も年3回あります。
そのため、1学期休学してインターンをしたり、夏に学費を稼ぐために完全に学業から離れた生活を送ることもできます。
夏に授業を取ることで早く卒業することも可能なので、毎学期詰め込めば(私はすすめませんが)3年間で卒業することも可能です。
ネブラスカ州立大学 | 「華麗に卒業」とはいかない大学生活
私がアメリカで送った大学生での1日の生活は、おもに以下のような内容でした。
- 7時…起床後、シェアハウスのキッチンで朝食
- 7時30分…徒歩25分でキャンパスまで通学
- 8時…授業
- 10時…授業
- 11時30分…友達とキャンパス内で昼食
- 14時…図書館でクラスメイトと勉強(おもにこの日の授業の課題と予習、オンラインテスト)
- 16時…家でルームメイトと一緒に過ごす(なにもしない)
- 18時…授業(ナイトクラス)
- 20時…ルームメイトと夕食
- 22時…友達とLINE、家族とSkype、もしくはテスト勉強
- 24時…シャワー
- 25時…就寝
このように「基本的に勉強している」のが、大学での最後の学期のライフスタイルでした。
大学4年生の卒業前に単位をほとんど取り終え、就活を終えて有意義に過ごすというのが私の目標でした。
しかし、難易度の高い授業を学生生活後半まで「やりたくない」という理由で放置し続けた結果、完全に遅れを取ってしまいました。
起きている時間は基本的に勉強しないと卒業できないかもしれない…という危機的状況に陥ったのです。
卒業に必須だったマネージメントの最難関クラスをとった際、1ヵ月後教授からメールが。
「このままだと君は絶対卒業できないから、毎週水曜日にオフィスに来てプロジェクトの進行状況を見せなさい」と。
そんな状況をまったく知らない母は、卒業式にアメリカに来るのをとても楽しみにしていました。
私も、母がアメリカ行きの話をするたびに焦燥感に駆られました。
ネブラスカ州立大学 | 滑り込み「卒業」はスリルいっぱい!
アメリカの大学の卒業式は、日本と異なり、春夏冬の3回あります。
毎回卒業が決まるまで、スリルいっぱい!
私の場合は、12月2週目の水曜日に最後の期末試験を受け、その2日後の金曜日に卒業式に出ました。
アメリカでは「卒業式歩く?」というおもしろい質問をよく耳にします。
まず、卒業するためには卒業式に出るための手数料を払い、式典で着るためのガウンなどをレンタルしなくてはなりません。
卒業式では壇上で学部長と右手で握手をし、同時に左手で卒業証書を受け取ります。しかし、その中身はなんと空っぽ(!)。
卒業証書が届かないと本当の卒業かわからない⁉️
卒業式の前日まで期末試験を受けている人もいるため、最終的な成績が出るのに数日かかり、どうしても証書が卒業式当日に間に合わないのです。
つまり卒業式を「歩く」人たちは自分が本当に卒業したのかわかっておらず、実際に卒業したかわかるのは本物の卒業証書が届く日なのです。
私は金曜日に卒業し、その週の日曜日に就職のためシカゴに引っ越す予定でした。
そのため、最後に受けた期末試験の結果を早く出してもらわなくてはなりません。
教授のケータイに何度も連絡した甲斐があり、卒業式は13時に終わり、卒業証書は当日の17時にもらうことができました。
しかし、私の友達は翌週の木曜日まで待っていたし、学校によっては2ヵ月以上かかることもあるそう。もちろんそれまでに成績はオンラインで確認できますが、卒業証書が手に届くまで安心できません。
私は限りなくギリギリで卒業しましたが、周囲では難易度の高いクラスもバランスよく1、2年生のときにとり、後半に詰め込まない人も多くいました。
希望する時期に卒業するためには、全米の大学の教授の評価をシェアするサイト「RateMyProfessors」を活用して単位取得の傾向をチェックしておいたり、友人や先輩にどの授業を・どの教授で・どのタイミングで取ればいいかを聞いてみることがとても大切です。
また、私の大学ではどのクラスも20名ぐらいで授業をしていたので、授業に行かないとかならずバレました。
教授によっては「なぜ今日提出の課題を出していないのか」とメールが来ました。
もちろんすべての教授がそこまで面倒見がいいとは限りませんが、1クラスだけでのつながりとは思えないほどよくケアされていたと思います。
ネブラスカ州立大学 | 大学時代は「自分の強み」を模索する時期
ここまで勉強について紹介しましたが、留学生活では「勉強だけではいけない」と思います。
勉強ができる学生は世の中にあふれるほどいて、同じ専攻を卒業をする学生も全米に数え切れないほどいます。
就職を視野に入れて自分の強みを探す
そのなかで、日本からきた留学生としていかにして「自分はちょっと違うんだ」というユニークな部分を見せることができるか、就職を考えるうえではとても大事になってきます。


私は、アメリカでの就職は「学歴主義、コネ歓迎」というイメージを持っていますが、実際、銀行員になりたいのなら地元の銀行でインターンをしたり、商社でバイトしたりして早いうちに多くのネットワークを作る人も多くいます。
戦略ありきの履歴書を作ろう
就職について明確なイメージを持ち、具体的な経験を織り込んだ履歴書は、学歴のみで勝負する人よりも強い武器となります。
人事担当者も「卒業後すぐに即戦力になる学生」を選ぶので、「新卒で何もわからないけど頑張ります」と就活する人よりも内定は早くでます。
大学の専攻が仕事に直結する
そして、日本と大きく違うのは「旅行学の専攻で卒業した人が銀行で就職する」ことは、ほぼ不可能だということです。
日本でも、英文学専攻だった人がエンジニアの部署に配属されることはないと思いますが、アメリカではとても簡単に学部や専攻が変更できるのにも関わらず、就職先の業界を選ぶのは日本より難しいのです。
留学生である以上、バイトやインターンをするのはビザの関係上難しいですが、3ヵ月以上ある夏休みにどれだけ人と違うことができるかが、仕事を得るうえで大きなポイントになります。
人事担当者が履歴書を見ただけで「この学生と会って話をしてみたい」と思ってもらえるような履歴書を作るために、大学生活前半から貪欲に普段と違うことに挑戦するのをオススメします。
こういった挑戦は、最終的には「この業界は自分に向いてないな」と早く気づくチャンスにもなりますよ。
ネブラスカ州立大学 | 留学で得られる「大切なもの」
アメリカの大学では、日本ほどサークル活動が充実していません。
しかし、学生の間に起業したりボランティアをしたりと忙しい人は本当に忙しいいっぽうで、ヒマな人は時間を持て余してしまうという両極端な生活になる可能性があります。
誘われたらなんでもやってみる!
私はなにをするにも時間がかかるタイプなので、勉強だけでも十分忙しかったのですが、それだけで学生生活を終えたくないなともずっと思っていたので、「とりあえずなんでも誘われたらやってみる」というポリシーでネットワークを広げていました。


私の成績は友人が驚くほど低かったのですが、常に「自分はこうなりたい」という具体的な卒業後のイメージを持ち続けていたので、「もう辞めたい。日本に帰りたい」と言いながらも、卒業までなんとかモチベーションを持ち続けることができました。
大学が自分に合っていないのなら、環境を変えるために転学したり、休学して社会に出るのもアリだと思います。
そして、新しい環境でゼロから自分のコミュニティを作るのがどれだけ大変なことなのか、早く学習することがとても重要です。
投げやりにならず、同じ場所で頑張ってみる
簡単に「この大学つまらない」と投げやりにならず、同じ場所で頑張ると、その長い期間に一緒に成長できるたくさんの人たちと出会うことができます。
米国での大学生活で、私が得た一番のものは「友達」です。
彼らとの出会いが今の自分をつくった、と言っても過言ではありません。できるだけ多くの人に会うために、そしてその人たちを知る以上に自分のことを知るために、私は海外留学を目指している人を応援しています。
ネブラスカ州立大学 | 思い立ったら、今日から準備しよう
とりあえず「海外大を選択肢に入れて進路を考えている」という人、思い立ったら今日からなにかはじめましょう。
競争相手は日本の外にいる
あなたの競争すべき相手は、日本の外にいます。誰かが同じ参考書をAmazonで注文し、世界のどこかで同じ問題を解いているかもしれません。
私は地方出身なので、県内でTOEFLが受けることができず、対策をしてくれるような塾もありませんでした。
でも、「TOEFL iBT勉強法」で紹介した内容を中心に、トライ&エラーで目標点数に達することができました。
アメリカには優秀じゃない学生はいない
アメリカの大学生は、日本の学生とは比較にならないほどよく勉強します。海外から来る優秀な留学生たちと同じぐらい勉強しないと、卒業後仕事を取られるからだと私は理解しています。
アメリカの学生は、授業中居眠りをしたりスマホを見たりしないし、むしろ優秀じゃない人がクラスにいないのです。
大学に行かなくても、別に死ぬことはないし、パートタイムの仕事ならどこにでもあります。だから、「本当に自分は将来これがやりたいんだ!」という確固たる意志のない学生はどんどん退学していきます。
教室にいる学生数が激減するような、授業についていくのが困難なほど難関なクラスもあります。
ビジネス系の学部生の誰もが恐れる「ファイナンス」のクラスでは、半数のクラスメイトが落第。毎回試験が終わるたびに、学生の数も減っていきました。
過酷だけど、世界中からの仲間と過ごせる素晴らしい場所
過酷な部分も多いアメリカ留学ではありますが、世界中から集まったさまざまなバックグラウンドを持つ人たちと毎日過ごせる素晴らしい環境です。
私の大学の在籍学生は5000名と中規模だったので、キャンパス内を歩いているとかならず友達に会いました。
どのクラスも少人数で、ディスカッションやグループワークも多く、クラスメイトと協力しないと突破できないプロジェクトも数多くありました。
勉強漬けの毎日に嫌気がさしてホームシックになったとき、『あー大学辞めたい、日本に帰りたい』と突発的に思ったことも幾度となくありました。
でも、出会いには恵まれ、友達の存在のおかげで思い留まり、卒業までやってくることができました。
ネブラスカ州立大学 | 進路を拓くのに一番必要なのは「英語力」
もし、海外の大学をもう一度選べるとしたら、私はまた中規模の学生数の大学を選ぶと思います。
学費の安さと犯罪率の低さだけを重視し、ネブラスカの大学を選びましたが、都会に行くほど日本人も増えるので、英語力を磨きたいのなら地方を選ぶといいかもしれません。
地方に選ぶほど不便になるけれど
交通や生活は、地方に行くほど「不便になっていく」のは確かです。
でも、最近はネットショッピングで何でも手に入りますし、大都会の日本人コミュニティーにどっぷり浸かってしまっては留学ではなくなってしまうので、気をつけたほうがいいと思います。
繰り返しとなりますが、一番必要なのはやはり英語力。
なにはなくとも英語力を磨こう
度胸やメンタルの強さも大事ですが、TOEFLの点数やGPA、人によってはSATなどのスコアが足りなければ希望の進路を選ぶことができません。
スコアが高ければ高いほど、選べる大学も増えます。英語力をアップするために、とにかく解く、解く、練習、復習に限ります。
入学した後はもっと大変だけど、その価値はある
入学したあとのほうが数百倍難しい課題をこなすことになりますが、その対価に見合う経験がその先にかならずあります。この経験は、日本では絶対できないことだと思っています。
多くの日本人は、謙虚で完璧に遂行しようとするので、自分のことを上手に表現することができませんが、アメリカでは謙虚すぎると社会の隅に置かれてしまう気がします。
チャンスがあれば「私にもできます(多分)!」ぐらいの勢いでアピールしないと、すぐ人の手に回ってしまうのがアメリカ。
それでも、周りに気付かれなくてもコツコツと重ねる努力は、かならず報われると私は信じています。そのプロセスで学び、得られたことは、すべて何かの形で自分に返ってくると思います。
「あのとき頑張ってよかった」と思える日がいつ来るかはわかりませんが、私はアメリカに来て本当によかったと思っています。