「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今号は、「アメリカの留学生政策と大学経営の行方」に注目が集まった一週間でした。トランプ政権によるビザ政策の再提案や、ムーディーズによる大学信用リスクの指摘など、“留学生を取り巻く制度と経済”の動きが連続して報じられたのが印象的です。
一方、日本では留学先の多様化が加速し、アジア圏の台頭と北米離れの傾向が見られました。さらに、オランダのスマホ制限政策の成功や、IELTSの学業成果との関連研究など、教育の質・環境に関するグローバルな話題も多く、保護者にとっても進路設計のヒントが詰まった週となりました。
トランプ政権、学生ビザ有効期間を厳格化する法案成立への動き
2025年6月27日、トランプ政権は留学生ビザの有効期間を、2年間または4年間に厳格化する規則案を提出したと見られています。
まだ詳細は公になっていませんが、2020年に第一次トランプ政権が提出し、最終的にはバイデン政権下によって取り下げられた規則案と同一タイトルであることから、Fragomen移民法律事務所パートナーのBlumberg氏は、今回の規則案は2020年版と多くの類似性を有するだろうと推測しています。
2020年規則案の内容とは、留学生の出身国に応じてビザ期間を2年間または4年間に制限し、さらなる滞在を望む場合はビザの延長を義務付けるというものでした。
仮に、2020年規則案通りに変更された場合、大半の留学生は就学の継続または企業研修に参加するために煩雑な延長手続きをこなす必要性に迫られそうです。
さらに、政府機関による事務手続きの遅延が常態化することで、ゆくゆくは「留学生を米国から遠ざけることになるだろう」と関係者は警告しています。
 副編集長 城
副編集長 城トランプ政権は、留学に関して影響力の強い施策を打ち出す傾向にあります。未確定事項も多いですが、その動向は注視していきましょう
出典リンク
- THE PIE | Trump eyes time limits on US student visas
- Federal Register(連邦官報)| Establishing a Fixed Time Period of Admission and an Extension of Stay Procedure for Nonimmigrant Academic Students, Exchange Visitors, and Representatives of Foreign Information Media
ムーディーズ、米国内大学の信用リスクを警告
トランプ政権による留学生に対する風当たりの強い施策が続くなか、世界的な格付け機関ムーディーズは、留学生比率の高い米国内大学が信用リスクに直面する可能性を6月30日付けの報告書にまとめています。
とくに、信用リスクを指摘されたのは、留学生比率が20%を超えるケースやもともと財務状況に余裕のない教育機関。
留学生入学者数の想定外の減少は、留学生依存度の高い大学ほど授業料収入の減少につながるほか、留学生向け授業料が米国人学生より大幅に高く設定されている構造もそのリスクが顕在化する一因となるようです。
その反面、寄付金や研究活動による収入など授業料以外の財源が豊富な大学であれば、留学生減少による打撃を抑制できる見通しも言及されています。



トランプ政権の留学生に対する一連の施策は、一見するとローカル学生には無関係のように思えますが、学生の構成比率が急変した場合、大学の存続や授業料体系など多方面に影響することが示唆されました
出典リンク
- Inside Higher Ed | Moody’s Warns of Credit Risk for Colleges Reliant on International Enrollment
- Higher Education – US | Decline in international students poses
credit risk from loss in revenue
日本人留学生数コロナ前の約9割に回復、留学先1位は豪
JAOS(一般社団法人海外留学協議会)が発表した統計によると、2024年の日本人留学生数はコロナ禍前の約90%の水準まで回復したことが明らかになりました。
同法人がまとめた2024年日本人留学生数は、前年比4246人増の合計70,253人。
国別の増減を見ると、2023年度調査1位の米国は2000名弱減少して2位へ後退。対照的に、年間留学生数が約4300名も増加したオーストラリアが2024年度の留学先1位となりました。
また、北米やオセアニアがコロナ禍前の水準に回復しきれない一方、マレーシア、シンガポール、台湾などのアジア諸国は既にコロナ禍前を上回る留学生受け入れを記録しており、留学コストの継続的な上昇を背景に、英語留学先としてアジア人気の高まりが顕著に表れているといえるでしょう。



2024年の日本人留学生は北米圏(アメリカ・カナダ)をやや避ける傾向が見られました。その分、他の人気国、オーストラリアと英国の留学生数増加に反映されたとも推察できます
出典リンク
- THE PIE | Japan’s study abroad numbers rebound in 2024
- JAOS(一般社団法人海外留学協議会)| JAOS-Survey-in-2023_-240520.pdf
オランダ、スマホ禁止が学習環境を改善する研究結果
オランダでは、学校教室へのスマートフォン持ち込み禁止を国家規模で推奨していますが、そうした取り組みは学習効果を向上させるという調査結果が明らかになりました。
中等学校から得られた成果によると、「集中しやすくなった」「学習環境が改善した」「成績が向上した」などの回答が多くを占めています。
オランダは2024年1月より、教室内にスマホ持ち込みを禁止するガイドラインを導入。法的な強制力はありませんが、ほとんどの学校がこの国主導のポリシーに従っています。
当初は、生徒に限らず、学校・教師・保護者からも抗議や疑問の声が挙がりましたが、こっそり撮影した写真をオンライン共有する術もなく、直接対話するしかない環境下で過ごすうちに、全体として良好な雰囲気に切り替わったと多くの当事者は好意的に捉えているようです。



スマホがあると大人でも注意散漫になりがち。使用すべきではない時と場所のルール化は有効な解決策になりそうですね
出典リンク
- the Guardian | Smartphone bans in Dutch schools have improved learning, study finds
- KOHNSTAMM INSTITUUT | Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons en andere devices in de klas
IELTSスコアと大学新入生1学期の成績に関連性あり
英語を母国語としない6481名の学生を対象に3年間を費やしたヨーク大学の研究によると、留学生のIELTSスコアと大学在学中のGPA(成績平均点)には、有意な相関関係が成立するそうです。
とくに、IELTSがハイスコアであるほど、入学して最初の一学期は成績優秀であること、長期的に見ても、一時的に成績が落ち込んだ場合のGPA回復力がIELTS高得点者の方が優れていることが明らかにされています。
また、上記の関係性については、同時に研究対象となったTOEFL iBTと比較しても、IELTSがより明確な相関を示したという点も興味深いです。
IELTSに代表される英語能力試験は、大学が入学志願者の学力を見定める指標としての品質が求められますが、本研究の結果を踏まえると学生にとっても教育機関にとってもIELTSは信頼に足る高付加価値な試験と評価できそうです。
👉 IELTSのスコアの仕組み・CEFR換算表・英検やTOEFLの違いについて → IELTS完全ガイド



IELTSは一時の受験対策というより、さらにその先の未来を見据えて学ぶ価値がありそうですね
出典リンク
- IELTS | Independent research links IELTS scores to early academic success for international students
- SAGE Jornal | The relationship between English language proficiency test scores and academic achievement: A longitudinal study of two tests
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
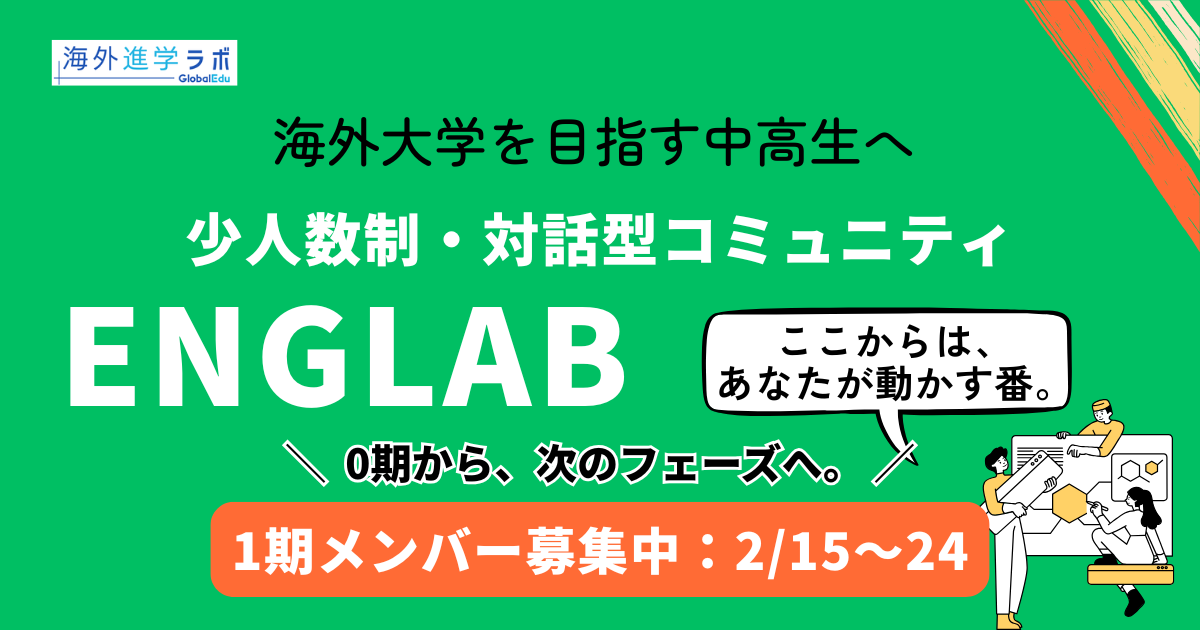


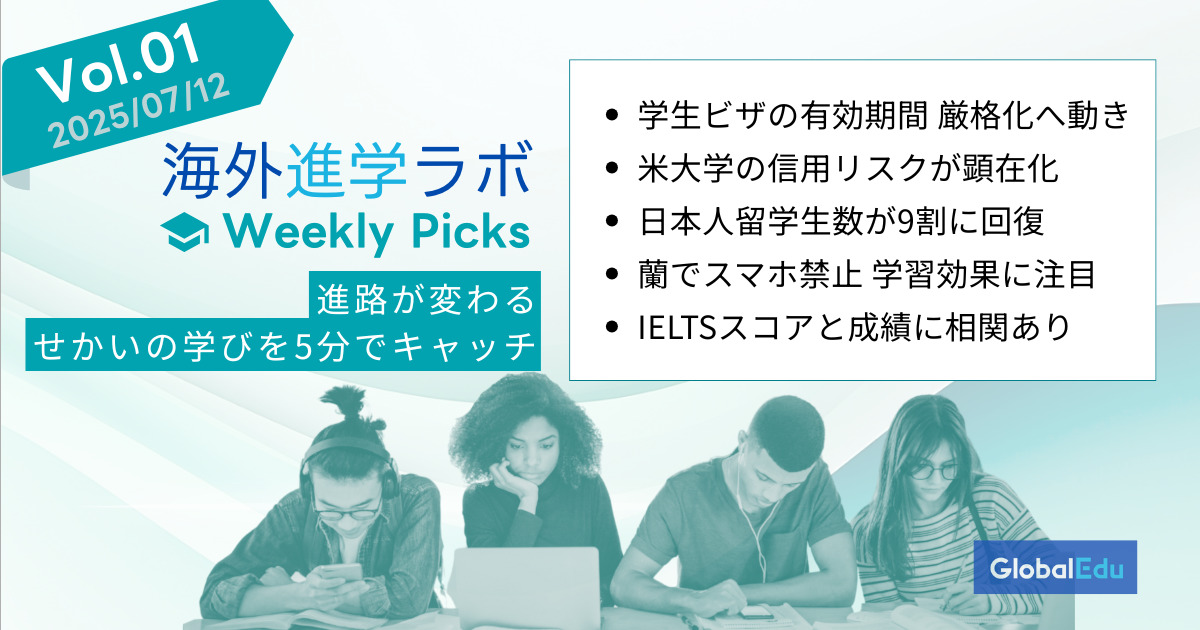


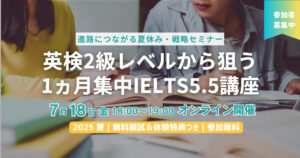

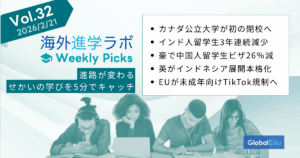
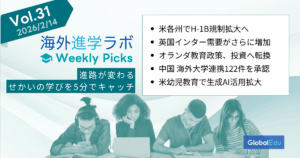


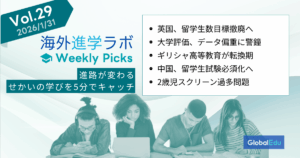
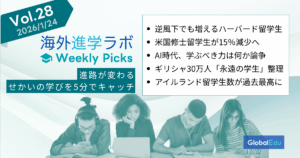
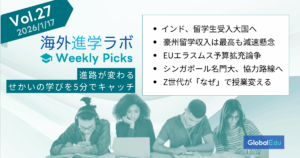
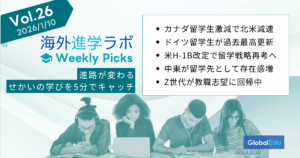
“外的要因”の動きがグローバル進学の現実に
影響を与えることが改めて浮き彫りに。