「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
国際教育の舞台がここ数年で大きく揺れ動いています。大学の海外キャンパスが地政学的な逆風をものともせずに増加している一方で、高等教育が担う「社会的流動性」の役割には限界も見え始めています。
さらに、英語試験のシステムトラブルや米国の学生ビザ政策の急変など、学びの場をめぐる制度的変化・リスクも増加。
保護者や中高生が進路設計で押さえておきたいのは、“選択肢の広がり”だけでなく“制度・仕組みの裏側”にも目を配ること。今号でも、知っておくべき世界の動きと、授業/進路設計に活かせるヒントを5分でキャッチします。
地政学的緊張にも動じず大学分校の拡大トレンド継続、米・英・露が海外展開を先導
国境を越えた教育研究チーム「C-BERT」が実施した調査によると、2025年11月時点の各大学が国外に設置する分校(国際キャンパス)は、85の国と地域を含む384校に達することが明らかになりました。
約2年前の調査から分校数は15%増加しており、地政学的緊張や一部外交面の摩擦を挟みながらも、大学の海外展開トレンドは安定した成長軌道を描いているようです。
大学の海外展開をリードする国は、1位米国(97校)、2位英国(51校)、3位ロシア(43校)など。対して分校を多く受け入れている国は1位中国(50校)、2位アラブ首長国連邦(39校)、3位ウズベキスタン(17校)が続きます。
例えば、ロシアはもともと交流のある旧ソ連諸国をターゲットとして高等教育の海外進出を軌道に乗せたようです。
 副編集長 城
副編集長 城こうしたトレンドは、現地の若者にとって遠方への留学という高コスト要因を避けながら、理想の学位取得につながる選択肢を増やすことになるでしょう
出典リンク
- The Times Higher Education | US, UK and Russia drive growth of branch campuses worldwide
- Cross‑Border Education Research Team(C-BERT)| International Campuses
- ランカスターほか英国大学のインド進出が活発、高等教育需要は上昇の一途
- サウジアラビア、New Haven大学(米)やWollongong大学(豪)が開学予定
- 米軍基地内で学ぶアメリカ大学│横須賀・三沢・横田・岩国・佐世保・沖縄で受講できるメリーランド大学UMUCプログラム
米国科学者、研究予算カットや監視強化により中国への緩やかな流出が進行
CNNの集計では、2024年初頭から今日まで米国内科学者85名が中国の研究機関にフルタイム勤務で加入するなど、米国から中国へ「頭脳の流出」といえる事態が表面化しつつあるようです。
現トランプ政権は、今後さらに研究予算を削減する方向で調整しており、中国人の科学者や学生への監視が厳しくなる状況と合わせて、STEM分野を中心に米国の研究者離れが加速する可能性が指摘されています。
広島大学高等教育研究開発センターの黄教授は、国を越えた共同プログラムや学術交流は続くものの「より選択的かつ政治的な慎重さが垣間見える」と言及。
米国の大学はコンプライアンスやリスク評価を強化する一方、中国の大学は欧州や東南アジア方面との研究パートナーシップ構築へと動いているようです。



気候変動や公衆衛生など政治的にセンシティブではない分野は、従来の共同研究体制が維持されやすいのではないかと考えられています
出典リンク
- The Times Higher Education | Very difficult moment’ prompts flight of US scientists to China
- CSS | In the race to attract the world’s smartest minds, China is gaining on the US
OECD諸国、大学進学キャリア増加に関わらず社会的流動性は不本意な横ばい状態
社会的流動性にフォーカスする慈善団体「The Sutton Trust」が発表した報告書によると、比較的裕福なOECD加盟20ヵ国において、大学進学キャリアの増加が確認されるものの、全体的な社会的流動性はほぼ横ばいに止まっていることが明らかになりました。
2012年~2023年にかけては、非大学卒業生の家庭で育った層の学位取得率は11%上昇し、大学卒業家庭出身者の5%増よりも改善傾向は顕著です。
しかし、非大学卒業生家庭出身の大学キャリアの収入増加率が8%減じたこともあり、トータルな社会的流動性の改善には至らない実態が判明。
また、環境に恵まれた層と比べると、非大学卒業生家庭の学位取得者はトップクラスの収入を得られる可能性は45%も低くなるようです。



同団体の研究責任者は、大学キャリアが万能の解決策とは捉えておらず「より低所得者層を取り込みやすい職業専門的ルートの拡充も重視すべき」と見解を述べています
出典リンク
- The Times Higher Education | Social mobility ‘flatlining’ despite increased HE participation
- Sutton Trust | Degrees of Difference
第二次トランプ政権、累計8000人の学生ビザを取消、事案次第で国務省による即時決定
米国務省はPie Newsの取材に対し、第二次トランプ政権が発足した1月20日以降、約8000件の学生ビザを取り消したことを明らかにしました。
学生ビザを含む非移民ビザ取消件数は、2024年比の2倍以上を記録し、現政権による積極的なビザ取り締まりを裏付ける結果が示されています。
取消理由は、暴行・窃盗・飲酒運転がほぼ半数を占めており、「超過滞在、犯罪行為および公共の安全への脅威に潜在的に結びつく兆候があればビザは即時取消の対象となる」と国務省広報は言及しています。
大学連盟の責任者はこうした厳しい監視が常態化したことで、「キャンパス内で学生が自由に意見交換できる気風を削ぎ、留学生や学者を孤立させた」と主張。同様の状況が続けば、海外学生が米国留学を敬遠する傾向に拍車がかかるだろうと懸念を表明しています。



直近1年の米国ビザ政策が教育環境に与えた変化は、米国外の高等教育事情にも一定の影響を及ぼしそうです
出典リンク
- THE PIE | Trump administration has revoked 8,000 student visas
- Reuters | Trump administration revoked more than 6,000 student visas, State Dept says
IELTS、試験結果の一部に技術トラブルによるスコア間違い発覚、修正スコアの提供と再受験の機会も
IELTS運営団体は、2023年8月~2025年9月にかけて一部の試験結果に技術的トラブルによる計算ミスが起きていたことを明らかにし、影響を受けた受験生には修正スコアがEメールにて通知されたようです。
運営団体によると、エラーが生じていたのは一部テストのリスニングとリーディングパート。全体の99%超には影響がないようですが、2025年9月以前に受験した場合は念のためEメールボックスを確認しておくといいでしょう。また、対象受験生には払い戻しと無料再受験の機会も用意されます。
今後、波紋を呼びそうなのは、スコアエラーの影響で、大学入試に成功できなかった、進路変更を余儀なくされたであろう受験者の存在です。
試験業界の評論家は「学術と移民の門番のような資格試験に誤りがあると、その影響は深刻かつ広範なものになる」と不安視しています。



ハノイ在住受験者の事例によると、総合スコア7.0が7.5に修正されたそうです
出典リンク
- THE PIE | IELTS apologises after technical issue leads to score changes
- IELTS Result Support
- VnExpress International | IELTS candidates see scores changed months later as test maker admits technical error
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
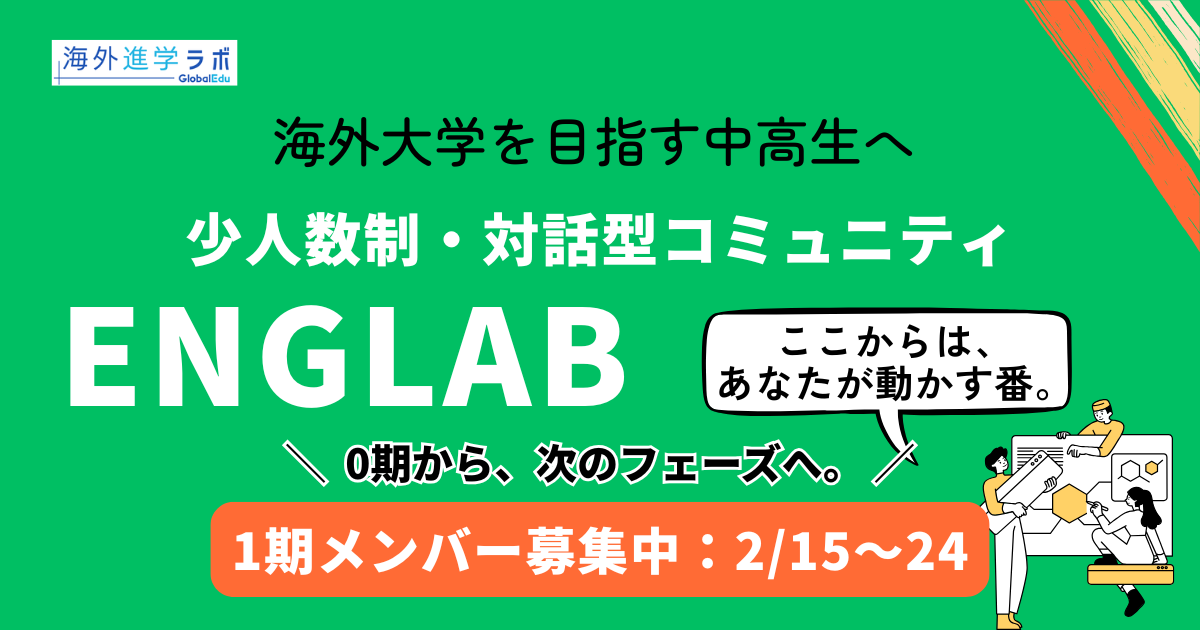


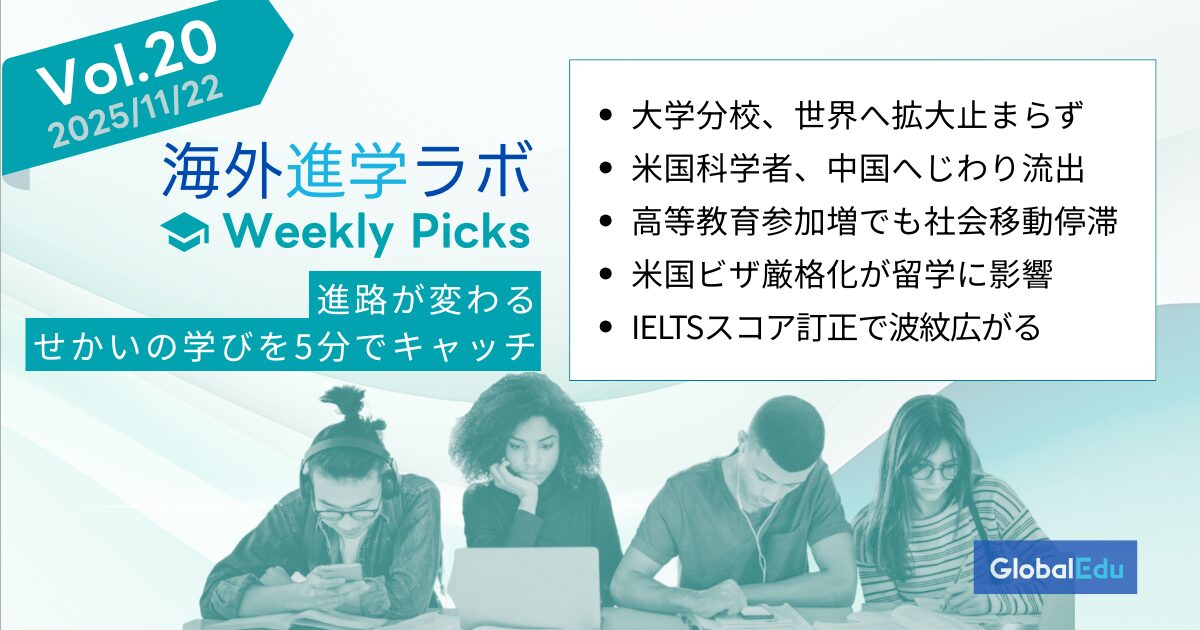





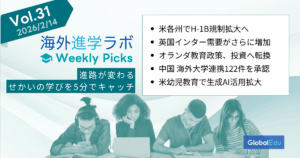

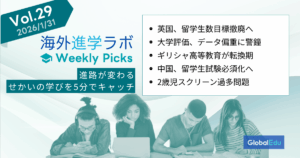
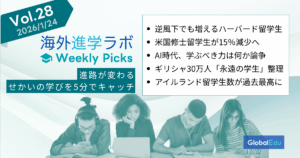
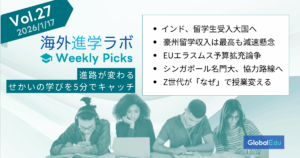
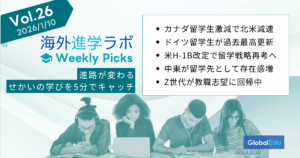

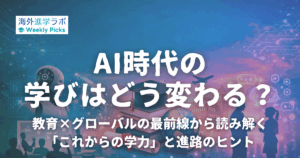
いま、進路をめぐる“前提”そのものが
少しずつ形を変え始めています