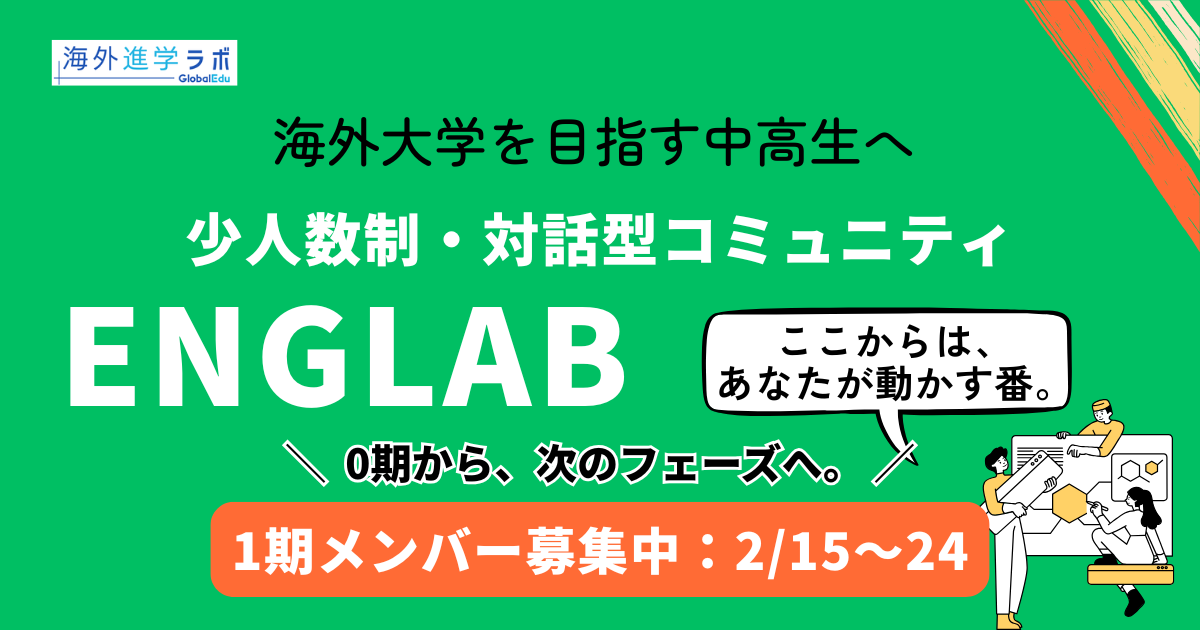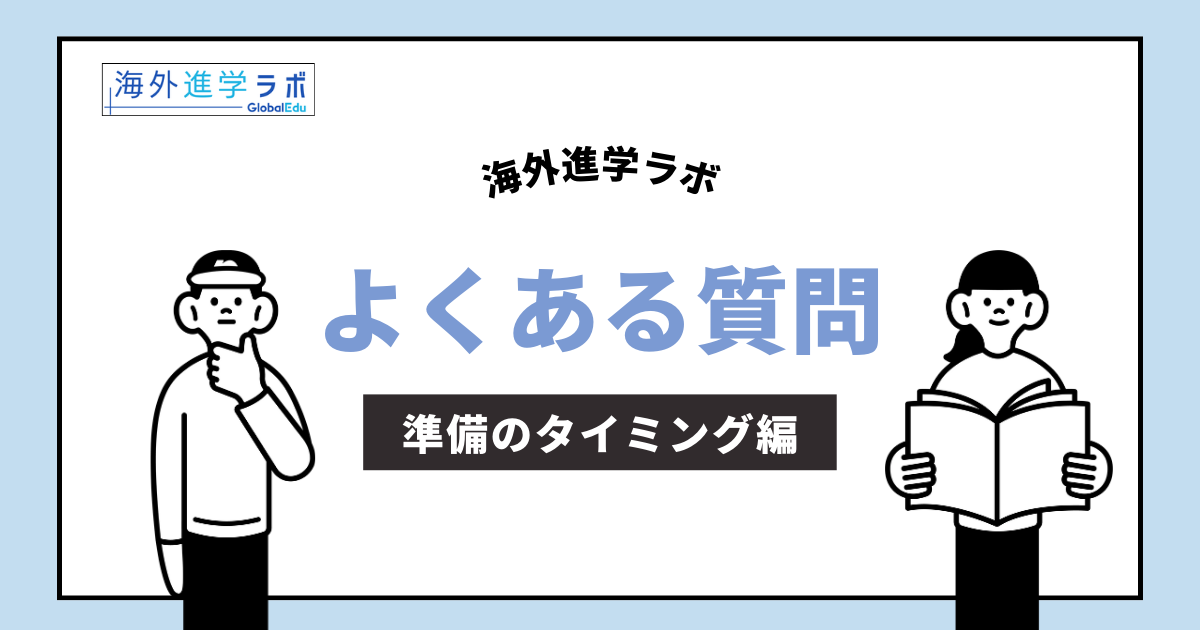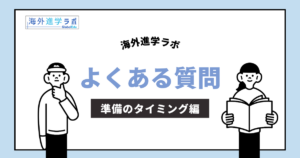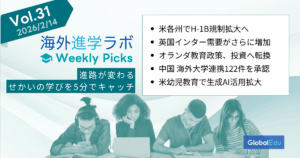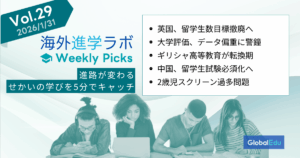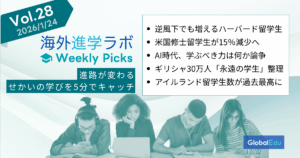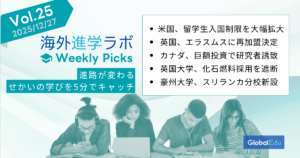海外進学Q&A|準備のタイミング編
海外進学っていつから準備を始めるべき?
目安としては中学3年〜高校1年のうちに情報収集と進学計画づくりに着手し、高1のうちに基礎的な英語力や探究・課外活動に取り組めると理想的です。
出願は高3の秋〜冬になることが多いため、そこから逆算すると「志望校の絞り込み」「出願書類の準備」「英語スコアの取得」などに約1〜2年の準備期間が必要です。
 海外進学ラボ
海外進学ラボとはいえ、遅すぎることはありません。大切なのは“今の自分からできること”を明確にし、一歩ずつ進めることです
👇 関連情報をチェック
海外大学の情報収集はどこから?
まずは各大学の公式サイトをチェックし、出願条件や学部情報を確認するのが基本です。
そのうえで、信頼できる情報発信者(教育メディア、進学支援団体、留学経験者など)を見つけて、リアルな声や最新動向を把握していきましょう。説明会やWebセミナー、パンフレット請求も有効です。
小学生のうちからできることは?
小学生の時期は、海外進学を“決める”というよりも、“視野を広げる”ことに重点を置きましょう。
英語学習に加えて、他国の文化や社会問題に触れたり、多様な視点を育むような読書・体験がとても大切です。
なかには親子留学やサマースクールに参加して、「自分もこうなりたい」という憧れを持つ子もいます。



進路として意識しすぎなくても、“学ぶって面白い”を育てることが最大の準備です
高校からでも間に合う?
はい、十分間に合います。高校1〜2年生から本格的に進路を考え始める人も多くいます。
とくに英語力(TOEFL・英検)や活動実績(ボランティア・探究学習など)の蓄積に集中すれば、高2の後半には書類づくりに着手できます。
ただし、情報の断片を集めるだけでは時間が足りなくなる可能性もあるため、信頼できる相談先やロードマップを活用して、進路を“逆算して組み立てる”視点が重要になります。
中3から準備するなら何をすべき?
中3は「将来の可能性を広げる基盤づくり」の時期。
英語に力を入れ始めることはもちろん、探究やボランティアなど“自分の興味関心を広げる経験”を積んでおくと、高校に入ってからの書類作成や進路計画がスムーズになります。
また、進学ルートを知る、英検などの資格取得に挑戦する、情報源を選ぶなど、「家族で進路を意識するスタート年」としても最適。夏の短期留学なども効果的です。
留学希望でも高校選びは重要?
はい。海外進学を視野に入れるなら、探究活動・英語教育・海外進学サポートがある高校はアドバンテージになります。
ただし、どんな高校にいても、自己主導で情報を集め、行動できる人であれば進学は可能です。学校に頼り切らず、自分で進路設計できる姿勢が重要です。
高1で海外進学に切り替えるのは遅い?
決して遅くありませんが、戦略的な準備が必要です。
高1の段階で進路を海外にシフトするなら、英語力の強化(英検準1級、TOEFLなど)をすぐにスタートしましょう。
同時に、課外活動や探究学習、エッセイに活かせる経験も積んでいくと、出願時に“自分らしいストーリー”が語れるようになります。
志望校や制度によって求められる要素が異なるため、早めに情報収集し、逆算した計画を立てることがカギになります。
高校1年生でやっておくと得なことは?
英語力強化、興味関心を広げる探究・課外活動、情報収集の3点が柱になります。
また、ポートフォリオや自己分析ワークを通じて“自分を言語化する力”を育てておくと、エッセイや面接の準備がスムーズになります。学年が上がる前の春〜夏が行動のチャンスです。
高2で準備スタートするなら何を優先?
最優先は英語資格の取得とエッセイ準備です。高2のうちにTOEFLやIELTSの目標スコアに近づけておくことで、出願に余裕が生まれます。
あわせて、探究活動や課外経験の振り返りと整理も進めましょう。志望校選びや進路の方向性がまだ不明瞭でも、“自分らしい材料”を集めておくことで後から選択の幅が広がります。
海外進学と国内併願、どっちを先に考える?
理想は“どちらも並行して考える”ことです。英語資格やエッセイ準備など、海外進学と国内の推薦・総合型入試には共通項が多いため、準備の重なりを活かせます。



志望度や進学意欲が定まっていない場合でも、海外を視野に入れて動くことで、結果的に国内選択にも納得感が生まれやすくなります
総合型入試と同時並行できるの?
できます。エッセイや課外活動の準備は共通点が多く、とくに自己PRや志望理由の明確化は両方に活かせます。
ただし、出願スケジュールや必要書類の形式が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。カレンダーを作って締切管理するのが効果的です。
留学説明会はどの時期に行くべき?
中3〜高2の間に1度は参加しておくのがおすすめです。
とくに、高1〜高2前半は進路の選択肢を広げる時期。各大学や各国の公的教育機関が開催する説明会で、リアルな入試情報や在学生の話を聞くことで、自分に合った進路を考えるヒントになります。
秋〜冬にも海外大学の出願時期に合わせて多くの説明会が開催されるため、そのタイミングを狙うと良いでしょう。
👇 関連情報をチェック
英語が苦手でも、いまから間に合う?
英語力は「早く始めた方が有利」ではありますが、途中からでも追いつける力です。
大切なのは、受験用の知識ではなく「英語で考え、伝える」力。これはTOEFLや英検準1級のような試験で問われる力でもあります。
たとえば、毎日英語で日記をつける、英語記事を読んで意見を考えるなど、地道な積み上げが大きな差になります。



間に合うかよりも、「いつ本気になるか」が大事です
いつまでに英語資格を取ればいい?
出願時に間に合うよう、高2の秋までにスコアがそろっていると安心です。
大学や国によっては高3の秋〜冬の出願締切に間に合わせればOKですが、スコアが足りずに再受験となるとスケジュール的に厳しくなります。
とくにTOEFLやIELTSは初回で目標スコアに届かないことも多いため、余裕をもって早めに受験スケジュールを組みましょう。
英検を取るならどのタイミング?
高1〜高2の間に準1級レベルを目指すのが理想です。海外大学の出願では英検準1級レベルから認められるケースが多く、国内推薦でも評価されやすい資格です。
出願時期に余裕をもって臨めるよう、早めの受験計画を立て、リスニングや英作文の強化を並行して行いましょう。
TOEFL対策は何ヵ月前から?
個人差はありますが、初回受験の半年前〜3ヵ月前には本格的に対策を始めるのがおすすめです。
スピーキングとライティングは伸ばすのに時間がかかるため、早期スタートが有利です。
また、TOEFL特有の出題形式にも慣れる必要があるので、模試や過去問を使った実践トレーニングが効果的です。
夏休みにできることは?
夏は“経験を積んで、深める”絶好のタイミングです。短期留学やボランティア、探究活動、課題研究など、自分の興味と社会との接点をつくるような体験が望ましいです。
これらは出願時のポートフォリオやエッセイに大きく影響します。



また、英語学習に集中して取り組む時間も確保しやすいため、英検やTOEFLのスコアアップにもつなげやすいです
春休みにやるといいことは?
進路についての親子対話、探究活動の企画、英語力の集中特訓などに最適な時期です。また、海外の大学やプログラムの資料を取り寄せたり、志望校をリストアップするなど“設計”に向けた準備が進みます。
春は年間計画を立て直すチャンスでもあります。
ボランティア活動はいつから始める?
できるだけ早い段階、高1前後がおすすめです。無理なく継続できる活動を選び、「なぜその活動を選んだのか」「どんな学びがあったのか」を振り返るプロセスが重要になります。
評価されるのは活動の規模よりも“自分らしさ”と“内省の深さ”です。
学校での進路相談では何を聞けばいい?
「海外進学を考えているが、具体的にどんなサポートが受けられるか」「どの教員に相談すればよいか」「過去に海外進学した先輩はいるか」などがいい質問です。



先生によって知識の差があることもあるので、自分でも情報を集めつつ、必要に応じて外部相談も活用すると安心です
IBやAPを取っていないと不利?
IB(国際バカロレア)やAP(アドバンスト・プレイスメント)などを取っていないからといって、大幅に不利になるわけではありません。
各大学には一般的なカリキュラム(日本の高校など)から出願するためのルートが用意されています。



重要なのは、どのカリキュラムであっても“その中でどのように学び、成長してきたか”を明確に伝えることです
留学エージェントを使う時期は?
本格的に出願準備を始める高2後半〜高3前半に利用するケースが多いですが、情報収集の段階から無料カウンセリングなどを活用するのもおすすめです。
複数のエージェントに相談し、自分の目的や志望校に合った支援が受けられるかを見極めるといいでしょう。
出願書類はいつから準備する?
高2の秋ごろにはエッセイや推薦書の準備に着手するのが理想です。
志望校の要件を確認したうえで、自己PR文やパーソナルステートメントを構成するための素材(体験・活動・考察)を洗い出しておくといいでしょう。下書きを早めに始めることで、見直しや添削の時間が確保できます。
留学準備を途中でやめる人の理由は?
費用面や語学スコアの壁、家庭の事情、または“やっぱり国内の方が合っていると感じた”という理由が多いです。
ただし、準備の過程で得た英語力や思考力、エッセイ経験などは国内進学にも活きる財産になります。



進路変更は失敗ではなく、必要なプロセスの一部ととらえることが大切です
海外進学に関するイベント・資料・Q&A更新情報をLINEでお届けします。



受験準備のヒントや、保護者向けの特典情報もいち早くお届けします