「海外進学ラボ Weekly Picks」は、グローバル進学に関心のある中高生・保護者向けに、世界の教育ニュースを厳選してお届けしています。進路のヒントが“5分”で見つかる週刊特集です。
今号でも、教育をめぐる世界の最新動向を一気にチェックします。
中国はSTEM人材獲得に向けた新ビザを導入し、グローバル人材競争を加速。マレーシアは留学生授業料に6%課税を導入するも、影響は限定的と見られています。
英国では留学生が地域経済に与える多大な効果が示され、卒業生の長期的な英国教育への肯定感も明らかに。米国ではAI需要増大でデータセンター拡張が進み、教育現場周辺への環境影響が懸念される局面に。
進路を考えるとき、その背景には常に国際教育をめぐる政策や社会の動きがあります。
中国、グローバル人材戦略の一環でKビザという新ビザを導入
中国政府は、国内外の一流教育機関でSTEM学位を取得した若者やSTEM分野の若手教育研究者を対象とした新就労ビザ、「Kビザ」の2025年10月1日からの導入を発表。
Cina Education International創設者のCharles Sun氏は、「世界の優秀且つ聡明な人材を積極的に誘致したい中国の強い意欲の表れ」と捉えています。
このKビザでは、申請者の年齢やキャリアが要件となる一方で、企業側のサポートを必要としない合理化された申請プロセスを採用。
また、Kビザホルダーは入国回数や滞在期間が優遇されるほか、家族ごと中国に移住しやすい規定も適用されるようです。
 副編集長 城
副編集長 城Studyportalsのデータによると、中国では2024年比でAI学位への関心が88%も増加しており、こうした背景に支えられ、KビザがAI人材獲得競争を優位に運ぶ決め手になるかもしれません
出典リンク
- THE PIE | What does the K visa mean for China’s search for global talent?
- 中国政府の英語公式サイト | China to launch K visa for young science, technology talents
- Studyportals | China launches new STEM talent visa as US loses ground in global AI student demand
マレーシア私学、留学生授業料に6%課税決定も負の影響は限定的か
マレーシアは2025年7月1日より、小学校~大学まで私立教育機関で学ぶ留学生の授業料に対して6%の売上・サービス税(SST)を課していますが、タスマニア大学のJames Chinアジア研究教授は、この新課税による影響は限定的にとどまるという見解を明らかにしました。
Chin教授は6%課税が留学需要にあまり影響しない理由として、他国の教育機関が設ける上乗せ手数料ほど高額ではないこと、教育機関によっては留学生に係る税金分を学校側で負担している点などを挙げています。
その一方、25万人の留学生受け入れを目指す国家主導の教育戦略(MEDP)にそぐわないという指摘があるほか、短期的な問題は生じないとしても、他国との教育パートナーシップ活動やコスト変動に敏感な地域からの留学生の動向に一定の影響が生じるという懸念も寄せられています。



留学の選択肢が多様化し、一カ国で費用負担が増減するたびに常に他国の教育機関と天秤にかけられる状況が続きそうです
出典リンク
- THE Times Higher Education | New tax on fees ‘unlikely to dent Malaysia’s growth ambitions’
- The Economic Times | Malaysia to charge 6% tax on private education for international students from July 2025
英国超党派団体、留学生がもたらす多大な地域経済効果を最新調査で強調
英国の超党派議員グループ「APPG for International Students」は、最新の調査報告に基づき、英国における留学生がそれぞれの地域社会に多大な経済的恩恵をもたらしている実情を強調しました。
最新調査によると、大学の収入100万ポンドごとに多分野の雇用を伴う230万~250万ポンドの経済効果が生じ、英国全体への貢献額は年間419億ポンドに達するそうです。また、英国内100以上の選挙区では高等教育がトップ3の輸出産業として地域社会に貢献しており、国際教育が分野横断的な価値を有していることが示されました。
こうした調査結果を踏まえ、APPGは「国際教育を各地域の特色に沿った開発戦略に組み込むこと」、「地元雇用主のニーズも考慮し、Graduate Route(卒業後の滞在可能期間)は短縮せず2年のまま維持すること」などを英国政府へ提言しています。



今も変わらず世界的な注目度が高い英国の国際教育、どの程度の恩恵が地域社会に波及するかは今後の制度設計によっても左右されそうです
出典リンク
- THE PIE | Economic case for international students in UK “overwhelming”
- International Students | The APPG Launches Inquiry Report on The UK’s Global Edge: Regional Impact and the Future of International students
英国大学を卒業した留学生、数十年後も英国への肯定感が持続するという調査結果
British Councilの調査によると、英国の大学を卒業した元留学生のほとんどが、英国を魅力的な留学先や旅行先と認識し、その8割以上が周囲に英国留学を継続的に勧めていることが明らかになりました。
この国際調査は、123カ国3094名の英国大学同窓生を対象として実施。卒業年から25年以上が経過した同窓生に限っても、78.4%が英国における就学を推奨しており、英国留学へのポジティブな印象は卒業後数十年が過ぎても変わりない実態が浮かび上がりました。
British Councilの教育ディレクターは、「留学で育んだ永続的なネットワークを通じて、英国の教育・観光・文化的価値を広めてくれるのは、本物の親善大使であるかのようです。」と言及。世界的な同窓生ネットワークが、英国高等教育の権威と信頼性を陰ながら力強く支える役目を果たしているようです。



同調査では、EU圏の同窓生は英国教育の推奨レベルが64.8%にとどまり、むしろEU圏外の出身者が英国教育への肯定感が強い傾向を示しています
出典リンク
- THE Times Higher Education |International students ‘keep promoting UK decades after study’
- British Council | Alumni Voices: UK graduates, global influence(2025年)
急拡大する米国内AI関連インフラ、学校近隣エリアへの進出が不安視される局面に
今後、教育現場においてもより重要な役割が求められそうな生成AI。米国では、そうしたAIの需要が大きくなるにつれて、AIインフラ、すなわちデータセンターの拡充が避けられない状況に直面しています。
同時に、AIを支える大規模建造物が、学校の近隣エリアに建設される可能性も生じており、環境面への悪影響を不安視する声も上がっています。実際、データセンターは大量の熱を放出する一方で大量の飲料水を必要とするため、生活環境や地元の貯水池に問題が生じるリスクは否めません。
その対策として、ハーバード大学エンジニアリングスクールの研究グループは、データセンターの持続可能な運営について研究を進めており、その成果物の1つとして環境保全やエネルギー生成効率の面でより適切な拠点選びに役立つデジタルツールを開発しています。



米国より国土が狭い日本も、先端技術を駆使して見切り発車にならない立地選定を実践したいですね
出典リンク
- EdSurge | As Data Centers Expand, Should That Concern Schools?
- ハーバード大学工学・応用科学部(SEAS)|A sustainable future for data centers
【教育関係者のみなさまへ】
世界の変化を、教育のチャンスに変えるために。
Weekly Picks では、教育政策、評価制度、AI、留学生市場など、世界の学びをめぐる変化を「ニュース」ではなく、教育の前提条件として整理しています。
こうした知見を、学校運営や教育設計、意思決定にどのように活かせるのかを考えたい方は、こちらのページもご覧ください。
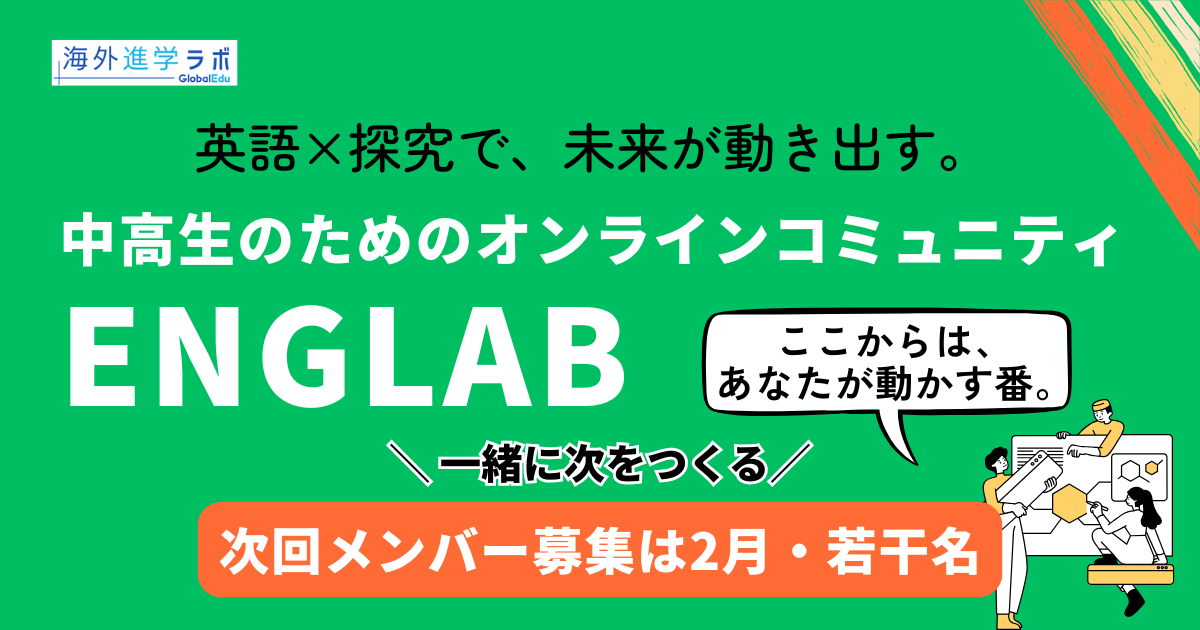


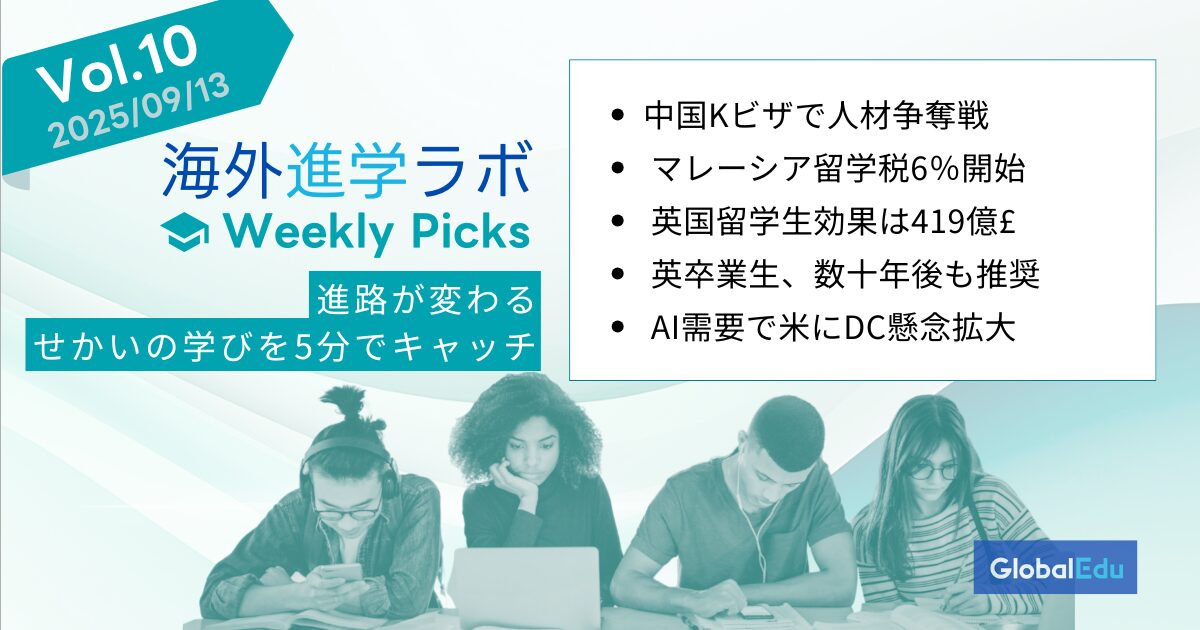





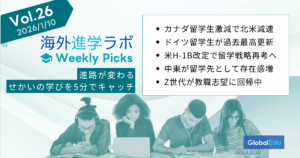

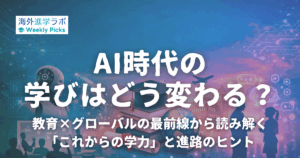

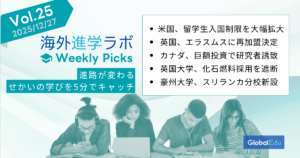
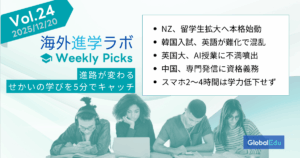
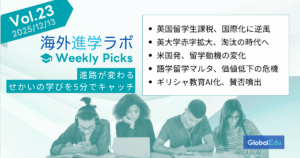
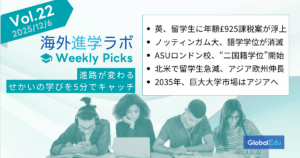
進学の「選び方」そのものが
静かに塗り替わりつつあります