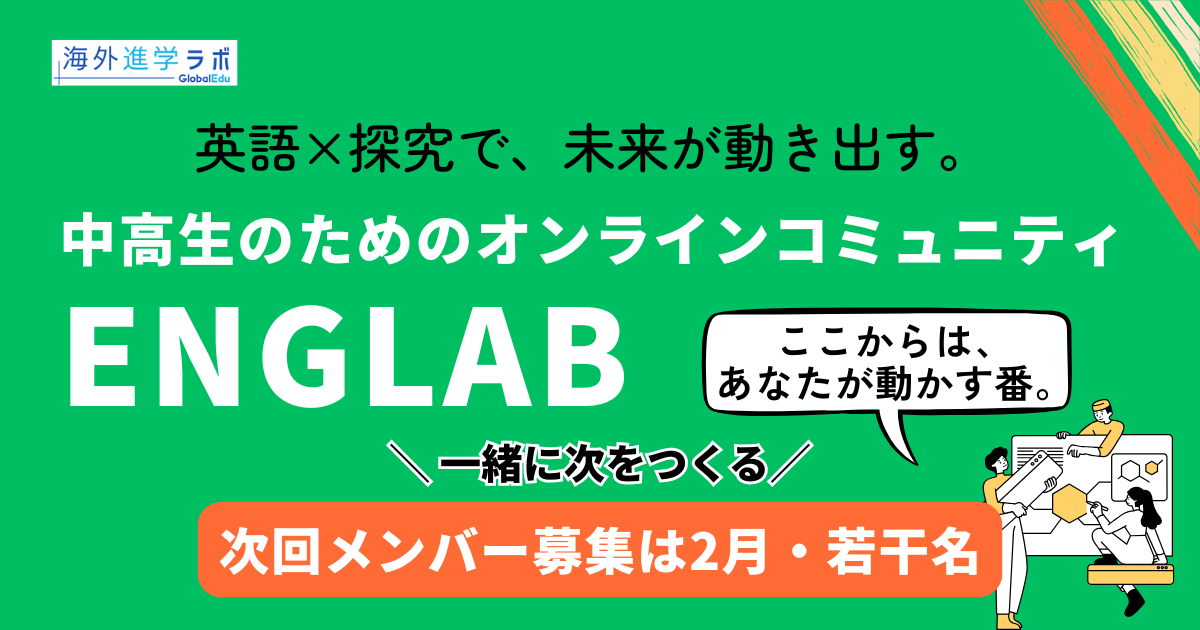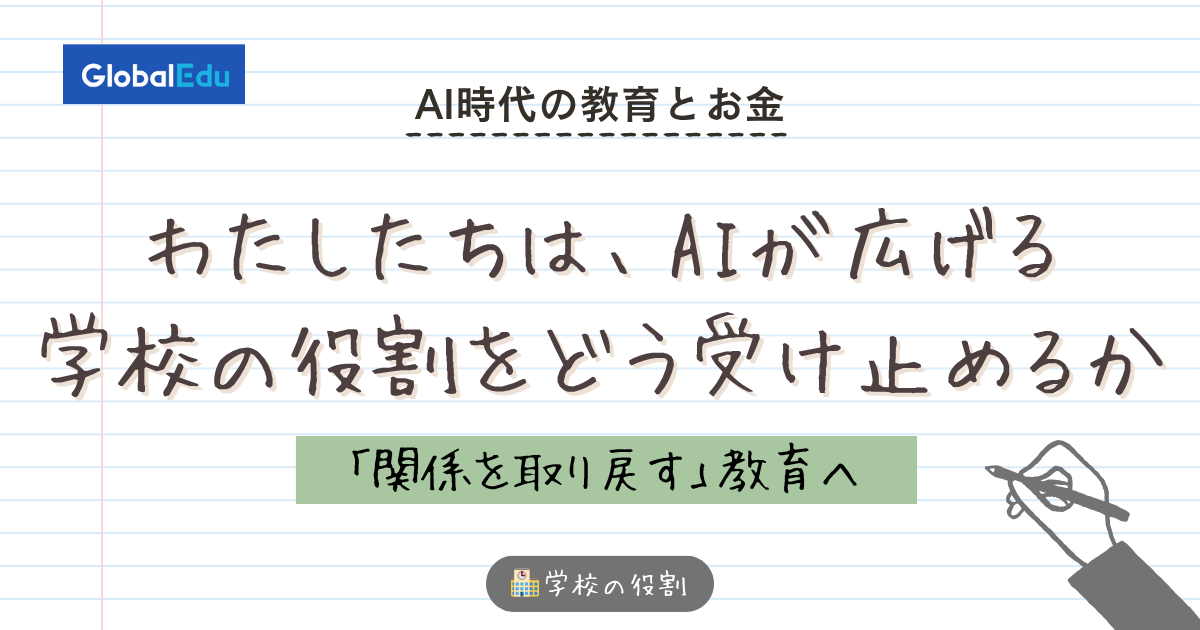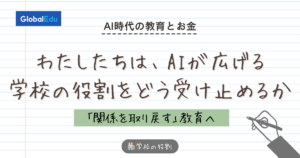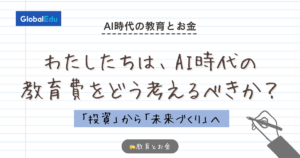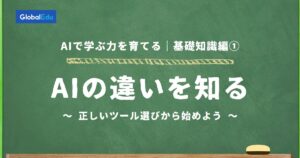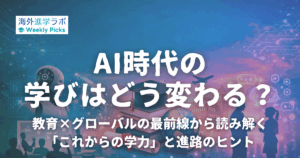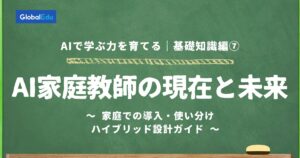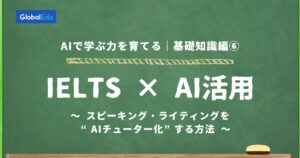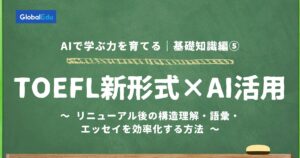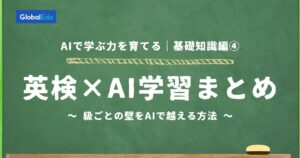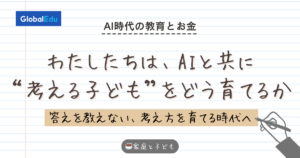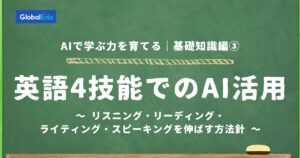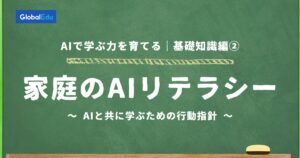AIが学校に入ってきた
数年前までは「AI教育」といえば、どこか遠い話でした。でも今、教室の中にはすでにAIが静かに入り始めています。
授業準備の支援、レポート添削、学習記録の分析。
AIは確実に、先生たちの働き方を変えつつあります。
けれどその変化を前に、わたしたちはこんな問いを抱きます。
 .
.学校は、何を“AIに任せ”、何を“人が担う”べきなのか?



AIと共に学ぶ子どもたちに、わたしたちは何を伝えられるのか?
AIの導入を「効率化の波」として受け止めるだけでは、教育の本質を見失ってしまうかもしれません。
いまこそ、わたしたちは「AIと共にある学校の意味」を、もう一度見つめ直す時なのです。
先生が取り戻す「人の時間」
AIの導入で最も変わったのは、先生たちの時間の使い方です。
成績処理、教材作成、通知表のコメント──。
これまで多くの時間を奪ってきた“事務の山”を、AIが少しずつ引き受けています。
すると不思議なことが起こります。
「授業以外」に追われていた先生が、再び「子どもと向き合う時間」を取り戻していくのです。
子どものつぶやきに立ち止まる余裕。
放課後に残って話を聞く余白。
AIが整えたのは、“効率”ではなく“余白”。
この余白こそが、教育の呼吸を取り戻す第一歩です。
わたしたちは、AIを「評価のため」に使っていないか
AIの分析機能はすばらしいです。
学習履歴をもとに、一人ひとりの得意や苦手を見える化できる。
でも、その便利さの裏で、わたしたちはもう一つの問いを持つべきです。
子どもを“データ”として見る時間が増えていないだろうか?
AIが出すグラフやスコアは客観的ですが、その子の「迷い」「悩み」「変わろうとする瞬間」は映し出せません。
AIに数字を任せるほど、先生は「物語」を見る目を磨く必要があります。
AIの分析を使いながらも、「なぜこうなったか」「どう感じているか」を聞けるのは人だけです。
教育とは、結果の管理ではなく、変化の観察。
AIができないのは、まさにその“人の観察”なのです。
教室が「共創の場」に変わる
AIを取り入れた学校では、先生が“教える人”から“学びを設計する人”へと変わりつつあります。
子どもたちはAIを使って情報を整理し、意見をまとめ、発表を準備します。
先生は、AIが出した答えを“正しいかどうか”で判断するのではなく、
「なぜそう考えたのか?」
「その意見を現実にどう活かせるか?」
を問う存在になります。
AIが生徒に「正解」を提示するなら、先生はその正解を「問い」に変える人。
それが、AI時代における“新しい教える力”です。
学びの“個別化”と“孤立化”のあいだで
AIの力で、一人ひとりに合った学習内容を提案できるようになりました。
でも、気をつけたいのは“個別化”が“孤立化”にならないこと。
AIがカスタマイズした教材を与え、生徒が黙々と画面に向かうだけの授業になっていないでしょうか。
わたしたちが目指すべきは、「一人で進む学び」ではなく、「一人ひとりが持ち寄る学び」です。
AIが提供する多様な視点を、教室の中で共有し、「人と人がつながるための道具」として活かしていく。
その橋渡しをするのが、先生であり、学校という場の役割です。
わたしたちは、家庭と学校の境界をどう越えていくか
AIによって、家庭と学校の距離も変わり始めています。
学習履歴やレポート進捗がクラウド上で共有され、親もリアルタイムで学びを見守れるようになりました。
便利な一方で、ここにも問いがあります。
「見守る」と「管理する」の境界は、どこにあるのか?
AIによって情報が“透明化”される時代だからこそ、
わたしたちは「子どもの自主性」と「親の関わり方」のバランスをもう一度考え直す必要があります。
家庭が学校に近づくのではなく、学校と家庭が“学びのパートナー”として並び立つ。
AIは、その関係を再構築するためのツールにもなれるのです。
教育は「人を磨く時間」に戻っていく
AIが進化するほど、教育の価値はシンプルになります。
知識を“与える”ことより、人と人が“向き合う”こと。
AIは先生の仕事を奪うのではなく、先生が本来の仕事――“人を育てる”という本質に戻る手助けをしています。
子どもを理解することに時間を使う。
教えるより、考えさせる。
答えを出すより、問いを育てる。
わたしたちがAIと共に進む教育は、決して“機械的な学び”ではありません。
むしろ、人の温度を取り戻すためのプロセスなのです。
AIが生むのは「新しい教育の余白」
AIが変えるのは、教育の形だけではありません。
わたしたちが「なぜ教えるのか」「何を育てたいのか」という、教育の哲学そのものです。
AIが整えるのは、情報と効率。
わたしたちが整えるのは、関係と意味。
教育とは、知識を詰め込むことではなく、人が人を見つめる余白を持つこと。
その余白こそが、AI時代における“人間らしい学校”の姿です。