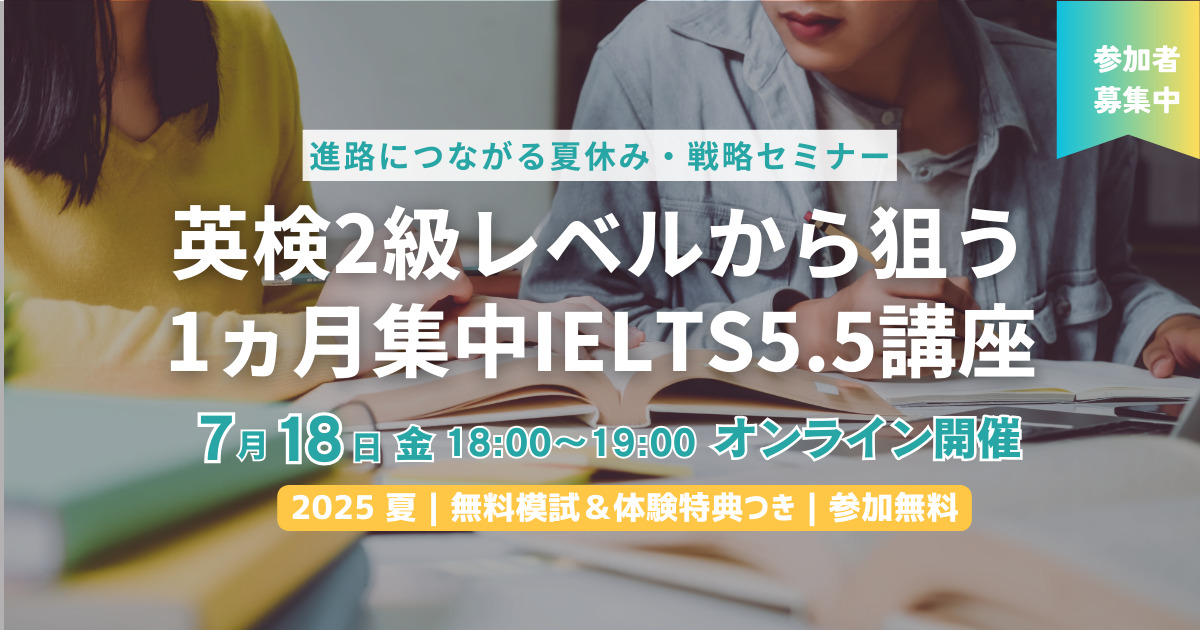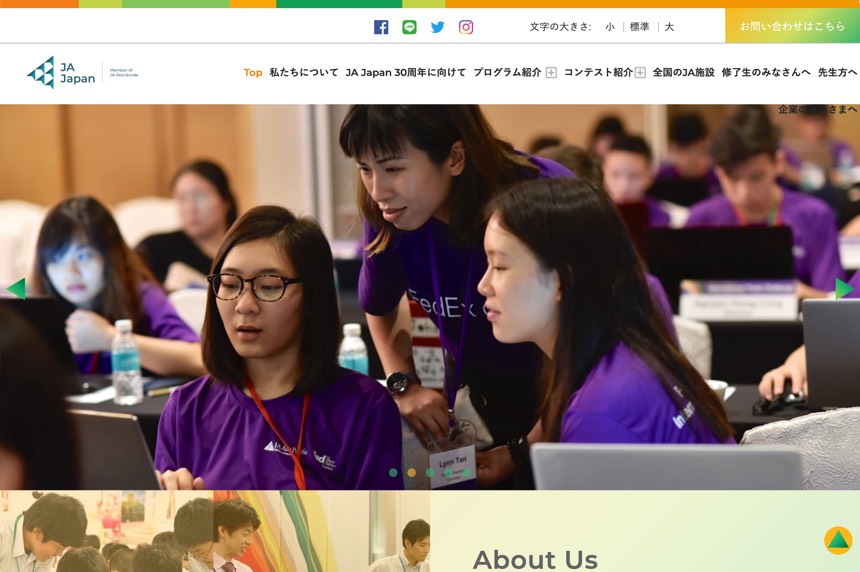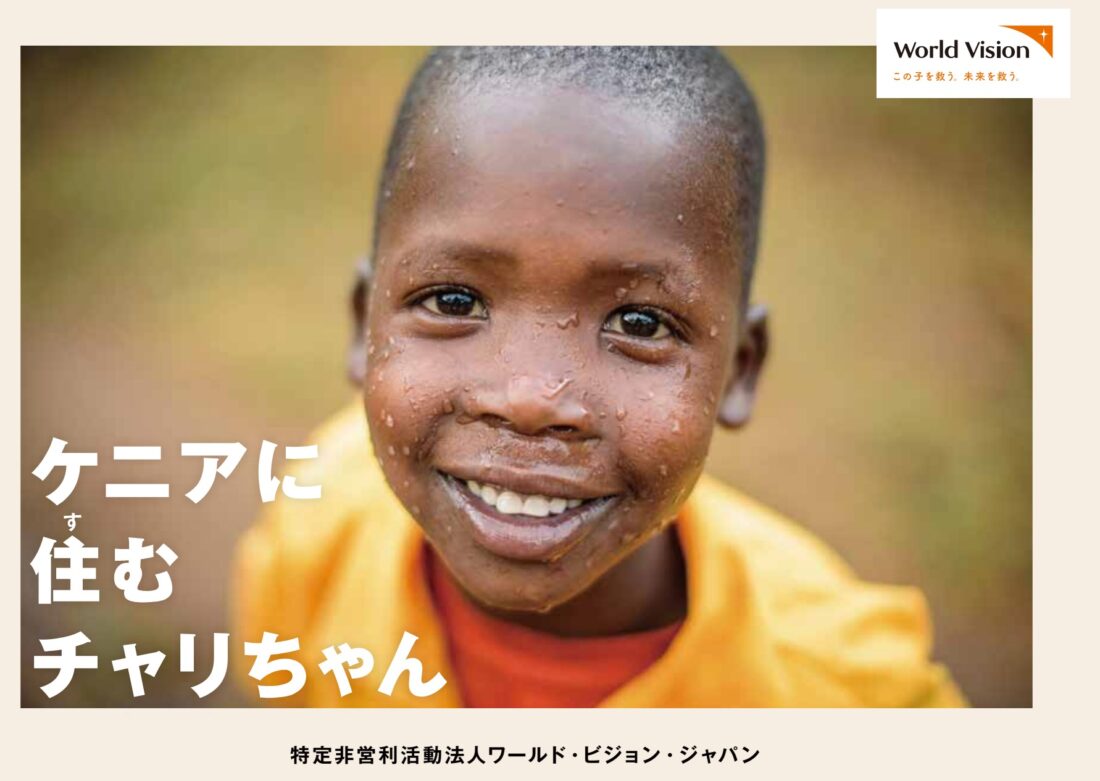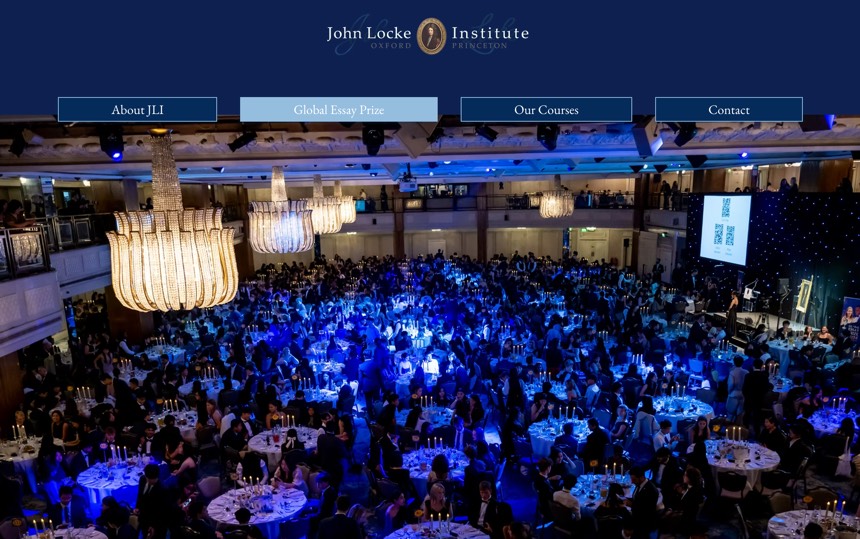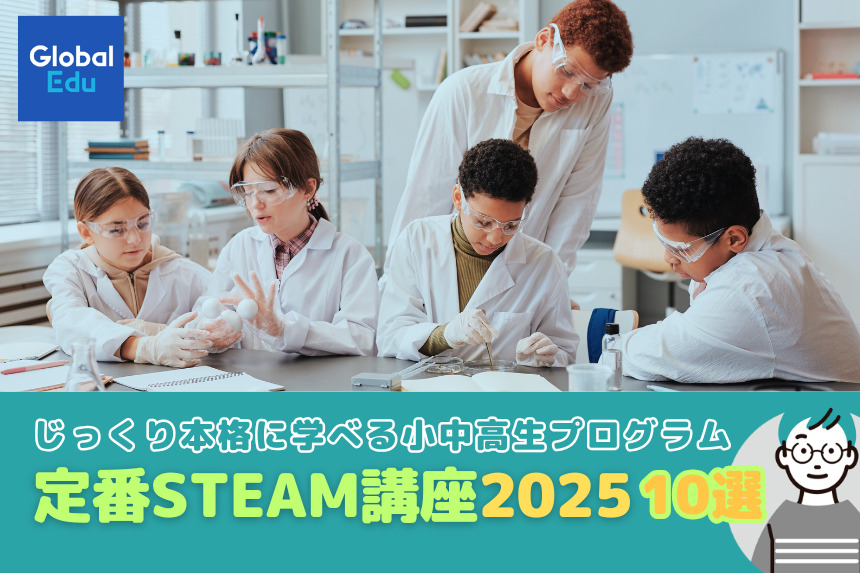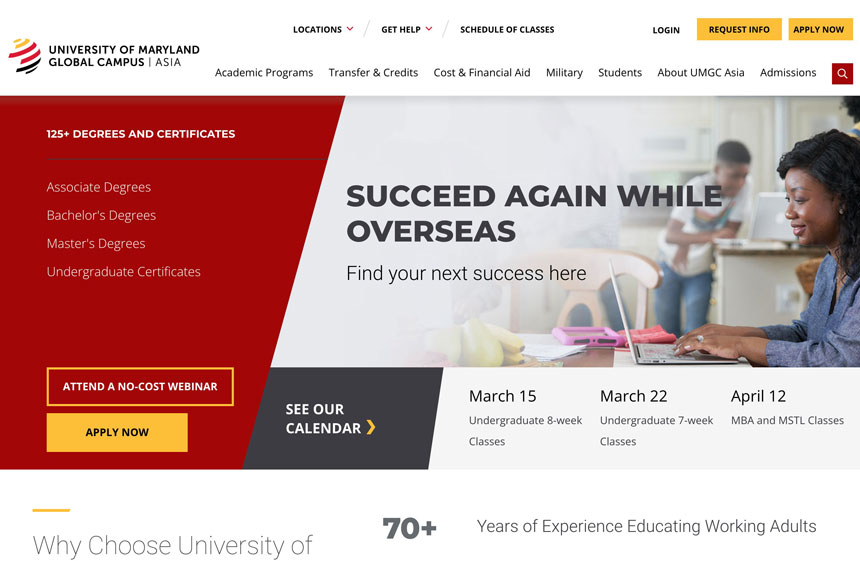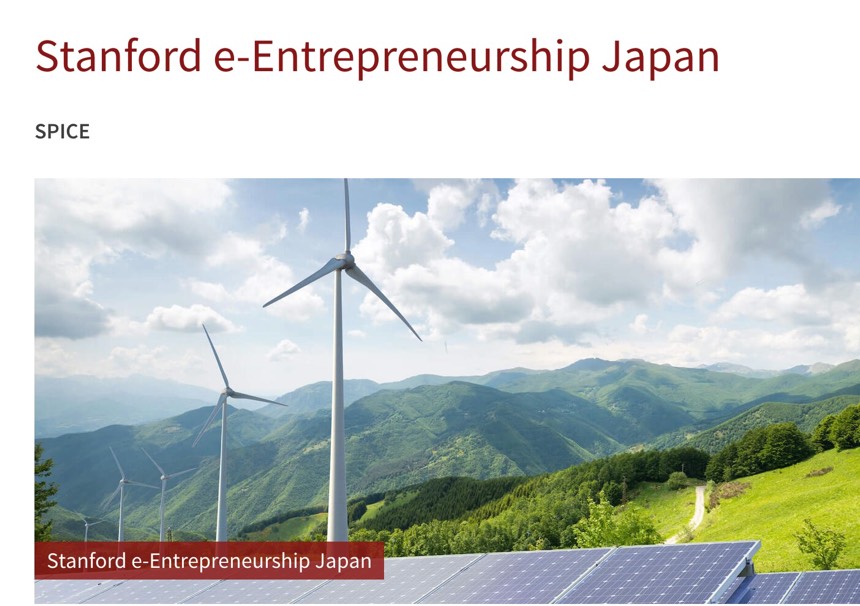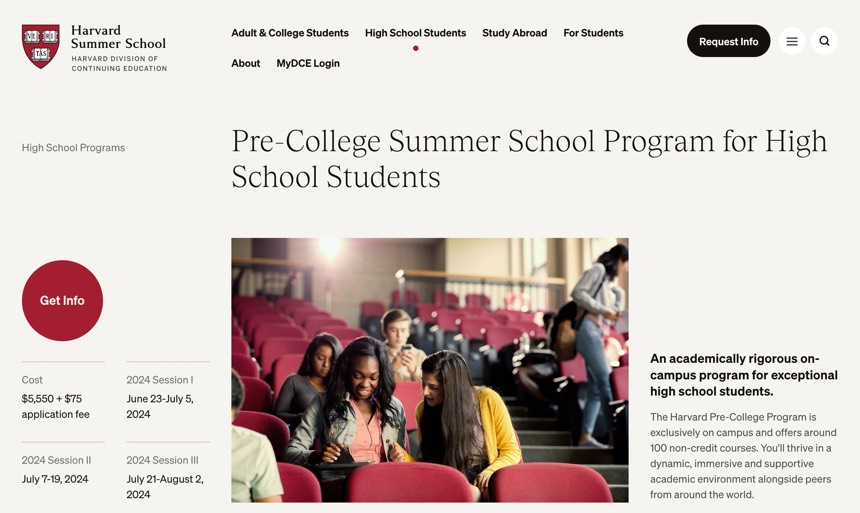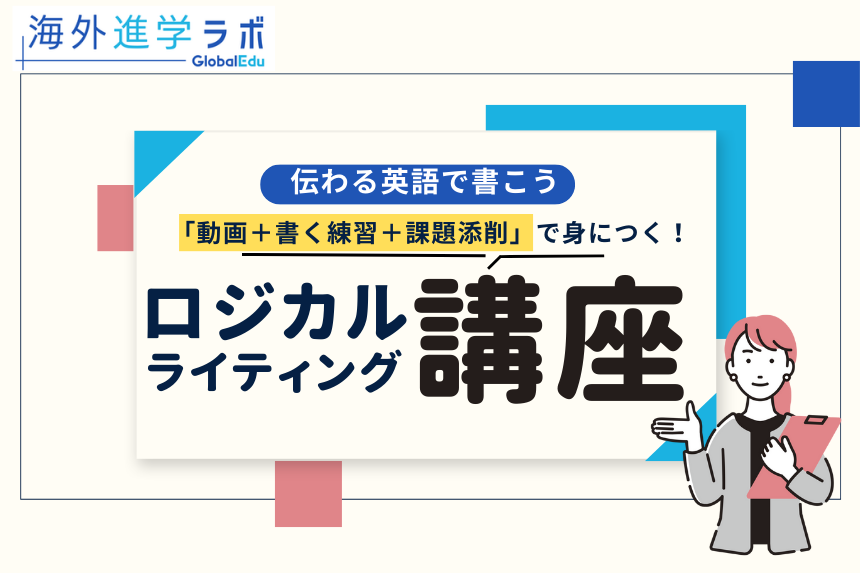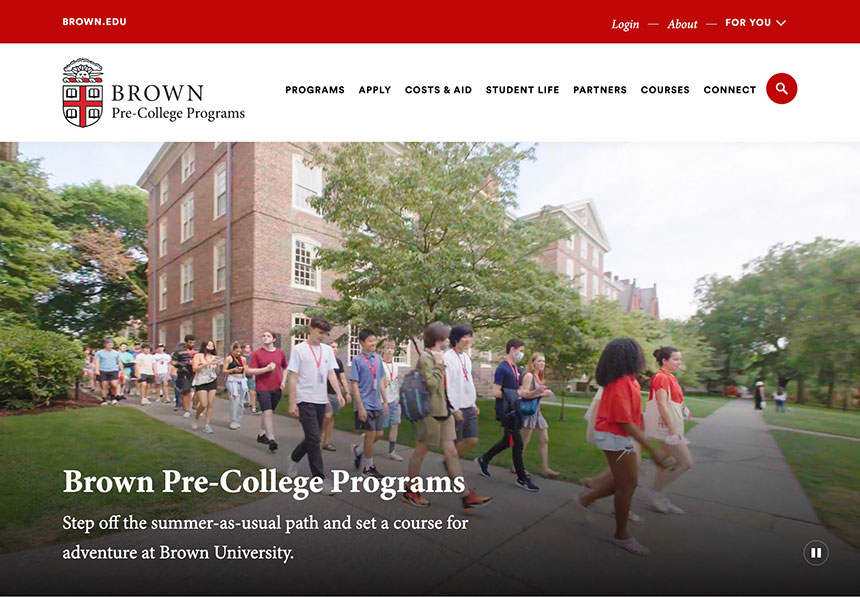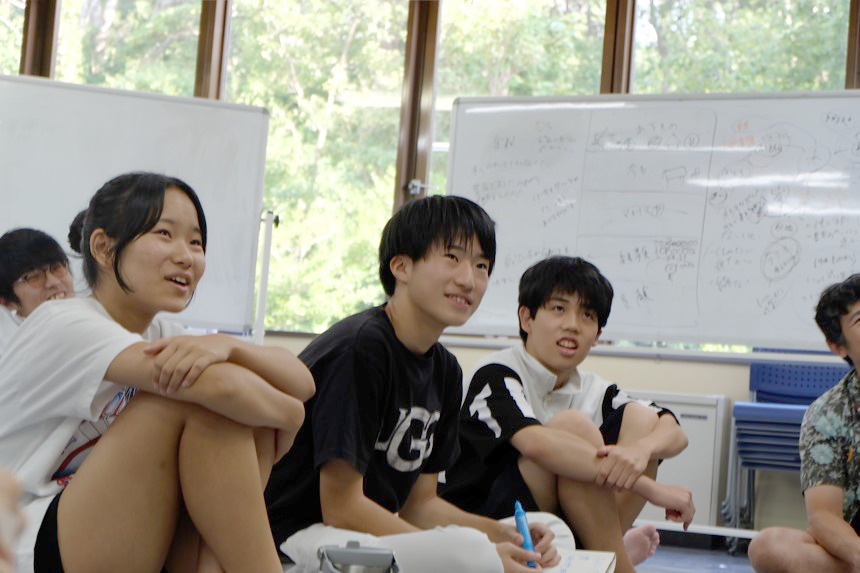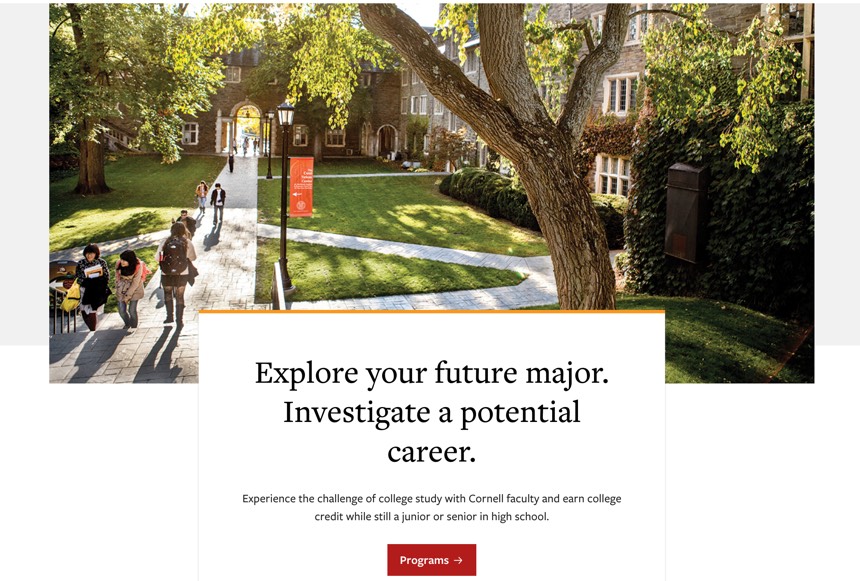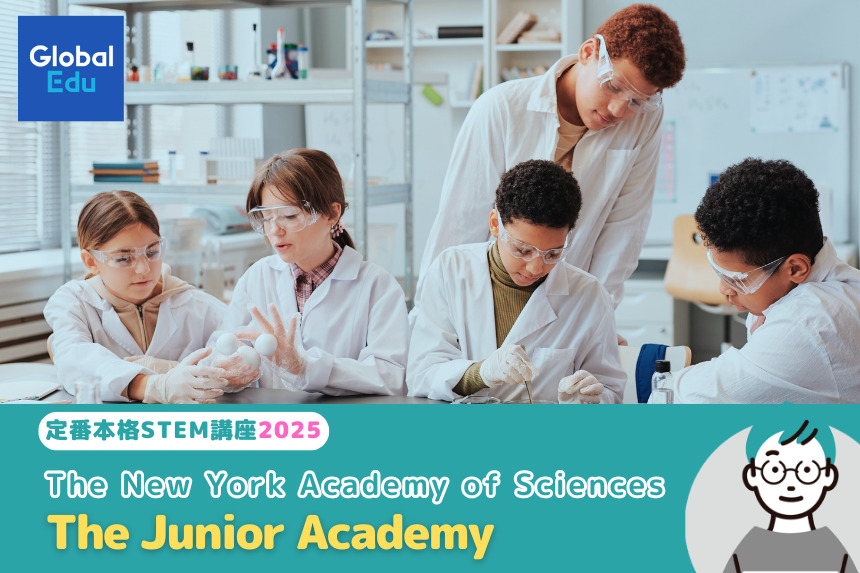課外活動に参加しよう– Challenge Program –
-

Re:Route|多様な進路選択を後押しする高校生コミュニティ型プロジェクト
-

ESAアジア教育支援の会ユースチーム | 教育格差に向き合う学生ボランティア募集!
-

グリーンバード| 全国・海外に広がる「ごみ拾いからはじまる」“まちと人”のつながり
-

ECOFF|田舎に住み込んで地域と出会う“村おこしボランティア”
-

生徒会@GTE|世界とつながる!中高生のためのアントレ×政策提言の学び場
-

We Kids United|医療×教育支援を行うユース主導の国際ボランティア団体
-

Stanford e-Japan 2025秋│意欲的に日米関係を学び課題に取り組む高校生無料オンライン講座 8/17〆
-

7/10開催!進路につながる課外活動ガイド 2025夏 | 教室の外に、ほんとうの学びがある。
-

明星サマースクール2025 | 世界からの国際ボランティアとも交流できる6日間小中高生英語プログラム 6/30〆
-

ジュニア・アチーブメント2025 | 3ヵ国からなる多国籍高校生チームで日本の魅力を発見&発表する全英語無料プログラム 7/25〆
-

高校生のためのアジアの言語と文化2025 | 4日間でスペイン語・韓国語・中国語・インドネシア語を学ぶサマースクール 7/7〆
-

早稲田大学ユニラブ2025 | 約30の科学実験プログラムを用意小中学生1500名程度募集 7/7〆
-

7月イベントカレンダー2025 | 新しい学びと出会うチャンス!応募締切日や開催日をチェック
-

ワールド・ビジョン・サマースクール2025 | 世界を知ることで未来も広がるオンラインイベント各500組7/14〆、対面イベント各50組 6/23〆
-

テンプル大学サマー英語プログラム2025 | 小学生講座から米高校生と学び合う7日間まで1000名を募集 6/13,6/30,7/27〆
-

おもてなし親善大使2025 | 英語で外国人旅行者へのおもてなし手法が学べる夏休みの2日間…中高生200名 6/30〆
-

千葉大学ASCENT-6E 2025 | 科学技術+データサイエンスの基礎力を身につけ、大学で研究を行う高校生40名 6/15〆
-

KEIO WIZARD 2025 | 宇宙・防災・医療・環境などの身近な課題を学ぶ…小5~中3対象「GLOCALベーシックコース」40名 6/30〆
-

SFC未来構想キャンプ2025 | 慶應SFC、京都、鳥取の3会場で6つの高校生ワークショップを開催約110名 6/12〆
-

LEARN with Porsche 2025 | 東大と連携した5日間のイノベーティブな中高生無料サマープログラム 6/15,29〆
-

2025 Global Essay Prize | 世界トップ大の教授陣が審査…幅広い課題探究に挑戦する中高生のエッセイを募集 6/30〆
-

子ども大学グローバル2025 | 深い思考や地球規模のユニークなテーマで学ぶハイブリッド型全7回小中学生講座 5/30〆
-

Cambridge Re:think Essay Competition | 受賞者はケンブリッジ大でのディナーに招待…国際的な中高生エッセイコンテスト 5/10〆
-

女子中高生夏の学校2025 | 理工系のセンパイと出会いその魅力を体感する3日間サマーキャンプ90名 6/13〆
-

STEM講座10選2025 | トップ大学などが主催する、小中高生対象の人気定番講座を見逃すな!
-

埼玉大学STEM教育研究センター | 6つのテーマでプログラミングを学ぶ「ロボットと未来研究会2025」こども研究員約60名
-

エアロスペーススクール2025 | JAXA高校生サマースクールが北海道・宮城・筑波・東京の4会場で計75名を募集 5/15〆